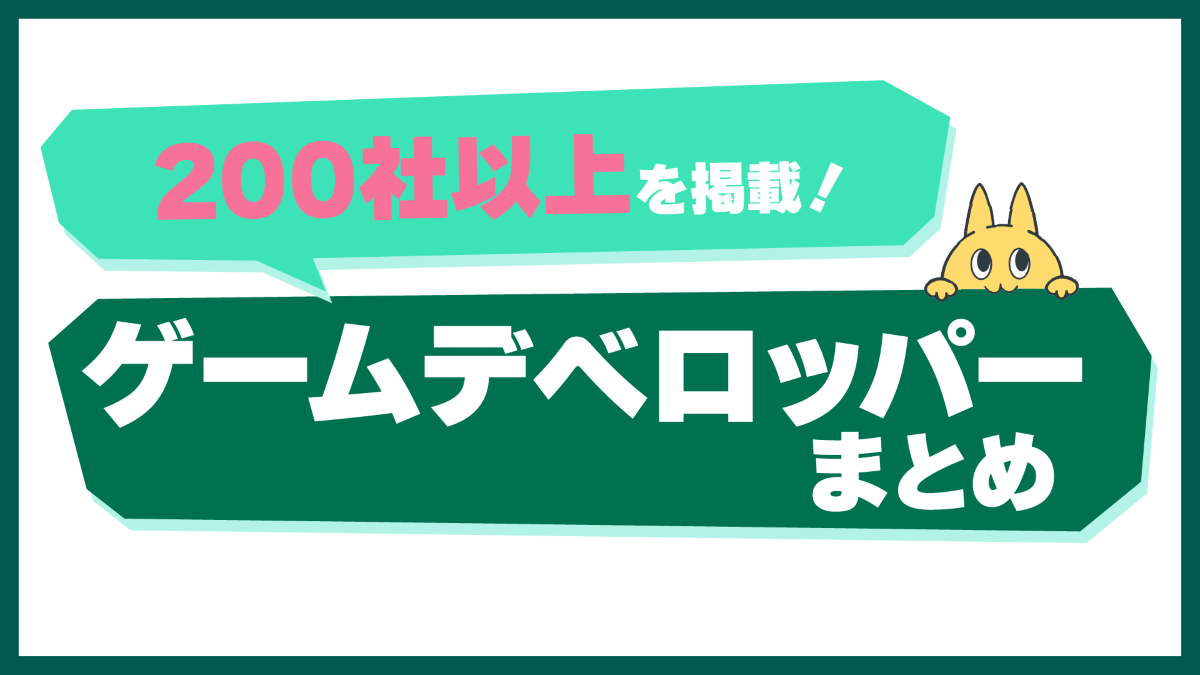Godot Japan User Communityが主催する、Godot Engine(以下、Godot)の勉強会「Godot Meetup Tokyo Vol.2」が2024年7月26日に開催されました。
本稿では、GodotにおけるApple Vision Pro向けアプリケーションの開発手法や、エンジン開発チームによるアニメーション機能のアップデート内容などが語られた本イベントの様子をレポートします。

Godot Japan User Communityが主催する、Godot Engine(以下、Godot)の勉強会「Godot Meetup Tokyo Vol.2」が2024年7月26日に開催されました。
本稿では、GodotにおけるApple Vision Pro向けアプリケーションの開発手法や、エンジン開発チームによるアニメーション機能のアップデート内容などが語られた本イベントの様子をレポートします。
TEXT / 神谷 優斗
最初に行われたCRI・ミドルウェアによるセッションでは、同社が提供するサービス「CRIWARE」および「OPTPiX SpriteStudio」におけるGodotへの対応状況が語られました。
サウンドツール群「CRIWARE」は、Godotでは「CRIWARE for C#」を通して使用します。
CRIWARE for C#は、C#の開発環境でCRIWAREを扱うプラグインで、2024年8月のリリースが目標となっています。講演時点ではGodot 4での動作が確認できており、将来的にLE版も用意される予定です。
セッションでは、2Dアニメーション作成ツール「OPTPiX SpriteStudio」で制作したアニメーションをGodot上で再生する「SpriteStudioPlayer for Godot」も紹介されました。
SpriteStudioPlayer for Godotは、講演時点でGodot 3.6に対応済み。Godot 4への対応は進行中とのことです。
Gotcha Gotcha Games 開発部 森野 友介氏によるセッションでは、ベースエンジンにGodotを採用した「RPG Maker(旧:RPG ツクール)」シリーズ最新作『ACTION GAME MAKER(以下、アクツク)』の詳細が語られました。
セッションでは、Godotとアクツクの相違点として以下が紹介されました。
UIはGodotのものをそのまま使用しているそう。これにより、Godot向けのプラグインなどがそのまま使える利点があります。
講演時点でのアクツクはGodot 4.1をベースにしており、今後はGodot 4.3ベースにアップデートする予定であるそうです。
ふぉるた氏によるセッションでは、Godotのエディタを拡張するツールを実装する手法が解説されました。
Godotでは、スクリプトに「@tool」アノテーションを付与することで、処理をエディタ内から直接実行できるようになります。
Godotにおけるエディタ拡張にはエディタプラグインを制作する方法もありますが、@toolを使うとエディタプラグインを実装する手間が省けます。一方で、1つのスクリプトファイルにゲーム用のコードとツール用のコードが混在するデメリットも持ち合わせます。
その対策として、関数の実行時にエディタ内かどうかを判定する関数を用いて処理を分岐させるテクニックが紹介されました。
Godotには、エディタ内でのみ使用できるクラスがいくつか提供されています。セッションでは、ふぉるた氏が薦める2つのエディタ専用クラスが紹介されました。
1つめの「EditorScript」は、スクリプトエディタから実行できる処理を定義するクラスです。RPG Maker用の画像素材をGodotのタイルセットに一括で変換するツールが使用例として紹介されました。
2つめの「EditorScenePostImport」は、3Dモデルなどのインポート時に行われるシーンの生成に、独自の処理を追加できるクラスです。マテリアルの差し替えや、別々のモデルを1つにまとめる処理などを自動で実行できます。
続いてはYuumayay氏が登壇。講演時点で15歳の同氏は、Godotを始めて1年3か月の間で56作品を制作したそうです。
#GodotMeetupTokyo で2DプラットフォーマーRTAをするときに使ったpdfをアップしました。当日は、Godotを始めて1年3ヶ月の間に作った56作を無理やりまとめた動画を流しました。https://t.co/Mmzp3WX5R9#Godot #GodotEngine #gamedev https://t.co/MeR7fd433D pic.twitter.com/bzfekCaHmF
— ⭐Yuumayay⭐ (@yuumayay) July 27, 2024
Yuumayay氏の作品をまとめた動画
セッションでは、「RTA(※)」を模して、Godotで2Dプラットフォーマーを完成させるまでのタイムアタックを実演。
※「Real Time Attack」の略称。ゲーム開始から、ゲームクリアなど特定の状態に到達するまでの時間を競う
わずか2分27秒で、操作できるプレイヤーキャラクターと地面が存在する2Dプラットフォーマーが完成しました。
なお、同氏が主催するゲームジャム「Godotでゆるっとゲーム制作祭」は、冬頃に次回開催が予定されています。
shiena氏によるセッションでは、Apple Vision Pro用のアプリケーションをGodotで開発する手法が解説されました。
Apple Vision Pro向けアプリケーションの開発には「GodotVision」ライブラリを使用します。GodotVisionを使用すると、AR開発フレームワーク「RealityKit」とGodotの橋渡しが可能になります。
GodotVisionを使うと、RealityKitが入力とレンダリングを担うようになる(画像はGodotVision公式サイトより引用)
GodotVisionのサンプルプロジェクトはGitHubで公開されている
ジェスチャー認識は「ドラッグ」「回転」「拡大・縮小」の3つに対応。
一方、講演時点では以下の機能には対応していません。
セッションでは、実際にGodotのプロジェクトをApple Vision Pro上で実行する様子が実演されました。
Godotのアニメーションチームであるトカゲ氏は、Godot 4.0からGodot 4.3までに施されたアニメーション機能への改修について説明しました。
Godotにはキーフレームアニメーションを再生する2つのノード「AnimationPlayer」「AnimationTree」が実装されています。しかし、従来では両者が異なる親クラスを継承していたため、同じ役割を持ちながらも別々に実装されている機能が存在していました。
そこで、Godot4.3では共通のAnimationMixerクラスを継承するよう変更。これにより実装が一本化したほか、今まで潜在的に存在していたブレンドなどに関するバグが修正されました。
Godot 4.3におけるアニメーション機能の改修については、Godot公式ブログでも説明されています。なお、同氏はVRM 1.0への対応に向けて準備を進めているとのことです。
講演後の懇親会でも、参加者同士がGodot特有の開発事情や日頃の業務に関する情報交換などを行っており、日本におけるGodotの盛り上がりが感じられました。次回は2024年11月の開催が予定されています。
「Godot Meetup Tokyo Vol.2」イベントページ「Godot Meetup Tokyo Vol.2」アーカイブ動画コーヒーがゲームデザインと同じくらい好きです



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。