IGDA日本のオーディオ専門部会、SIG-AUDIO主催によるセミナー「SIG-AUDIO 2024 Vol.03 オンラインセミナー「パネルディスカッション: ビデオゲームの振動デザインについて」が2024年3月8日(金)にオンラインで開催されました。
パネルディスカッションには第一線でゲームサウンド業務に関わる4名が参加。「良い振動とは何か?」から、アクセシビリティとしての振動、触覚としての振動、そして振動にまつわる知見やスケジュールの必要性が訴えられた本セッションをレポートします。

IGDA日本のオーディオ専門部会、SIG-AUDIO主催によるセミナー「SIG-AUDIO 2024 Vol.03 オンラインセミナー「パネルディスカッション: ビデオゲームの振動デザインについて」が2024年3月8日(金)にオンラインで開催されました。
パネルディスカッションには第一線でゲームサウンド業務に関わる4名が参加。「良い振動とは何か?」から、アクセシビリティとしての振動、触覚としての振動、そして振動にまつわる知見やスケジュールの必要性が訴えられた本セッションをレポートします。
TEXT / じーくどらむす
EDIT / 神山 大輝
今回パネルディスカッションに参加したのは、CEDEC2023で「振動のフォーリー録音!? サウンド技術で振動攻略 ~音と振動はだいたい同じ~」講演を行った株式会社スクウェア・エニックス サウンドプログラマー山本 雄飛氏と、2023年に同社より発売された『FORSPOKEN』のゲームデザイナーとして振動やプラットフォーム機能の仕様作成・実装に携わった株式会社スクウェア・エニックス(当時、株式会社Luminous Productions所属)の松本 風雅氏。
この2人に加えて、サウンドデザイナー・サウンドディレクターの立場から振動への興味関心が尽きない株式会社コネクテコ 代表取締役 サウンドディレクター 北村 一樹氏、株式会社DETUNE代表取締役社長 佐野 信義氏が参加し、「振動デザイン」をサウンド側が担当するメリットや課題を整理しました。
佐野:
松本さんは「良い振動」ってなんだと思いますか?
松本:
『FORSPOKEN』の開発において良い振動とは何かを考えた結果、「この振動が何を示しているのかが直感的にわかるもの」が良い振動という定義をしていました。
佐野:
「(プレイヤーが)納得できる」ということですよね。
松本:
そうです。逆に言うと「なんでこのコントローラー、今このタイミングで振動してるんだろう?」というのが分からないと、それは良い振動ではなくなります。「なぜ振動しているのかがハッキリ分かる」ということを突き詰めていけば、品質の向上につながるのではないか、とチーム内では話し合っていました。
佐野:
それもサウンドの考え方と近いですね。ゲームで「なにか音が鳴っているんだけど、これって何の音?」となるとやっぱりバグのように捉えられるし。北村さんは、これまでに振動が印象的だったゲームはありますか?
北村:
やっぱり『ASTRO’s PLAYROOM』ですね。振動表現を突き詰めるとこうなるんだな、というお手本を提示してくれていて、フォースフィードバックも合わせて気持ち良い体験になってました。
手が振動を検知するキャパシティは耳が音を検知するキャパシティより小さいというか、「震えてる」から「震えてない」までのレンジが小さいので、ダイナミックレンジの付け方が繊細だと感じています。いま震えさせているなら、このあとしっかり振動「させない」時間を作るみたいに、アップダウンをつけていかないと良い振動にならないと思いました。
『ASTRO’s PLAYROOM』ゲームプレイトレーラー(YouTubeより引用)
佐野:
普通の音作りよりもメリハリが大事なんですね。ちなみに「嫌な振動」ってありますか?
山本:
具体的には言えませんが、抽象的に言うと「しつこすぎる振動」でしょうか。あまりにも強くて、ずっと振動していると、手がしびれてきて鬱陶しくなってしまいます。
北村:
そんな感じがしますね。ずっとブルブルしてるとギャップが分からなくなってしまう。取捨選択が重要そうです。
佐野:
北村さんとしても、振動はサウンドの新たな側面というか、サウンドの新たな出力先のような捉え方をしていますか?
北村:
僕の感覚としては、ハプティクス(触覚)デザイナーはサウンドデザイナーとはまた別の新しい職種としてあるべきなんじゃないかと思っています。必要とする知識は近いですが、考えるポイントが違うんですよね。周波数の切り方の観点も違いますし、音量の出し方、コンプレッションのかけ方、ADSRへの考え方なども音と振動でまったく違うものになると思います。
松本:
私自身も「これは新しい職種ができるな」と感じていました。「振動」を使って「触覚」を表現すると決めたら、今までとは認識を変えなければいけません。
振動とともに提示されるビジュアルとサウンドが合わさることで、触覚が成立するというメカニズムを意識する必要があります。サウンドの知識とゲームデザイナーの知識を兼ね備えつつ、システムエンジニアの知識も要求されるという難しい分野ではあります。
山本:
振動の開発環境を整えるのが自分の仕事ですが、DAWで作った音を書き出して、書き出した音を振動確認するためのソフトに入れてようやく確認できる、という工程が大変だったので、DAWから直接確認できるようなVSTプラグインを作っています。
振動をプレビューするときは当然コントローラーを手に持つんですけど、そうすると右手でマウスを持って再生ボタンを押してすぐ右手をコントローラーに戻すというのが結構面倒なんです。なので、コントローラーだけで振動のタイミング調整ができるツールなんかも作っています。
佐野:
めちゃめちゃいいですね、それ。
北村:
私も振動を作っていたときに、マウスで再生してコントローラーに持ち替えて、再生して持ち替えて、というのがすごく面倒で。もうループ再生するしかないみたいな。そういうツールがあるとすごく楽になりそうですね。
佐野:
マウスとコントローラーの持ち替え問題に対しては、フットペダルで再生ボタンを押すというのもアリですね。
松本:
コントローラーで確認するために手が塞がってしまうのは避けて通れないので、DAW自体をコントローラー持ったまま操作できると嬉しいですね。また、DAWからのプレビューだけではなく、実際にエンコードされてゲーム中に実装されたものに即座に振動を反映できたりすると、さらにありがたいです。
山本:
エンコードするだけでも手触りが微妙に変わってしまうこともあります。振動は、データとしては音と同じ波形データなので、特定の周波数帯の情報量を削るなどして圧縮するわけですが、それで振動を感じるのに大事なところが削られたりすると手触りが変わってしまう、ということが起こり得ます。
佐野:
「新しい圧縮フォーマットが必要になりそう」という会場からのコメントもありましたが、まさにそうですよね。圧縮フォーマットは聞いたときに違和感が少ないように調整されてますから、振動向けには現状だと不向きという事ですよね。
山本:
そうですね。エンコード以外にも、手が感じ取れる周波数は最高でも1,000Hzくらいなので、サンプリング周波数自体を2,000Hくらいにしてしまっても良いかもしれません。
北村:
素人考えだと、例えば登録しているSEの波形にローパスフィルターをかけて振動に送るだけで良いのでは?という発想もあるんですが、実際そうは上手くいかなさそうですよね。
山本:
はい。例えば3Dで鳴っている効果音は距離によって減衰しますが、振動のほうは減衰させたくない、という状況がすぐに出てきます。
松本:
ゲームデザインの都合で「このタイミングだけこの振動をなくしたい」という状況が出てくるので、サウンドとは別のパラメータで制御する必要がありますね。『FORSPOKEN』では、とあるボス戦で主人公の感覚を奪うというギミックがあり、そのときに振動を消す演出がありました。
北村:
CEDECでは山本さんが振動のフォーリー録音のセッションをされていましたが、実際にフォーリーと一緒に振動も録ってしまうというのは作業効率が良いんでしょうか?それとも、録ったは良いものの、後からエディットが大変などはありますか?
山本:
振動している物体は3次元的に振動していて、波形として1次元にする際にどの成分が最適かは分かりません。3軸すべてを取得し、後から取捨選択するという工程が必要なため、効率としては必ずしも良くないですね。また、収録する信号のレンジ自体も録りたい振動に応じて調整します。衝撃のようなものはセンサーの都合で完全にクリップしてしまうので諦めて、もう少し繊細な振動に特化してやっていますね。
松本:
『FORSPOKEN』の開発ではコントローラー振動を含めたプラットフォーム機能を担当するチームがあり、私はそこでLead Platform Functionality Designerとして仕様作成や実装を担当していました。そこで、振動をどうやって作り、どういうデータ構成にするかをプログラマーと議論してサウンド部に発注する業務も行っていました。
「振動の波形って、どうやって発注したらいいんだろう?」と思いますよね。擬態語や擬声語(オノマトペ)を使って発注すれば良いのか、ブルブル!とか言っても、それってなに?とか。
ゲームデザイナーからの振動依頼はだいたいオノマトペで来るんですが、それをこちらで一次請けして、サウンド側に発注する際には「この振動はこのフレーム尺でフェードをかけてほしい」とか「左右にパンを振って欲しい」とか、そういった言葉を付け足してコミュニケーションを行っていました。
また、オノマトペで相談が来るな、という想定が事前にできたので「この単語がきたら、この振動を出す」というリストをあらかじめ作っていました。「ゴロゴロ」が来たらこれ、「サラサラ」ならこれ、とか。魔法やエフェクトの動きに合わせてフェードやカットを入れてバリエーションを作るなどもしていました。
佐野:
サウンドでも、コンポーザーとディレクターの間の通訳は必要になりますよね。
松本:
動画や音声のように「こういう振動」と共有できると良いんですけどね。他のゲームを起動して「こんな感じです!」と直接触ってもらって伝えたり、自分でそれっぽい振動を作ったりしてみてサンプルとして活用するとか。
アクションや移動に対する振動の波形作りはこちらでもできたのですが、カットシーンや尺がしっかりあって絵に合わせる必要があるものはサウンド部の協力が必要でした。
北村:
動作に紐づく「能動的な振動」はプランナーで、カットシーンなどの「受動的な振動」はサウンド、といった分け方になるんですね。それぞれで振動のディレクションは変わったりするんですか?
松本:
カットシーンは担当のディレクターがいたので、基本的にはその方に委ねていました。カットシーン中はコントローラーを置いて見ているプレイヤーさんもいらっしゃいますので、そのときにコントローラーが急に震えだして驚いてしまうとか、そのためにずっとコントローラー握っていないといけないのか?という問題点もあります。
松本:
カットシーン中、猫を撫でるシーンで「猫を撫でる振動」が欲しいという難しい発注がありました。悩んだ末に、草の上を走るときの振動パターンを弱めたうえで撫でるモーションに合わせて使うと「猫を撫でてる!」と錯覚することができて、面白かったですね。
北村:
立体音響のように画面のフォローがあることで錯覚が起こるんですね。
佐野:
どうやってその振動に行き着いたんですか?実際に猫を連れてきたんですか?
松本:
実家に帰って猫を撫でてきました。ちょっとフカフカな感じを確かめたり。その経験からそれっぽい振動を試しに作っていると、以前作った草の上を走るときの振動パターンに似てる、と気が付きました。
魔法の振動パターンを作るときも、川辺に行って石を投げてみたりとか。剣に炎を纏わせる魔法があったんですけど、木の棒に火をつけて振り回そうとしたら火傷したので、これはオススメしません。
佐野:
それもやったんですね!?
松本:
『FORSPOKEN』はフォトリアルな作品なので、外連味が強すぎると「なんでこの振動が出てるんだ?」という違和感が生まれて、最初に定義した良い振動にならないので。自分で体験するしかないなと。音を作るために実際の音を聞きに行く、ということに近いですね。
佐野:
UIの決定やキャンセルなど、アイコン的な振動もあるじゃないですか。そのあたりは難しくなかったですか?
松本:
アイコン的な振動のほうがやりやすかったですね。スマートデバイスが普及しているおかげで、そうしたデバイスの振動を参考にして、質感というよりも、目や耳が不自由な方にも「ちゃんと操作できています」という情報を伝えるアクセシビリティの役割と考えると、意外とシンプルな振動が作れました。
佐野:
なるほど、ゲーム以外のところにも振動のリファレンスがあるわけですね。
松本:
これから挑戦したいこととして、質感としての振動とアクセシビリティとしての振動を、別々に調整できると良いなと思っています。表現の幅が増えたことで、質感を表現して没入感を生み出すだけではなく、今までゲームを遊ぶことに不自由を持っていた方でも一緒に遊べるようなアクセシビリティとしての可能性を感じたので、演出的な振動も含めて全部入り・アクセシビリティのみON・完全にOFFのような調整ができるのではないかと思いました。
北村:
アクセシビリティとしての良さと演出としての良さ。この2軸でそれぞれ良い振動が定義できそうですね。
松本:
さらに言うと、(プレイヤーの)能動的なアクションも加えて3つの軸がある感じですかね。最終的な振動デバイスとしては1個の振動に混ざってしまいますが、そうなったときには優先順位の話が出てきます。
松本:
ゲーム中はさまざまな振動が再生されるので、そこのバランスをどう改善していくか、そのやりとりに苦労しました。「この敵がいて、この攻撃を食らった時に、この魔法の振動が重なってしまった」とき、みたいなシチュエーションが再現しにくくて。
北村:
なるほど。同時発音数リミット2とかの世界での優先順位の問題ですよね。
松本:
そこはもう少し力を入れて対応できたら良かったなと。振動の優先順位づけとか、サウンドで言うダッキングのような仕組みを入れたりに次は挑戦したいですね。
山本:
最近気づいたんですけど、振動を作り込むとQA(品質管理やデバッグ)が大変になるんですよね。
松本:
そうなんですよ!気づきましたか?振動のパターンが増えるとQAが大変なんです。そのQAが判断するための資料を作るのも大変で。現実的には「どのプラットフォームでも、このタイミングで振動がします」というドキュメントを作ることになりますが、プラットフォームごとに(振動機能に差があって)体験を変えます、という場合はそれぞれにドキュメントが必要になって、QA側の作業も大変になります。
プラットフォーム間でゲーム体験が違わないようにという気持ちもあるんですけど、個人的には各プラットフォームごとのデバイスの良さを活かしたいという気持ちもあって、そこはジレンマですね。
北村:
会場から「振動の記録と再生ができないと、意図したものと違う振動が出ている、という報告が不可能では」というコメントありましたが、まさにそうですよね。「変な振動してます」と報告が来ても、添付した動画ではそれが伝わりませんよね。
松本:
デバッグの時は、振動してるかしてないかだけで割り切っていましたね。そのうえで、明らかに尺が合ってない、途切れているなどはバグというよりクオリティという観点で修正点として挙げていました。
北村:
今は振動のQAが「ONかOFFか」だけになっていますが、今後クオリティが上がっていくと、QAとのやりとりでどこまで振動の再現性を追いかけていくのか、どういう振動の体験になっているかをどう情報共有するのか、さまざまな課題が見えてきますね。
松本:
質感の品質判断ってものすごく難しいんですよ。従来の「振動」のイメージのままでいる人と、今の時代の「触覚」として考え直している人の間で認識のズレが激しくて、そこを統一しないと、品質とは何か、この振動が良いかどうか、というのをレビューしにくいですね。
佐野:
「従来の振動」と「現代の触覚」の違いって、具体的にはどういうことですか?
松本:
昔の振動はON/OFFしかなかったんですよね。だから発注も「振動させてください」で良かった。そこに対して「どういう震え方が良いですか?」と返すと、固まっちゃうみたいな。今は振動の演出方法も多岐にわたっていて、考え方も変わっているという意識が担当のゲームデザイナーのみならず、サウンドの方やQAの方、ディレクターなどチーム全体で必要かと思います。
佐野:
「あなたの知ってる振動」とはもう違っている、という事ですよね。
松本:
そうです。仕様書でも振動という言葉は使わなかったです。「触覚」に書き換えました。
佐野:
なるほど。振動と言ってしまうと、さっきのON/OFFのイメージになるんですかね。
松本:
そうですね。もちろんその「振動ではなく触覚を表現する」という方針をチームの関係者を集めてプレゼンして、意識づくりをしていきました。それでも掴みきれなかったり、「振動」と言ったりしてしまう人もいるのですが。まずチームの意識づくりから、ですね。
佐野:
「振動デザイン」ってタイトルのパネルなのに「振動って言わない」って結論、いいですね。
北村:
そうですね、「触覚」ですね。
松本:
今回一番言いたかったのは、「振動を作る期間」を設けてもらいたいということですね。今までの作業工程って、モデルができて、モーションができて、エフェクトができて、そこに初めてサウンドが入ると思うんですけど、さらにサウンドの後に触覚をつけるという新しい工程が生じています。
北村:
サウンドが最下流工程でなくなる日が来るとは……
佐野:
サウンドを作る期間はゲームを作るうえで無視されがちというか、モーション、エフェクトできてたら音ももう出来てますよね?というガントチャートが引かれがち、みたいな。そんな中、サウンドが終わってから振動と言ってたら「それいつやんの?もう間に合わないよ?」となりますよね。
松本:
プロデューサーやディレクターなどの偉い方には是非「振動を作る」という期間をスケジュールに含めて欲しいですね。ゲームデザイナーは「振動を作る」という新たなタスクやその期間について、プロデューサーやディレクターと交渉していかなければいけないと強く感じています。
佐野:
そのためには、まず振動を好きになってもらわないといけないですよね。いきなりガントチャートを伸ばせといっても、乱暴な話かもしれませんので。私もなぜ最近になって振動に興味が出てきたかというと、今のコントローラーってステレオで振動できるんですよ。あれが楽しくて。
とあるゲームでキャラクターが左から歩いてくる足音をコントローラーに送ってみたら「ちゃんと左から振動してくる!」ということに感動して、振動は面白いなと思ったんですよね。新しい、特殊なサウンドの分野だなと。新しいものが好きなので、ぐっと刺さったんですよね。
佐野:
時間も迫ってきましたので、最後に皆さんから一言ずつお願いします。
山本:
技術開発はいろいろやらせていただいていましたが、実際のゲームに組み込むところの経験談を聞かせていただいて勉強になりました。
松本:
開発経験としては反省点が多くて、皆さんが聞きたいことが話せていると良いのですが。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
北村:
振動じゃなくて触覚というのがストンと腑に落ちました。あとはアクセシビリティと演出だったり、QAの課題といった今まで考えたこともなかった部分がインプットできたので非常に良かったです。
佐野:
お話していて大変楽しかったです。僕はSwitch版のKORG Gadgetという音楽制作ソフトを開発したんですけど、これで振動も作れたりしたらいいなという妄想を広げたりしてました。そうしたら「ハプティックDJ」みたいなのが生まれたりして!
もはや「振動」ではなく「触覚」。その役割は、驚きと興奮だけではなく、より繊細な質感を再現することによる没入やアクセシビリティを担保する意味での活用など多岐にわたります。
同じ波形データを取り扱うことからサウンド担当者やサウンドミドルウェアが振動機能の担い手として注目される中、本講演ではそれ以外のゲームデザイナー、QAセクション、そしてディレクターやプロデューサーまでも新たな視点で取り組まなくてはならない課題も見えてきました。
デバイス側の振動技術が進化する一方で、現場の意識づくりがこれから更に必要となる中において、本稿がその一助となれば幸いです。
フリーランスのサウンドプログラマー。スクウェア・エニックス在籍中に開発したインタラクティブミュージックシステム「MAGI」が「FINAL FANTASY XV」などに採用された。ゲームと音楽の融合を目指し、様々な音楽演出の研究、開発を行っている。
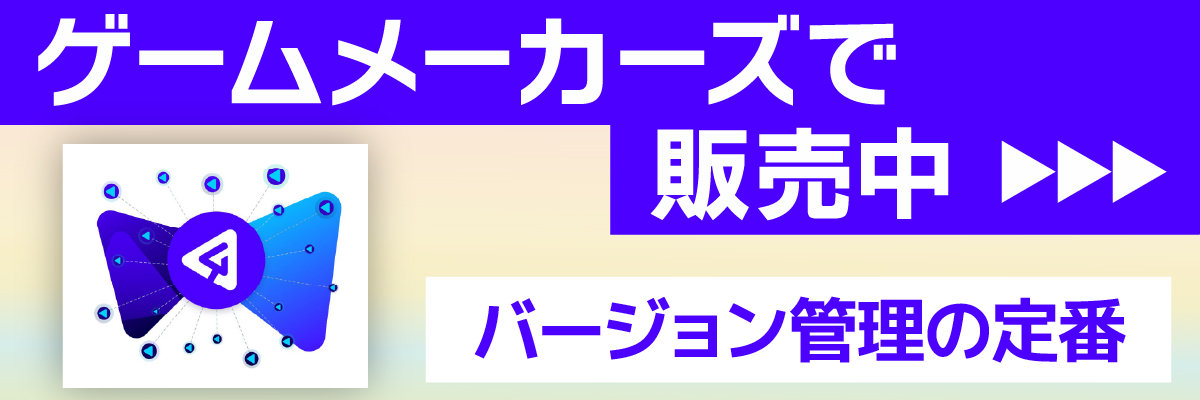
西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。




