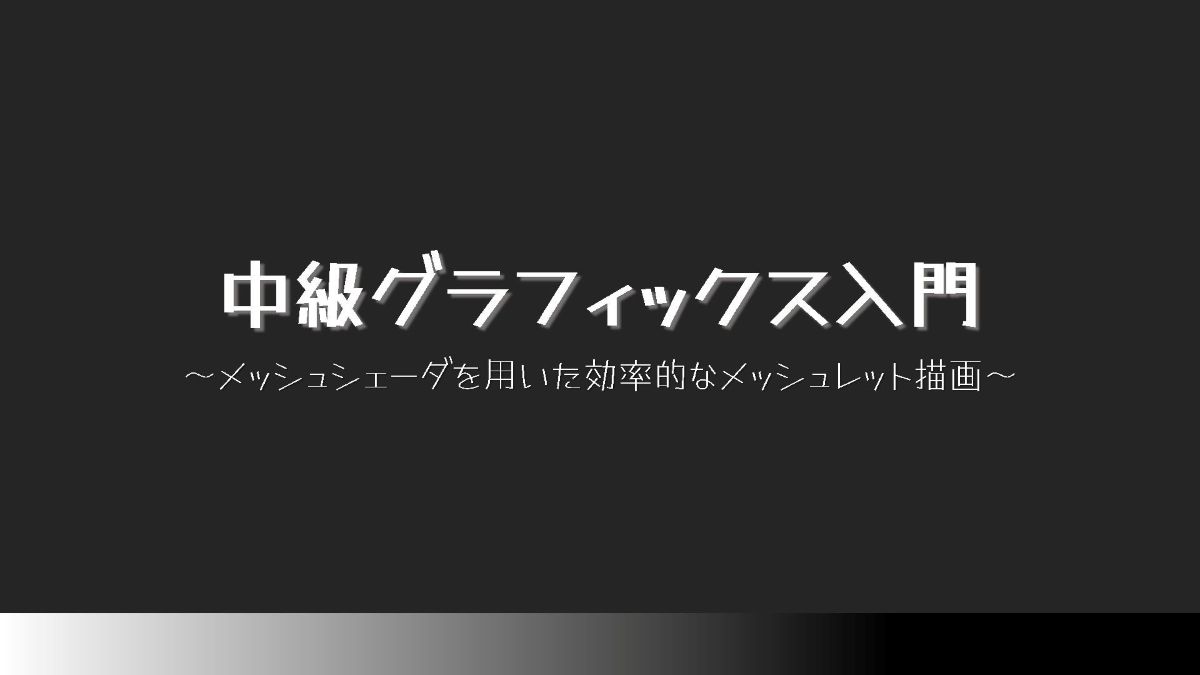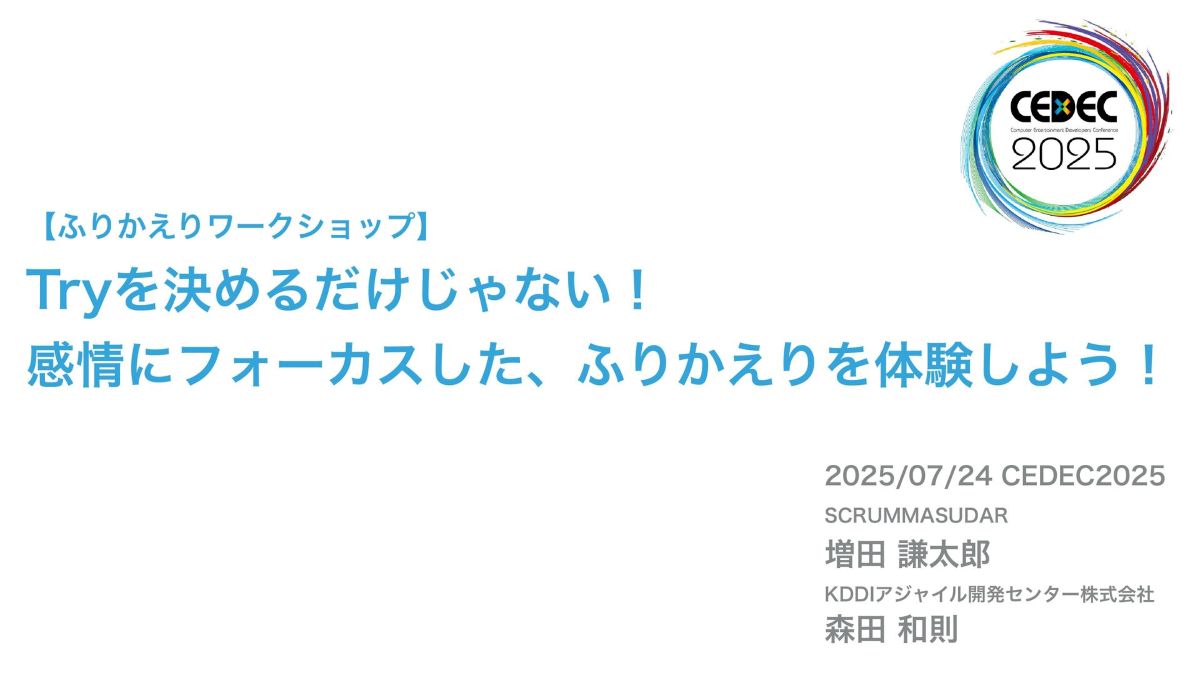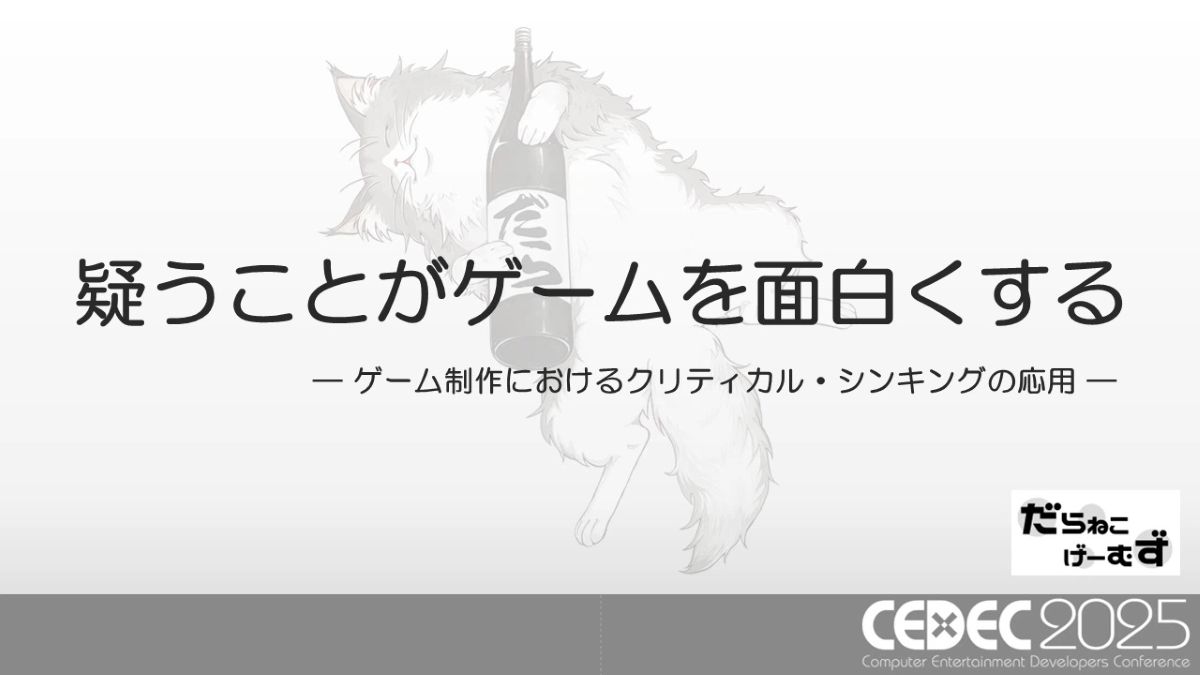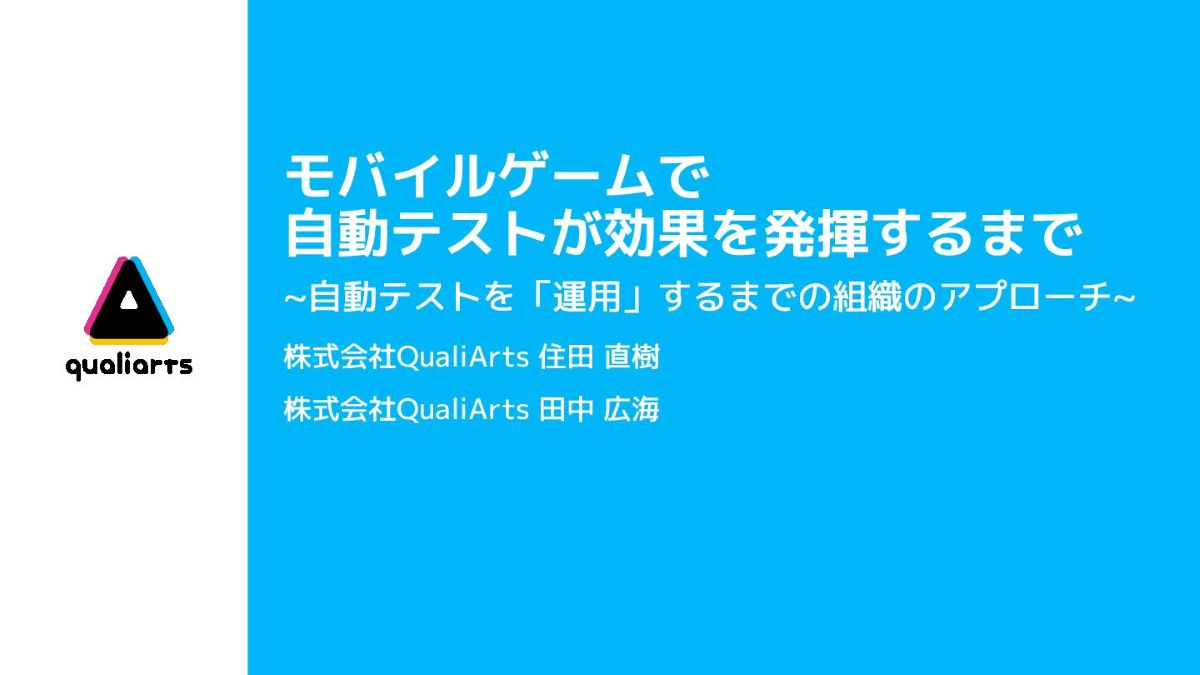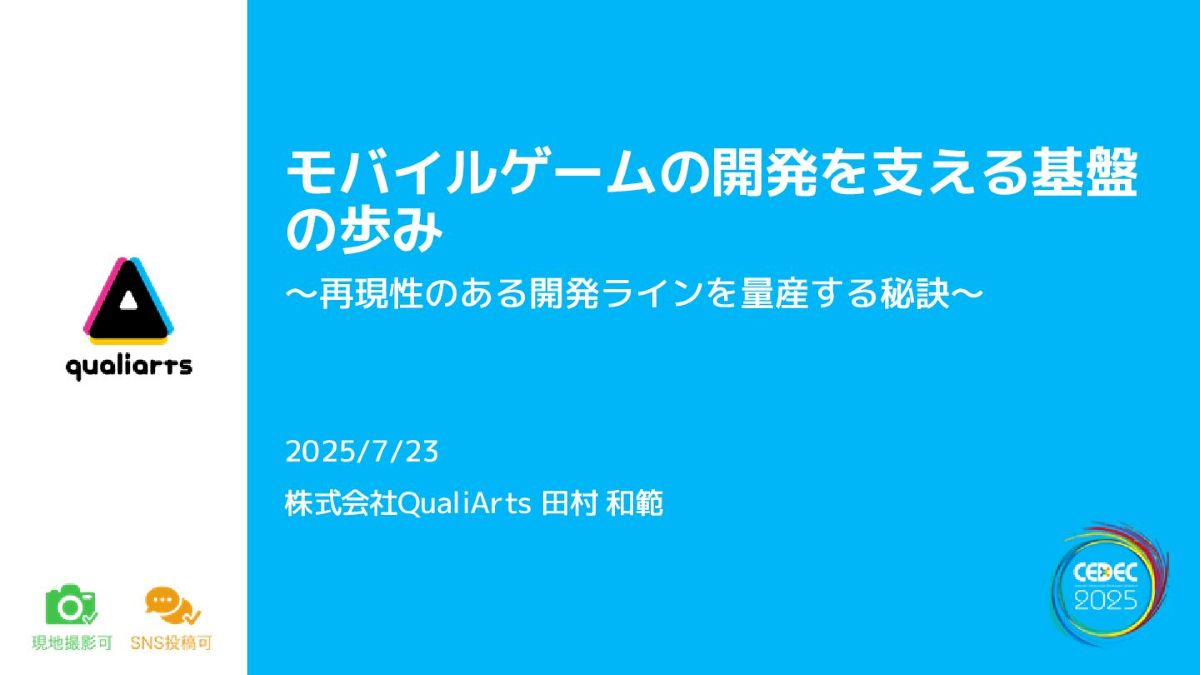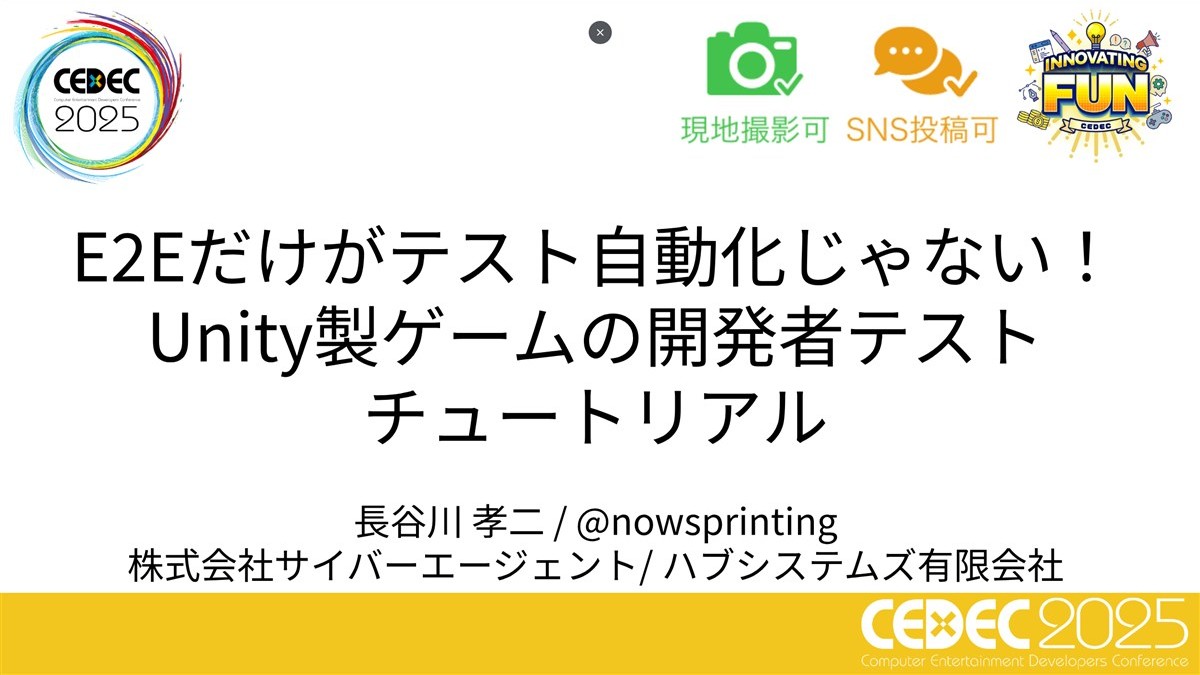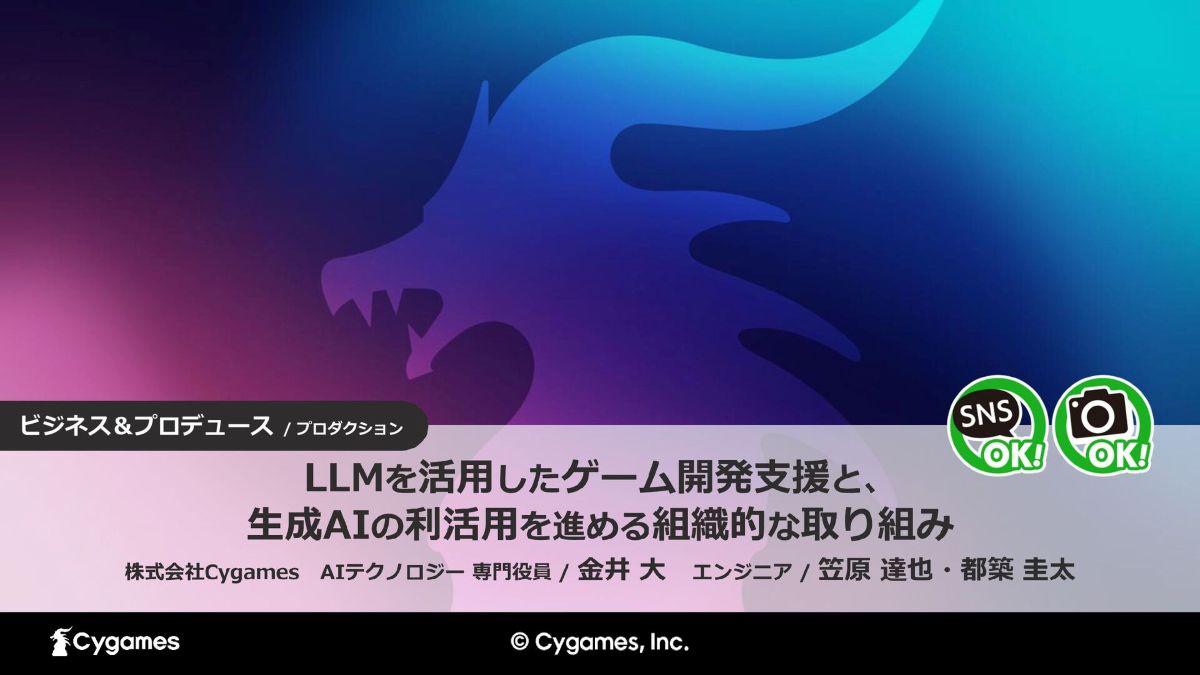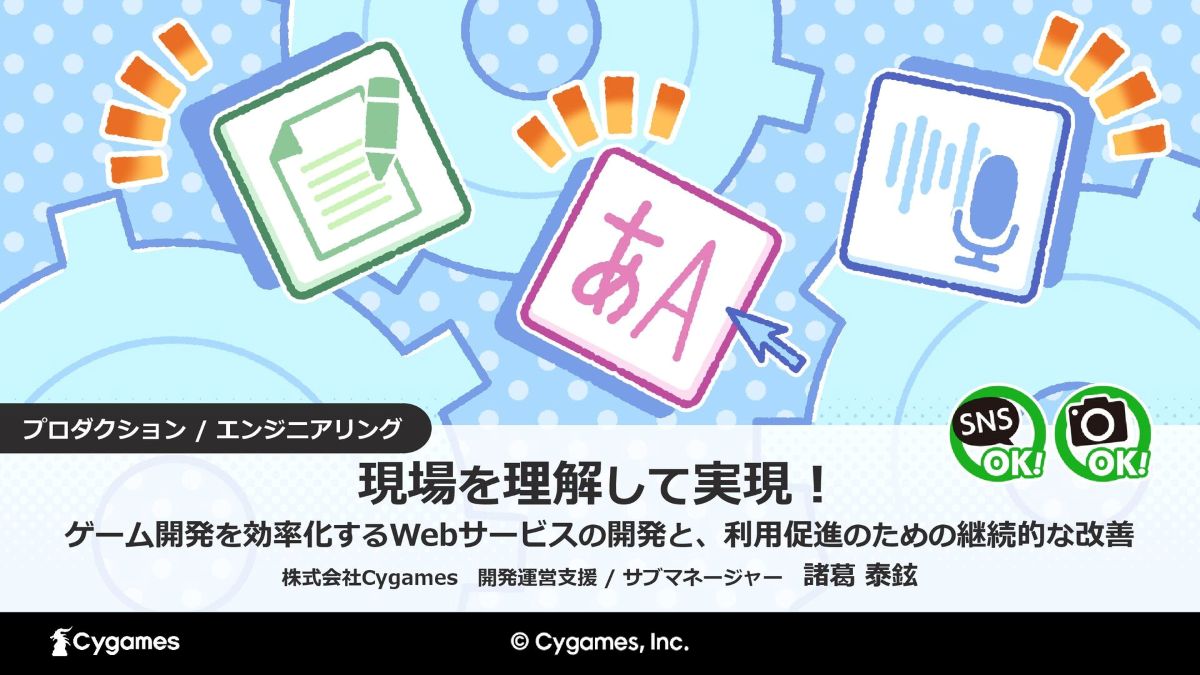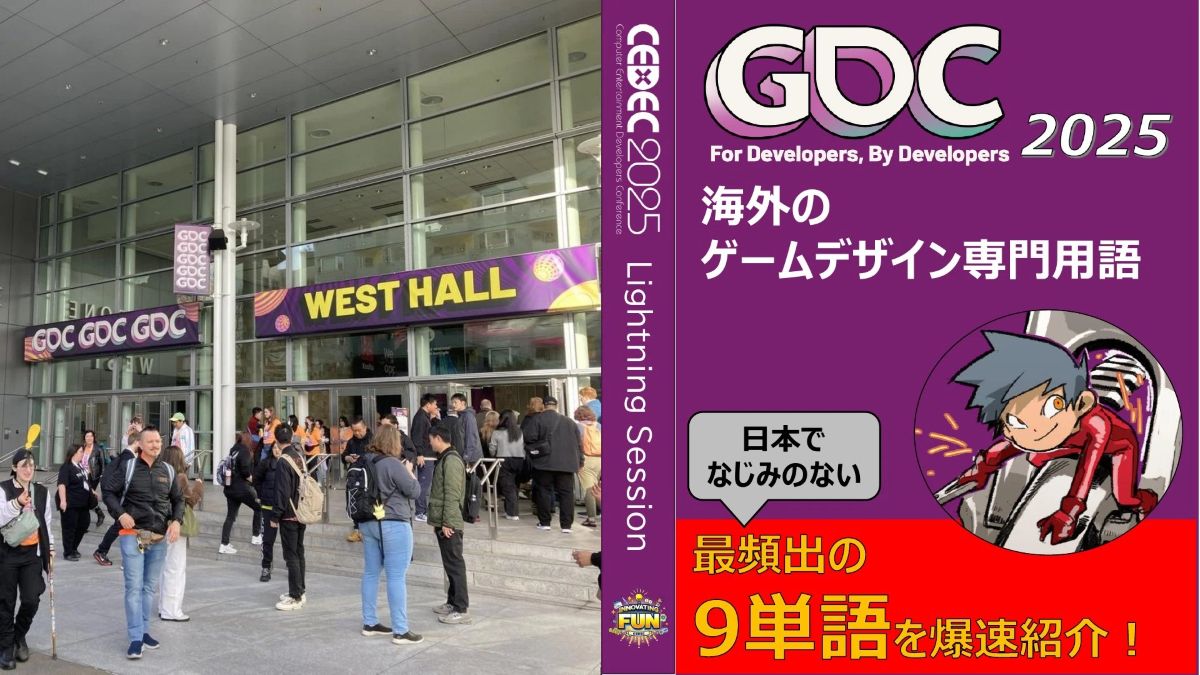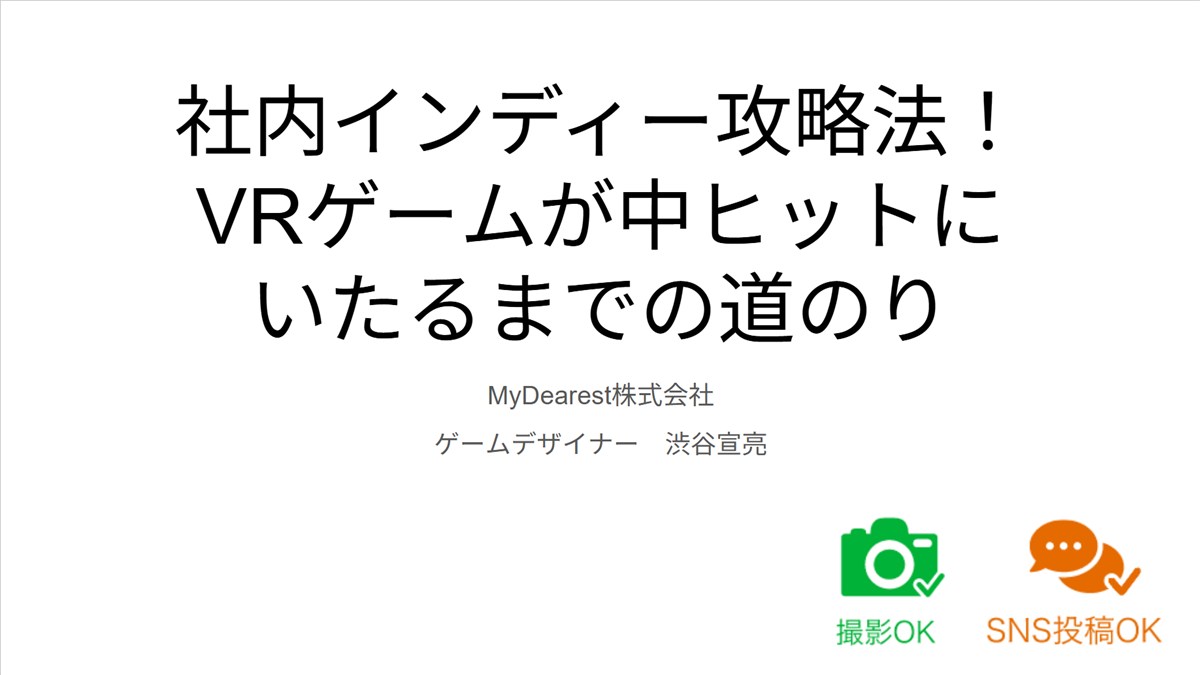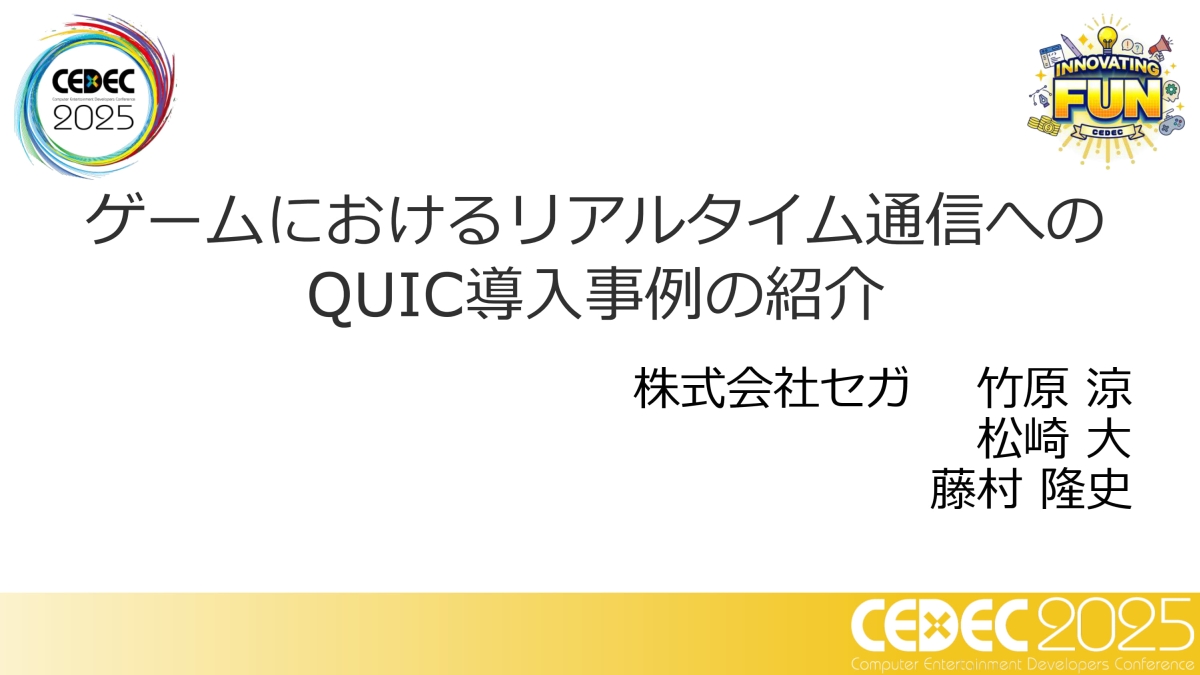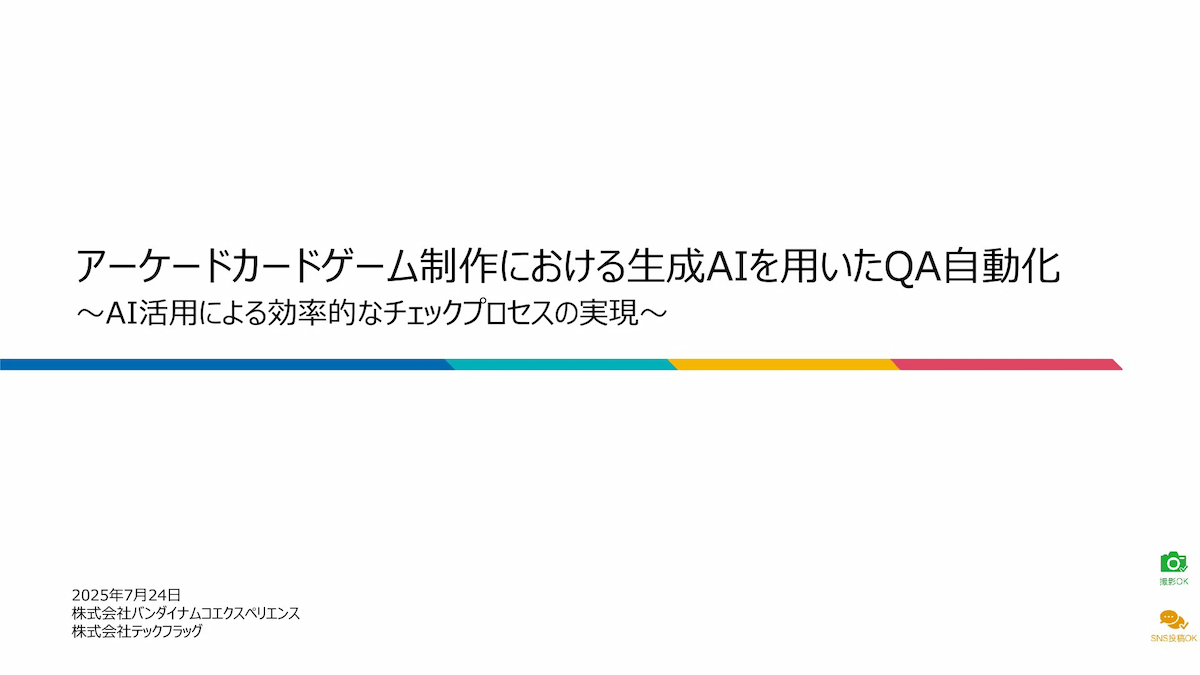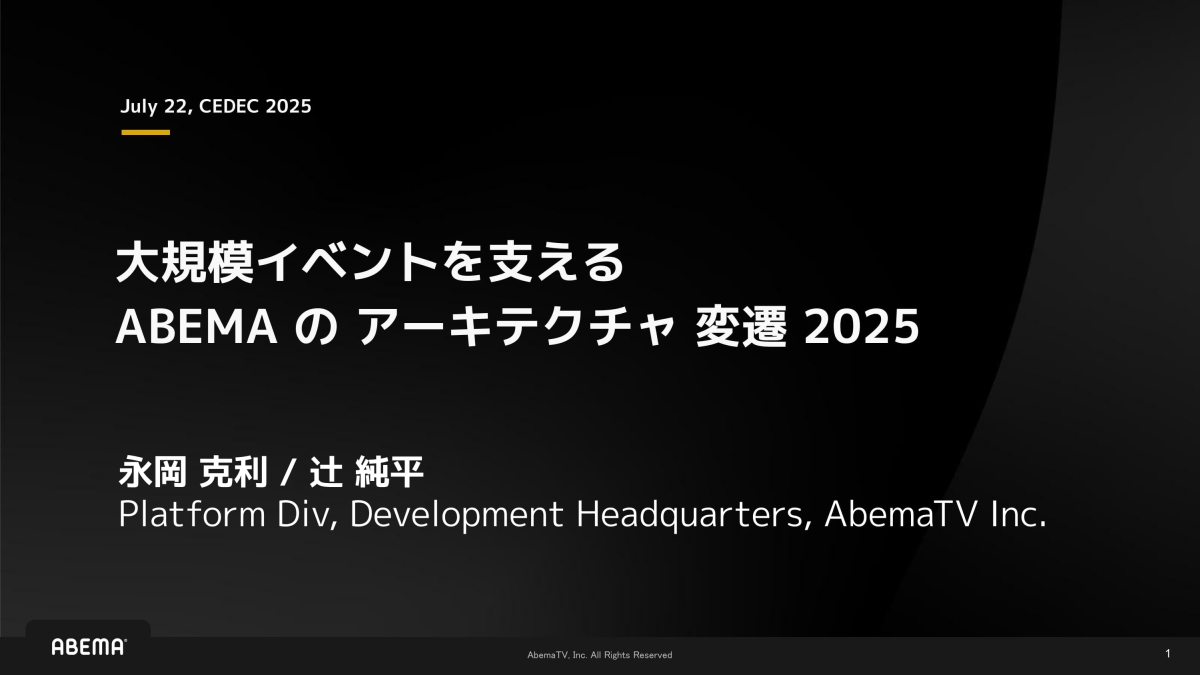本記事で紹介するスライド資料・フォローアップ記事一覧
各講演の紹介
中級グラフィックス入門 ~メッシュシェーダを用いた効率的なメッシュレット描画~
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
石橋 佳明 氏 |
ゲームエンジンを支える技術は年々進歩しており,中でもグラフィックス技術は年々複雑化の一途を辿り続けています。
『グラフィックスは難しくて良く分からない!』私の周りではそんな声も良く聞くようになってきました。
グラフィックス技術についての深い理解は,ゲームエンジンを利用する上でも,ゲームエンジンを作るうえでも非常に重要だと考えています。
そこで,本セッションでは,チュートリアルという形式を介してグラフィックス技術について理解を深めることを狙いとします。今回は,比較的に新しい技術であるメッシュシェーダと,メッシュレットをベースとした多段階LODシステムをトピックとして取り上げ,現代的なメッシュ描画について理解を深めます。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「中級グラフィックス入門 ~メッシュシェーダを用いた効率的なメッシュレット描画~」スライド資料【ふりかえりワークショップ】Tryを決めるだけじゃない!感情にフォーカスした、ふりかえりを体験しよう!
| 講演日 |
2025年7月24日(木) |
| 登壇者 |
増田 謙太郎 氏(SCRUMMASUDAR)
森田 和則 氏(KDDIアジャイル開発センター) |
ふりかえりを、プロジェクトの終わり・四半期といったタイミングで実施されている方は、ゲーム業界においても数多くいらっしゃると思います。しかし、反省会になってしまったり、Tryといわれる改善案を出すまで終われない経験をしている方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。
本来のふりかえりは、前向きな活動です。また、改善案を必ず出す必要もありません。ふりかえりに参加する方が、過去の事象とどう向き合ったのか、どのような感情を抱いたのかをチームメンバーと共有するだけでも、一人一人の行動は変わります。
本セッションでは、ワークショップを通してCEDEC2025の期間をふりかえります。より良いふりかえりを体験することで、明日からすぐに現場で活かす事ができます!
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「【ふりかえりワークショップ】Tryを決めるだけじゃない!感情にフォーカスした、ふりかえりを体験しよう!」スライド資料疑うことがゲームを面白くする ― ゲーム制作におけるクリティカル・シンキングの応用 ―
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
だらねこ(小笠原 健太)氏 |
ゲームを作る時は「コレは面白いゲームになるぞ」と希望に満ち溢れているものですが、しかし実際に作ってみた時に「あれ、思ったよりも面白くならないな……」となってしまうこともよくあることです。
そして作り直したけどやっぱり面白くならず、また作り直して、時間とお金を浪費して……となってしまえばプロジェクト的にも苦しい状況になっていくでしょう。
こういった状況はしばしば「想像した面白さに繋がらない仕様で作っている」「実装する仕様の問題点に気が付かずに作っている」といった考慮不足によって引き起こされます。
こうした問題を防いで実際に作ったゲームを面白くなるように、本講演では面白いゲームを作るための手法……の手前にある普遍的な「考える力」を高める手法として、研究分野などで使われている「クリティカル・シンキング」を紹介します。
ただしクリティカル・シンキングに関して紹介しただけでは実践レベルで使えるものにはなりません。
本講演では実際にゲーム制作の現場で起きる例を元に、実際にゲームデザインを考える際に落とし込むにはどうすればいいのか、気を付けるべきポイントは何か、クリティカル・シンキングを身につけるために何をしていけばいいのか……といった話も具体的にしていきます。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「疑うことがゲームを面白くする ― ゲーム制作におけるクリティカル・シンキングの応用 ―」フォローアップ記事モバイルゲームで自動テストが効果を発揮するまで ~自動テストを「運用」するまでの組織のアプローチ~
| 講演日 |
2025年7月24日(木) |
| 登壇者 |
住田 直樹 氏(QualiArts)
田中 広海 氏(QualiArts) |
昨今、ゲームに対する自動テストの導入が業界的に盛んになり、さまざまな活用事例やそれらを実現するライブラリやミドルウェアが登場するようになりました。
自動テストの言葉の響きはいいものの、実際は開発や保守のコストが高かったり、効果的な検証を実現できなかったり、期待していた成果になかなか繋がらないものです。
QualiArtsでも自動テストには多くのユースケースで検証を進めてきました。
そこで、本セッションでは、QualiArtsの自動テストの事例について、導入の経緯、工夫点から実績、問題点まで赤裸々にご紹介します。
そして、事例をもとにモバイルゲームに対して自動テストをどのように活用していくのか、ノウハウや観点をご紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「モバイルゲームで自動テストが効果を発揮するまで ~自動テストを「運用」するまでの組織のアプローチ~」スライド資料モバイルゲームの開発を支える基盤の歩み ~再現性のある開発ラインを量産する秘訣~
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
田村 和範 氏(QualiArts) |
QualiArtsではこれまでに多くのUnity製のモバイルゲームをリリースしてきました。
それらを安定して開発するために重要な役割を果たしてきたのが社内基盤ライブラリです。
社内基盤ライブラリは、Unityでのゲーム開発で共通して必要な機能を再利用可能な形で提供するものであり、QualiArtsでは数多くの基盤が開発されてきました。
基盤の存在により、プロジェクトごとにゼロから機能を開発しなければならない場面が減り、開発クオリティの再現性や開発効率の向上に寄与しています。
一方で、基盤の開発や活用には、基盤のクオリティ、浸透、属人化など、多くの課題が伴います。
それらの課題は一朝一夕で解決できるようなものではなく、会社の文化や価値観とも密接に関係してきます。
本セッションでは、QualiArtsではこれらの課題にどのように向き合い、効果的な基盤利用を達成しているのかを具体的に紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「モバイルゲームの開発を支える基盤の歩み ~再現性のある開発ラインを量産する秘訣~」スライド資料E2Eだけがテスト自動化じゃない! Unity製ゲームの開発者テスト チュートリアル
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
長谷川 孝二 氏(サイバーエージェント/ハブシステムズ) |
実機上でゲームプレイを行なうエンドツーエンド(E2E)テスト自動化の事例を見聞きする機会が増えてきました。
しかし、E2Eテストの自動化はゲームタイトル固有の工夫も必要でコストもかかるため、規模の大きいナンバリングタイトルでないと導入は難しいものです。
本セッションでは、旧来のテスト/デバッグ工程を「自動化する」アプローチではなく、開発の早い段階からユニットテストや統合テストによってバグの作り込みを防ぐ「開発者テスト」の導入方法や効果について、講演者が開発・公開しているオープンソースのUnity向けライブラリ/フレームワークの使いかたも交えて紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「E2Eだけがテスト自動化じゃない! Unity製ゲームの開発者テスト チュートリアル」フォローアップ記事LLMを活用したゲーム開発支援と、生成AIの利活用を進める組織的な取り組み
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
金井 大 氏(Cygames)
笠原 達也 氏(Cygames)
都築 圭太 氏(Cygames) |
本講演では、LLMを活用したゲーム開発支援機能の開発事例と、生成AIの導入と利用を推進するための組織的な取り組みの事例を紹介する。
急速に進化する生成AIに対応すべく、Cygamesでは全社横断的な活動を担う「GenerativeAI活用委員会」と、AIの専門部署である「AIテクノロジー」という組織を設立し、ゲーム開発において生成AIが「何ができ、何ができないか」を明確化する取り組みを進めており、LLMを活用した業務効率化で成果が出はじめている。
特にAIチャットサービス「Taurus」は、社内のナレッジベースやデータベースなどの様々な業務情報を用いた回答を実現し、開発と運用を通じて社内のAIリテラシーの向上や業務効率の改善に寄与している。
本講演では、これらの取り組みの中で発生した様々な課題と解決策、Microsoft Azure OpenAIのPTU環境やAWS Bedrockなどを用いたLLMベースの機能における開発事例を技術面にフォーカスして紹介する。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「LLMを活用したゲーム開発支援と、生成AIの利活用を進める組織的な取り組み」スライド資料「LLMを活用したゲーム開発支援と、生成AIの利活用を進める組織的な取り組み」フォローアップ記事現場を理解して実現!ゲーム開発を効率化するWebサービスの開発と、利用促進のための継続的な改善
| 講演日 |
2025年7月24日(木) |
| 登壇者 |
諸葛 泰鉉 氏(Cygames) |
本講演では、社内のゲーム開発効率化ツールを効果的に開発するためのプロセスや、全社的に利用してもらうための普及戦略について紹介します。
最初に少人数のチームで「シナリオ執筆支援ツール」「汎用的なオンラインストレージツール」「ローカライズ支援ツール」などの複数のツールを効果的に開発・運用するためのチーム構成、開発体制について説明します。 それに加え、「ローカライズ支援ツール」を例に7プロジェクトで利用されるまでの普及戦略を具体的に紹介します。
また、普段の業務ワークフローへの導入が難しいAIに関しても、「シナリオ執筆支援ツール」へAI監修機能を導入した事例を取り上げ、課題の洗い出しから導入までの流れを詳しく解説します。
これらの手法と事例を紹介することで、社内向けにゲーム開発効率化ツールの開発を行っている部署や、これからチームを立ち上げたいと考えている方々に非常に役立つ内容を共有します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「現場を理解して実現!ゲーム開発を効率化するWebサービスの開発と、利用促進のための継続的な改善」スライド資料「現場を理解して実現!ゲーム開発を効率化するWebサービスの開発と、利用促進のための継続的な改善」フォローアップ記事大規模言語モデルを活用したゲーム内会話パートのスクリプト作成支援への取り組み
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
立福 寛 氏(Cygames) |
本講演では、AIを活用したゲーム内会話パートのスクリプト作成支援機能の開発事例を紹介します。従来の機械学習による手法では、開発時に大量のデータを集めて学習させる必要があり、多大な時間と労力がかかっていました。しかし、GPT-4のような大規模言語モデルを利用することで、その手間を大幅に削減できるようになりました。本講演では、ゲームシナリオから、シーンに合わせたモーション、キャラクター画像、音声といった演出要素の設定をAIで行う機能の開発事例を紹介します。推論時の計算量を調整することで精度を大幅に向上させる手法についても説明します。また、過去のシナリオが存在しない新規キャラクターへの対応など、運営型のゲームで必要となる部分についても触れます。大量のデータと学習時間が不要な手法であるため、これからゲーム開発においてAI技術の導入を検討しているエンジニア、プロジェクトマネージャーに特に役立つ内容となっています。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「大規模言語モデルを活用したゲーム内会話パートのスクリプト作成支援への取り組み」スライド資料「大規模言語モデルを活用したゲーム内会話パートのスクリプト作成支援への取り組み」フォローアップ記事GDC2025頻出の海外ゲームデザイン用語を紹介!(CEDEC Lightning 2025)
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
知久 温 氏 |
CEDEC2025のCEDEC Lightningという企画で登壇した5分の講演です。
(ドクセルの資料概要欄より引用)
「GDC2025頻出の海外ゲームデザイン用語を紹介!(CEDEC Lightning 2025)」スライド資料社内インディー攻略法!VRゲームが中ヒットにいたるまでの道のり
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
渋谷 宣亮 氏(MyDearest) |
本セッションでは、ゲーム企業社内でのインディーゲーム開発を始め、経験の少ないスタッフが中心となってVRゲームを開発し、中ヒットを達成するまでのプロセスを詳しく解説します。小規模なリソースでの開発手法やVR市場への効果的なアプローチなど、具体的な事例を交えて共有します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「社内インディー攻略法!VRゲームが中ヒットにいたるまでの道のり」スライド資料『ウマ娘 プリティーダービー』における映像制作のさらなる高品質化へ!~ 豊富な素材出力と制作フローの改善を実現するツールについて~
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
嘉寺 尚也 氏(Cygames) |
『ウマ娘 プリティーダービー』では、ゲーム内やCMなどのメディア向けといった、ゲーム内外で数多くの映像が制作されています。
本コンテンツの映像制作では、ゲームの開発環境と素材を使い、Unityエディタ上で映像用の画面を構築し、UnityRecorderを用いて出力した画像をAfter Effectsでコンポジットして映像を作っていました。
しかしこの手法だと、プラットフォームやデバイスのスペックに応じた表現の幅に制約を受けてしまうという課題がありました。
この解決手段として、映像制作用の多様なコンポジット素材を出力するツールを開発しました。
ツールの導入により、ゲーム内だけではなく、CMなどのメディア向けの映像品質の向上や、制作フローの改善を実現できました。
本講演では、ツールの開発事例を通して、ゲーム素材を利用した映像制作での高品質化や制作フローの改善に関するノウハウを紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「『ウマ娘 プリティーダービー』における映像制作のさらなる高品質化へ! ~豊富な素材出力と制作フローの改善を実現するツールについて~」スライド資料Unreal Engine 5.6 最新アップデート - オープンワールドで60FPSを達成するための最適化
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
澤田 祐太朗 氏(Epic Games Japan)
鈴木 孝司 氏(Epic Games Japan) |
2025年6月にリリースしたUnreal Engine 5(UE5)の最新バージョン、UE5.6では、高精細かつ大規模なオープンワールドを60FPSで動作させるための様々な最適化が行われています。
このセッションでは、UE5.6で行われたアップデートを中心に、LumenやNaniteでリッチなグラフィックを実現しつつ60FPSを達成するための設定やテクニックを紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「Unreal Engine 5.6 最新アップデート - オープンワールドで60FPSを達成するための最適化」スライド資料Unreal Insightsを使用したパフォーマンス分析と最適化マスタリー
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
鍬農 健二郎 氏(Epic Games Japan) |
Unreal Insightsは、プロジェクトのパフォーマンスを分析し問題を診断するための便利なツールで、Unreal Engineで作成したゲームを最適化するのに最適なツールです。Insightsを使えば、CPU/GPUパフォーマンスのボトルネック、メモリリーク、アセットのロード時間の長さなどを調査し、ゲームをリリースする前にこれらの問題に対処することができます。このセッションでは、様々なタイトルのプロファイリング経験に基づき、パフォーマンスの問題とは何か説明し、そして各ボトルネックケース別での分析方法を解説します。また、ご自身のプロジェクトのパフォーマンス分析に活用できる、Unreal Insightsの新機能もご紹介します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「Unreal Insightsを使用したパフォーマンス分析と最適化マスタリー」スライド資料ゲームにおけるリアルタイム通信へのQUIC導入事例の紹介
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
竹原 涼 氏(セガ)
松崎 大 氏(セガ)
藤村 隆史 氏(セガ) |
2021年5月に標準化されたトランスポートプロトコルであるQUICは、Web業界をはじめ、既に様々な業界やプロダクトで採用され、ノウハウが蓄積されています。
しかし、ゲーム業界ではまだQUICに関する事例の共有が多くありません。
そこで、本セッションでは、まず「ゲームならでは」の視点にフォーカスしたQUICの機能やユースケースを共有します。
その後、セガのタイトルでのQUICの活用事例を紹介します。
【Sonic Rumbleの事例】
Sonic Rumbleは、32人がマルチプレイで対戦し、3つのステージを勝ち抜いて最後の1人として生き残ることを目指す、Unity製のパーティーロワイヤルゲームです。
このSonic Rumbleのリアルタイム通信にQUICを採用した事例を紹介し、実測データから得られたQUIC使用時のポイントを共有します。
【社内製リアルタイムネットワークライブラリ”SPHINGO”およびその採用タイトルの事例】
“SPHINGO”は、数人から数十人規模のリアルタイム通信対戦を行うためのネットワークライブラリで、既に20年近い歴史があり、セガ社内の複数のタイトルで採用されています。
今回は、この”SPHINGO”のプロトコルにQUICを追加した事例を紹介します。
各種プラットフォームにおいてConnection-Migrationを実装する際に苦労したポイントや、既存のSCTP/UDPベースの実装と比較した際の性能やリソースに関する実測データについても共有します。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「ゲームにおけるリアルタイム通信へのQUIC導入事例の紹介」スライド資料国内ゲーム実況ライブ配信統計データの見方
| 講演日 |
2025年7月24日(木) |
| 登壇者 |
中村 鮎葉 氏(配信技研) |
国内ではゲーム実況ライブ配信が注目されています。人気チャンネル・タイトルは今や多くの人が知るところです。しかし、その見方は感覚に頼っている企業・分析も多いです。
本セッションでは、配信技研が今まで出してきたランキング・その背景にある蓄積統計を総合して説明します。例えば国内ゲーム実況ライブ配信市場規模はどういった勢いで拡大したのか、どのような物理量でそれが説明できるのか、どういったチャンネルやタイトルが人気があるのかをご覧に入れます。
最終的に、ゲームパブリッシャーの方々がライブ配信の流行を追いかける際にどういった見方をすれば良いのか、ひいては在野のファンの方々もどのように楽しめば良いのかといった視点が身につきます。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「国内ゲーム実況ライブ配信統計データの見方」スライド資料掲載ページ『Shadowverse: Worlds Beyond』二度目のDCG開発でゲームをリデザインする~遊びやすさと競技性の両立~
| 講演日 |
2025年7月23日(水) |
| 登壇者 |
宮下 尚之 氏(Cygames) |
9周年を迎えたDCG(デジタルカードゲーム)『Shadowverse』と、今年6月リリースの後継作
『Shadowverse: Worlds Beyond』どちらも開発したリードゲームデザイナーだからこそ得られた知見の一端を紹介します。
・新作DCGとしての遊びやすさと、eスポーツタイトルとしての競技性を両立させる手法
・カードゲームジャンル特有のゲームデザイン上の課題を解決する手法
・ゲームデザインとテストプレイの工程を効率化する手法
などを紹介します。
はじめに『Shadowverse』についてざっくり説明するので、詳しくない方でも大丈夫です。カードゲームやゲームデザインに興味のある方なら、より楽しめます。また、過去作を参考にしてゲーム開発をするプランナーの方にとってヒントとなるセッションです。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「『Shadowverse: Worlds Beyond』二度目のDCG開発でゲームをリデザインする~遊びやすさと競技性の両立~」スライド資料アーケードカードゲーム制作における生成AIを用いたQA自動化~AI活用による効率的なチェックプロセスの実現~
| 講演日 |
2025年7月24日(木) |
| 登壇者 |
山中 亮 氏(テックフラッグ)
岡本 吉弘 氏(バンダイナムコ エクスペリエンス) |
ChatGPTの登場以来、生成AIは加速度的に進化をし続けています。
特に昨今ではマルチモーダル化も進み、目・耳・口にあたる機能の発展も進んできました。
昨年のCEDECではアーケードゲームにおける生成AIを活かしたQA自動化への取り組みを登壇させていただきました。
今回もバンダイナムコエクスペリエンス様と協力して生成AIを用いた実カードを含むカードゲームのQA自動化を同社のゲームを題材にして行いました。
カードゲーム制作において、どのようなプロセスとアプローチで自動化を行うと効率的なのか事例を含めて詳細にお話しします。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「アーケードカードゲーム制作における生成AIを用いたQA自動化~AI活用による効率的なチェックプロセスの実現~」スライド資料大規模イベントを支える ABEMA のアーキテクチャ
| 講演日 |
2025年7月22日(火) |
| 登壇者 |
永岡 克利 氏(AbemaTV)
辻 純平 氏(AbemaTV) |
本セッションでは、大規模イベントの配信を支えるために私たちが実施したクラウドアーキテクチャの強化施策と、更なる大規模イベントに向けた改善や社会インフラとしての進化について共有します。
従来の技術的負債を解消しながら、大規模トラフィック時のキャパシティ管理やオートスケール戦略、サービスメッシュ導入による通信制御・可観測性向上、モニタリングシステムの最適化など多角的なアプローチを実施しました。
過去のイベントを通じて得た学びを活かし、負荷試験やログ分析からクリティカルパスを抽出するとともに、障害時も小さく壊れるための耐障害設計を徹底。さらに、ピーキーなトラフィックや DDoS などのセキュリティリスクにも多層防御で対応し、社会インフラとしての信頼性をより強固にしました。
これらの取り組みは単なるイベント対応にとどまらず、次世代の大規模配信プラットフォームや社会インフラとしての進化に寄与するものです。本セッションを通じて、大規模ライブ配信の裏側でどのようなクラウドアーキテクチャが進化してきたのかを知り、今後のシステム設計・運用に役立つ具体的なノウハウをお伝えします。
(CEDEC2025の講演紹介ページより引用)
「大規模イベントを支える ABEMA のアーキテクチャ」スライド資料「CEDEC2025」公式サイトCEDiL