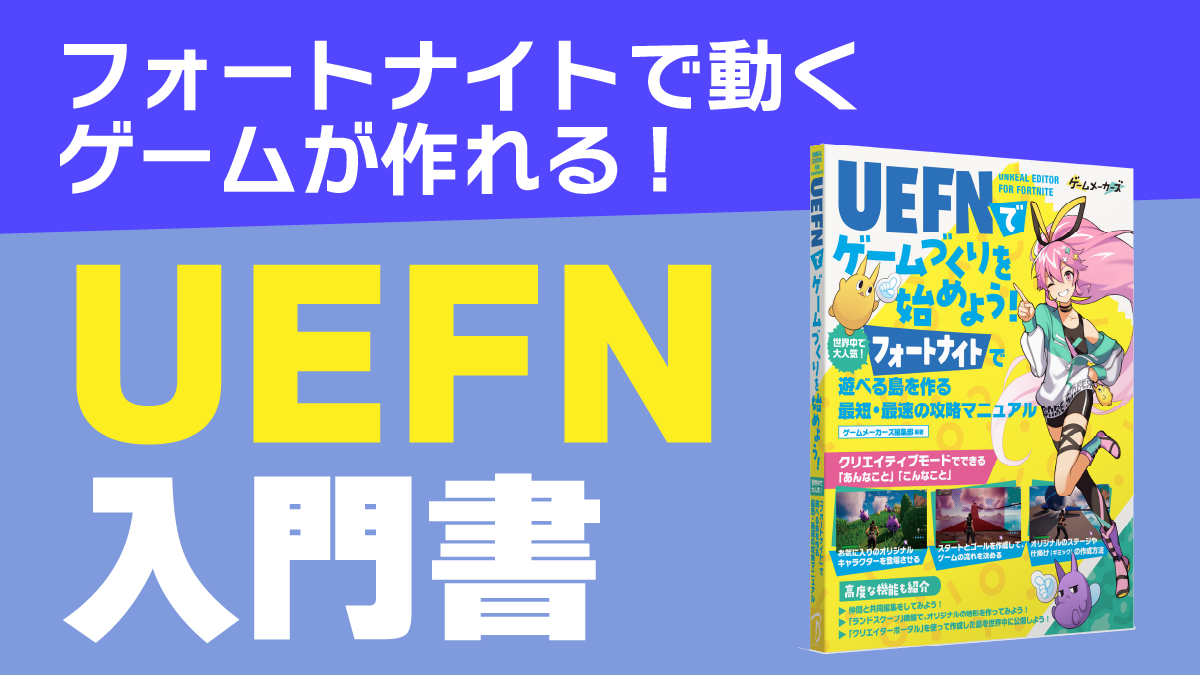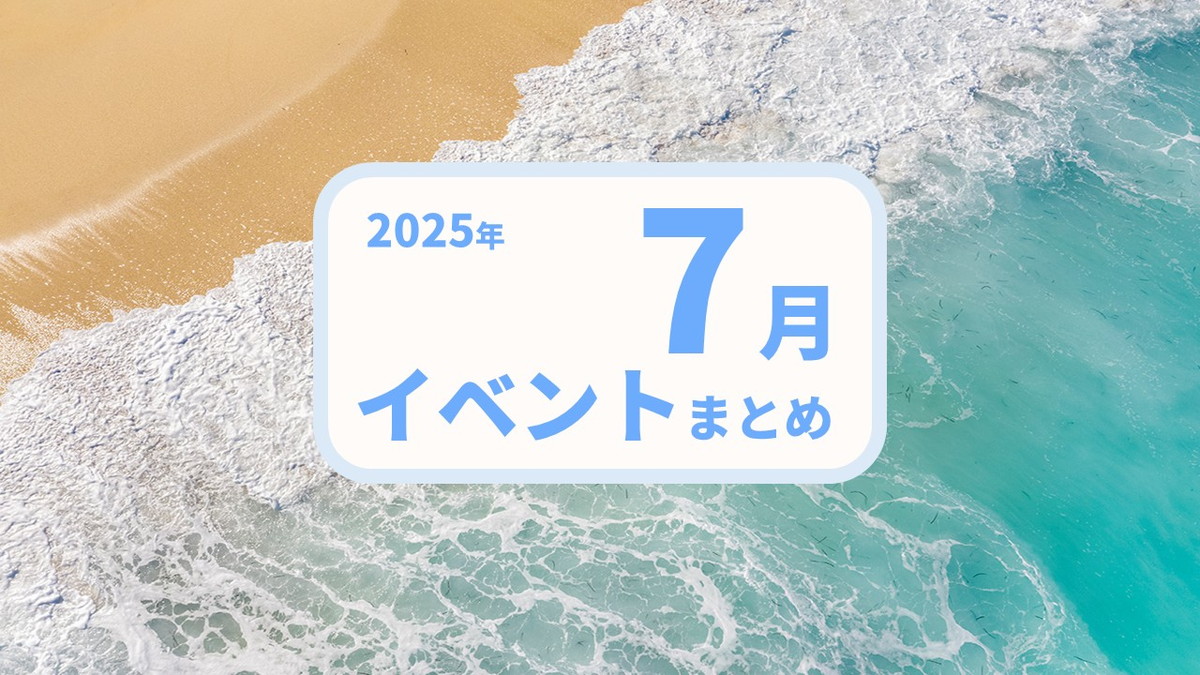ジャンプの高さやダッシュの速さ、キャラクター固有のアクションとエネミーデザイン、それらを活かすステージ設計。さまざまな要素が絡み合うアクションゲーム制作の設計手順と考え方について、世界累計100万本以上を売り上げたアクションRPG『天穂のサクナヒメ』制作者である えーでるわいす なる氏にお話を伺いました。前編では、サクナヒメの前身となるアクションゲーム『花咲か妖精フリージア』の設計思想について解説します。
ジャンプの高さやダッシュの速さ、キャラクター固有のアクションとエネミーデザイン、それらを活かすステージ設計。さまざまな要素が絡み合うアクションゲーム制作の設計手順と考え方について、世界累計100万本以上を売り上げたアクションRPG『天穂のサクナヒメ』制作者である えーでるわいす なる氏にお話を伺いました。前編では、サクナヒメの前身となるアクションゲーム『花咲か妖精フリージア』の設計思想について解説します。
INTERVIEW & TEXT / 神山 大輝
INTERVIEW / 佐々木 瞬
なる氏
同人ゲームサークルえーでるわいす代表で、主にゲームデザイン、プログラム、エフェクト、効果音を担当。代表作は「天穂のサクナヒメ」「アスタブリード」
――まずは自己紹介をお願いします。
えーでるわいす代表のなると申します。えーでるわいすは2005年から活動するゲーム制作サークルで、これまでに『天穂のサクナヒメ』、『アスタブリード』、『花咲か妖精フリージア』などをリリースしています。私は主にプログラムとゲームデザイン、エフェクト制作や効果音制作などを行っています。もともとはゲーム会社に在籍していましたが、東日本大震災をきっかけに退職して、今は専業でゲームを作っています。
――会社員時代は、どういったゲームに関わっていたのでしょうか。
プログラマーとして新卒入社して、最初はエフェクトなどを担当していました。制作していたのは3D格闘ゲームが中心で、3作品ほどメインプログラマーとして参加しました。大きなタイトルのリリースも経験しましたし、会社での仕事にも満足感はありましたが、ずっと続けていた同人サークルのほうが楽しくなってしまって。そこから今のスタイルに落ち着きました。
――新卒でゲーム会社に入られたということですが、最初にゲームづくりを意識したのはいつ頃だったのでしょうか。
私はファミコンやスーファミ世代で、ゲームで遊ぶことが当たり前の時代に生まれたので、興味自体は自然と持っていましたね。以前に同人ゲーム仲間と話したときに面白かったのは、みんな「小学校の頃に架空のゲームをノートに描いて遊んでいた」という共通項があったことです。思い返せば、私自身もサイコロを転がしてダメージを決めていく『ウィザードリィ』風のゲームを想像で書いて遊んでいました。
あとはノートの端に爆発エフェクトを模したパラパラ漫画を描いたりとか、小学校の間はずっとそんな感じで過ごしていましたね。この興味が本格的なゲームづくりに繋がったのは中高生の頃で、きっかけは『RPGツクール3』でした。
――PlayStation版のツクールですね。2までがスーパーファミコンでしたので、3から一気に容量が増えたことを覚えています。
そうですね。ゲームを完成させてコンテストにも応募しましたが、残念ながら受賞はできなくて。それが高校生くらいだと思いますが、その後もゲームづくりを続けようと思い、ECCコンピュータ専門学校に入学しました。学生時代はちょっとしたアクションパートで敵を倒すようなゲームを作っていました。
――この頃からアクションゲームが多いんですね。『めるへんマッチョTRUTH』は、コンボシステムとスクロールステージということで、今の作品に繋がる要素も感じます。
スクロールステージのアクションRPGへの想いは『コナミワイワイワールド』『ワンダーボーイ モンスターランド』辺りが原点だと思います。コンボアクションについては『ストリートファイター2』世代ですから、格闘ゲームには自然と触れていました。『THE KING OF FIGHTERS ’96』や『鉄拳3』をよく遊んだ記憶があります。ジャンルに特別思い入れがあるわけではないのですが、のちに入った会社で格闘ゲームばかり作ることになるとは思いませんでした。
――その後は最初の話に戻り、メインプログラマーとして3D格闘ゲームに携わってきたと。これも非常にやりがいのある仕事だと思いますが、「同人ゲームの方が楽しくなった」というのは具体的にどういうことでしょうか。
フリージアの開発後期から、サクナヒメでもグラフィックス全般とシナリオを担当してくれたこいちと一緒にゲームを作るようになったのですが、その時の開発の流れがすごく良かったんです。向こうが上げてくるグラフィックがこちらの予想を大きく上回っていて、それならゲームの仕様もこう変えられるな、と思って提案して、それに対してもっと良いデザインを返してくれて。お互いに自発的に作ってゲームがどんどん良くなっていくという流れが、「いま、自分はゲームを作っている!」という感覚に繋がっていたんです。
個人制作のいいところは、考えたものをその場ですぐに作れること。試行錯誤しながら、自分の裁量で進めていけるのが大きなメリットです。きっとこれは会社でもできることだと思いますが、プロジェクト規模や社風、チームの空気といった運に近いものも絡んできますので、やはり自分は今のようにサークルで作るのが合っていると感じています。
――なるさんのルーツをうかがったところで、ここからはアクションゲームを作る過程について、『フリージア』を題材にお伺いします。そもそも、キャラクターのアクションを設計するときは、どのような順序で制作を進めるのでしょうか。
まず最初に決めなくてはいけないのが「ジャンプの高さ」と「移動速度」です。特にジャンプの高さは重要ですね。これが決まらないとステージの設計ができないので、この2点を重点的に詰めていきます。アクションというのは2種類あると思っていて、例えばマリオやメトロイドはジャンプアクションです。ジャンプでステージを進んでいくことを目的とし、ジャンプの高さで行けないところを作るようなステージ設計をします。
一方、フリージアやサクナヒメはバトルアクションです。この2つのゲームは、ジャンプでステージを進んでいくことが主体ではなく、バトルが主体なんです。
――移動速度についてはいかがでしょうか。
移動速度は「1フレームごとに8cm」などときっちり速度を指定しています。移動速度とモーションが合っていないと地面を滑るような動きになってしまうので、モーションを発注する前に必ず正確な数値を出すようにしています。ここがおそろかになると動きが気持ち悪くなってしまうので、きちんと最初に決めておくべきところですね。
――ジャンプの高さや移動速度について、設定の基準はあるのでしょうか。
実際にキャラクターを動かしながら調整をしていきますが、結局はカンだと思います。ただ、ジャンプの高さはカメラで印象が変わってしまうので、ジャンプの前にカメラを決める必要はありますね。作り始める段階で、自分の頭の中には動いているゲームがあるので、それに合わせるような感覚です。フリージアやサクナヒメの場合は空中コンボを利用すればどこまでも行けてしまうので、移動制限というよりはバトルの気持ちよさを優先した調整になっています。
――ご自身のイメージに合わせて設定していくということですね。逆を返せば、最初からきっちりイメージを膨らませておくことが重要だとも感じました。キャラクターの基礎となる移動の部分が固まったら、次はどこを作るのでしょうか。
次は攻撃の処理を順番に作っていきました。ちなみに、フリージアは内製エンジンで開発されているんです。この当時は一般流通するゲームエンジンがなかったので、自分ですべての仕組みを作る必要がありました。
――その「攻撃」について、フリージアはコンボの感覚や敵の吹っ飛びなどを含めてアクションの操作性がすごく良いと感じています。どのような設計思想なのか、詳しくお聞かせください。
まずはフリージアの移動や攻撃の資料として、残っている中で一番古い動画をお見せします。この時点で1年ほどは経っているのかなと思います。基本的な移動と攻撃は、この時点で実装されていますね。
――既にコンボなども実現できていますね。一言でアクションゲームと言っても方向性はさまざまだと思いますが、フリージアはバトルアクションとしてどういったゲームを目指していたのでしょうか?一見すると、キャラクターの動きは格闘ゲームのそれに近いようにも感じます。
格闘ゲームはとにかくキャラクターを気持ちよく動かすジャンルだと思っていて、そのノウハウを格闘ゲーム以外にも使えるのではないかという気持ちはずっと持っていました。キャラクターを動かすこと自体はほぼ全てのゲームジャンルに共通するので、そこに格闘ゲームの持つ「気持ちよさ」のノウハウを入れ込もうと考えたんです。
――敵の浮きに対して追撃を入れてコンボを繋いでいくというのも格闘ゲーム的だと感じました。なにか影響を受けているタイトルはありますか?
この辺りもカンで作っているところはありますが、元を辿ると『MELTY BLOOD』の影響はあるかも知れません。敵の浮き具合や動き方のタメツメも、同作品に近しい考え方です。でもやっぱり、何度も自分で動かして一番気持ちが良いと思えるラインまで作り込むのが大切ですね。フリージアでは、触っていて気持ちのいいアクションというところをずっと追求していました。
――アクションの「気持ちよさ」は言語化できますか?汎用的な言葉ではなく、なるさんご自身の見解をお聞きできたらと思うのですが。
7割くらいはモーションの気持ちよさだと思っています。残りの3割については、プログラム、つまり制御の部分と、効果音やVFXなどの要素になります。フリージアのアニメーションは格闘ゲーム制作経験者が担当していて、「袈裟斬り、発生13フレームでお願いします」と依頼すると、それだけで良い感じのものを作ってくれます(技の持続は基本的に3F固定)。プログラムについては、ボタンをどこで受け付けるか、そして座標の移動値をどうするかなど、まさに制御の部分になりますね。
――モーションの気持ちよさと、そのモーションを受けた敵の挙動などが組み合わさることで、気持ちのいい動きに繋がっていると。そして、やっぱり”ピンと来る”まで試行錯誤するのが大事なんですね。ちなみに、発生フレームなどもなるさんが考えているのでしょうか。
そうです。発生フレームは純粋に遊びやすいかどうかで決めています。敵のモーションはプレイヤーが反応できるかどうかが判断基準です。簡単なフレームテストの機能も用意しています。敵の話でいくと、ちゃんと攻略可能かどうかの観点が出てくるので、プレイヤーの動きを作っていく作業とは領域がまったく変わってきますね。
――もうひとつ、技のキャンセルについてもお聞かせください。連打でコンボが繋がったり、特定の攻撃をジャンプでキャンセルしたりと、ここも格闘ゲームのノウハウを感じる部分ですが、どのように考えて、いつ実装していますか?
モーションをもらって実装するときに最低限は付けています。通常攻撃と必殺技などでカテゴリがあって、ヒット時においては下位のものから上位のものにキャンセルが掛かります。気を付けているのは、アニメーションの「戻り」に対して必ずキャンセルが掛かるようにすること。剣を振るアニメーションであれば、振り切ったあとに移動など通常動作のボタン入力を受け付けるというかたちにしています。
RPGでもなんでもそうだと思うのですが、攻撃をするまでの演出は長くても見ていられますが、攻撃が終わって自分の立ち位置に戻るまでの時間は結構ストレスなんです。
――先ほど少し敵の話題が出ましたが、基本的には雑魚敵とボス敵で分けて考えているのでしょうか?
実はここにはシューティングの考え方が入っていまして、自分はいつも小型、中型、大型の3段階で考えています。小型はバラバラ出てきてバンバン倒すもの、中型はプレイヤーの攻撃に少し耐えたりしっかり攻撃をしてくるもの、大型は節目で出てくる手強い敵というイメージです。この上に、中ボスと大ボスがいます。
――なるほど!シューティングゲーム的と言われれば、そう思えてきました。シューティングではチュートリアルも兼ねて、序盤には一発で倒せるような敵が大量に出現しますね。
フリージアの場合はリソースがなかったので3段階だけですが、本当は小型や中型の中にもいくつかタイプをたくさん作りたかったんです。モデルがなく、エフェクトだけで作った敵もいたくらいです。こうした思想の一部は、サクナヒメの敵にも活かされています。
――リソースという面も大きいかも知れませんが、3種類だけで遊びの幅は十分に用意できるのでしょうか。
私はむしろ敵の種類は絞りたい方なんです。個人的に『デビルメイクライ』シリーズがすごく好きなんですが、同シリーズは敵の種類自体は多くありませんよね?ゲーム性がしっかり練られていれば、むしろ敵の種類はむやみに増やさず、役割が明確な敵だけ作ればいいという思想です。あとは、バトルが中心といってもアクションゲームではあるので、ある程度敵のモーションを覚えていかないと攻略できないという側面もあります。
「敵の種類」について、シューティングゲームを例として挙げるなど、なる氏はシューティングゲームへの造詣も深い。『アスタブリード』はアクションとシューティングの融合系として非常に完成度の高いタイトルになっているので、是非プレイして欲しい
――ありがとうございます。フリージアの時点で、アクションの手触り感や敵の考え方の基礎は固まっていたのですね。これらを踏まえて、続いてはいよいよ『サクナヒメ』のアクションについて深堀りしていきたいと思います。
『天穂のサクナヒメ』公式サイト『アスタブリード』公式サイトゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。
ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。

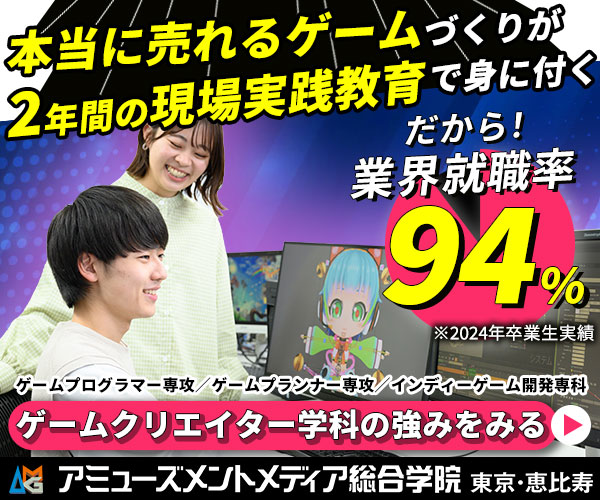

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCE ’25で行われた講演レポートをまとめました。
GDC 2025で行われた講演レポートをまとめました。
UNREAL FEST 2024で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。
東京ゲームショウ2024で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。
CEDEC2024で行われた講演レポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブル2024で行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。
CEDEC2023で行われた講演レポートをまとめました。
東京ゲームショウ2023で展示された作品のプレイレポートやインタビューをまとめました。
UNREAL FEST 2023で行われた講演レポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドをまとめました。
UNREAL FEST 2022で行われた講演レポートやインタビューをまとめました。
CEDEC2022で行われた講演レポートをまとめました。