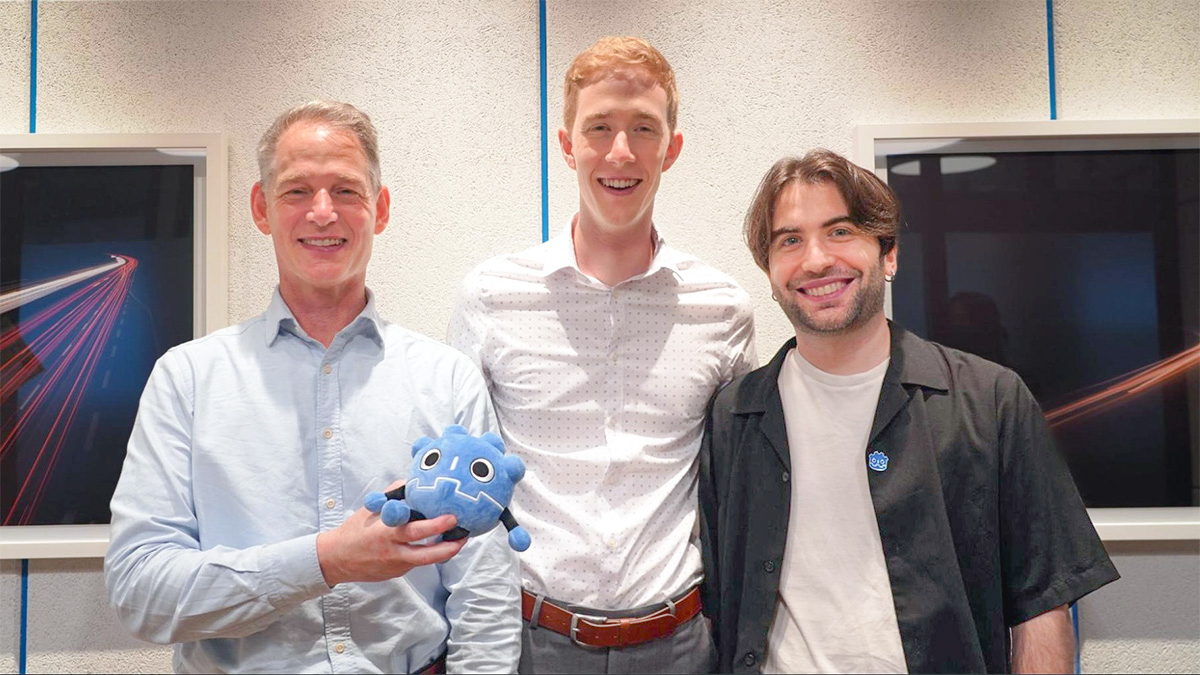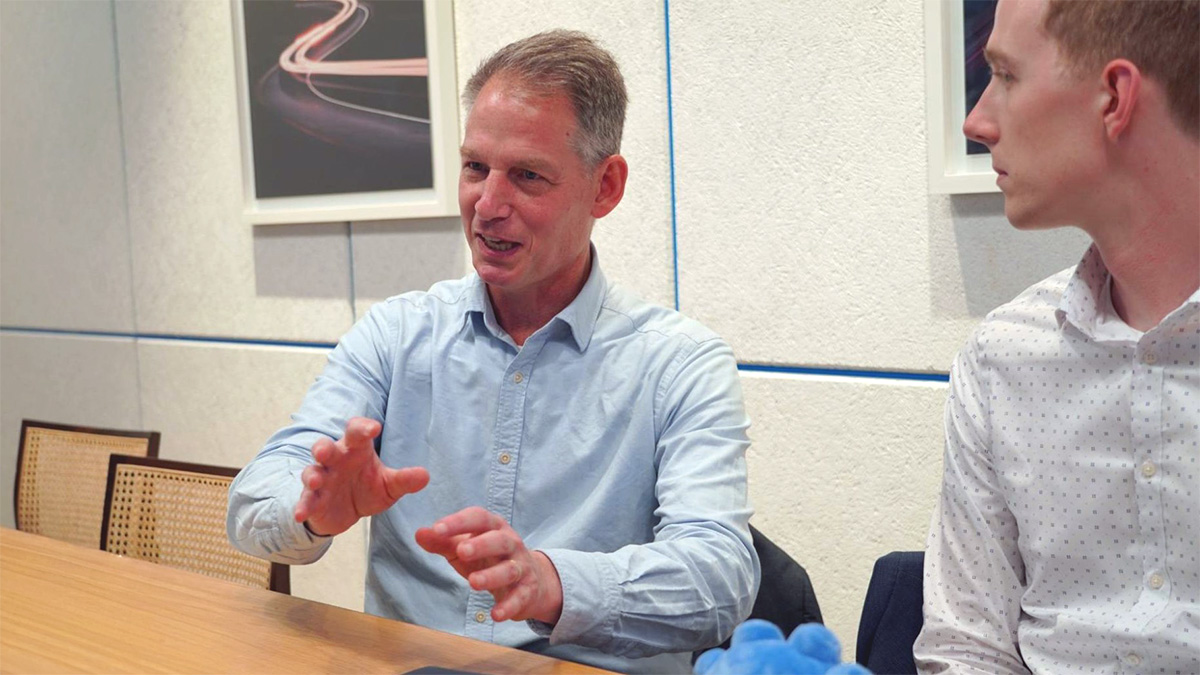Darin Bifani
W4 Games APACパートナーズ&ビジネスデベロップメントリード / コーポレートアフェアーズ責任者 / 法務顧問
Clay John
Godot Foundation 取締役会員
W4 Games テクニカルディレクター
Emilio Coppola
Godot Foundation エグゼクティブディレクター
「ユーザーを大事に」 コミュニティと共に成長していくGodot
――自己紹介をお願いします。
Emilio:Godot Foundationのエグゼクティブディレクター、Emilio Coppolaです。新しい人材の確保やコミュニティの意見に基づくプロジェクトの方針決定などがミッションです。
Clay:W4 GamesのClay Johnです。テクニカルディレクターとして、Godot製ゲームのコンソール移植用ミドルウェア「W4 Consoles」の制作と販売に携わっています。社内で進行しているほかの技術プロジェクトについても、必要に応じて協力しています。
また、Godot Foundationにも所属しており、取締役会のひとりとして方針や資金の使い方を話し合って決めています。レンダリングチームのリーダーでもあるので、システムの改善について各チームのリーダーと打ち合わせをすることもあります。
Darin:Darin Bifaniです。W4 Gamesでは、コーポレートアフェアーズの責任者として法務などに携わっています。現在はアジア参入への活動も行うようになりました。
写真左からDarin Bifani氏、Clay John氏、Emilio Coppola氏
月1~2作品のGodot製ゲームが売上100万ドル超を記録。ユーザー数も急増中
――Godot Foundationから見た、最近のGodotユーザーの変化を教えてください。
Emilio:ユーザー数は大きく増加しています。これまでは個人開発者が中心でしたが、最近は大規模チームやスタジオでの利用が増えました。大きなチームが目指すクオリティの高さに対応できるよう、エンジンとしてもさまざまな改良が必要になっています。
Clay:以前はGodotで作られたゲームが100万ドル以上売れるのは年に1本程度でしたが、今では月に1〜2本のペースです。
――Godotの拡大戦略はどのように考えていますか?例えば、ほかのエンジンでは大型タイトルとコラボレーションし、大規模開発での採用を拡大させる動きが見られます。
Emilio:Godot Foundationとしては、ユーザー拡大のために特別な活動を始めることは考えていません。私たちは「現在のユーザーを大切にする」ことを最優先にしています。
Godotはオープンソースで、個人や法人の意思決定に振り回されないのが大きな魅力です。オープンソースであることにひかれた人が新たなユーザーになってくれると思いますし、この魅力を損なうような動きをするつもりはありません。
Clay:ユーザーからの指摘や要望がコントリビュートという形で反映される点もオープンソースであるGodotの特徴です。コントリビューターもGodotユーザーだからこそ、ユーザーの気持ちを理解したものが生み出されていくんです。
すでに2,000人以上のコントリビューターが参加していますが、そのうちGodot Foundationに所属しているのは10人だけです。この数字に現れているように、外からの意見も幅広く取り入れてエンジンを改善していける点がGodotの長所だと考えています。
――コミュニティではどんな話し合いが行われているのですか?
Clay:最も注目されているのはプラグイン機能の充実です。Unityのアセットストアのような環境を構築中で、現在ベータテスト段階です。
Emilio:私たちは「将来必要になるかも」ではなく「今、何が最も必要か」を重視しています。今解決すべき課題と優先順位を、コミュニティからのフィードバックを基に決めています。
――コントリビューションに参加したい人はどこからアプローチすればよいのでしょうか?
Emilio:GodotのWebサイトにある「How to contribute」を読むとアプローチの方法が分かります。プログラミングができなくても、Webサイトの翻訳やチュートリアル作成など、さまざまな貢献方法があります。
Darin:Godotは日本ではそこまで普及していませんが、エンジンとしては着々と成長しています。コントリビューションに日本の開発者が持つ才能や技術が入ってくれるのは、Godotの成長、未来のために本当に重要だと思います。
Clay:今のGodotがあるのはコミュニティの皆さんの支援があってのものです。情熱あるコミュニティをさらに拡大していきたいですね。
「認知度はまだ低い」日本市場における課題
――W4 Gamesとしては、現在のアジア市場をどう見ていますか。
Darin:アジアのマーケットには大きなポテンシャルがありますが、Godotの認知度はまだ低いのが現状です。何が求められているかリサーチを行い、その結果から戦略を立てていく予定です。
――日本でGodotをもっと受け入れてもらうためには何が必要でしょうか。
Darin:教育コンテンツの充実が重要ですね。認知度だけでなく「Godotをどう使えばよいのか」がわからないハードルも存在している印象です。
今後は、技術資料やチュートリアル動画の日本語化、日本語での質問ができる環境の整備を進めたいと考えています。
W4 Gamesの役割とW4 Consoleの特徴
――続いて、W4 Gamesはどのような会社なのか教えてください。
Clay:W4 Gamesは、もともとGodotがカバーできなかった「コンソール移植」「大きなチームへのサポート」という2つの需要に対応するために生まれた会社です。長年誰もやらなかったので「じゃあ私たちが」と立ち上げました。
Darin:Godotはゲーム開発のためのエンジンですが、ゲーム開発者はゲームを作るだけでなくマネタイズも大切です。なので、ゲームのマネタイズのためのサービスと製品を提供することが、Godotにとっても重要なことなんです。
――W4 Gamesが展開するサービスについて教えてください。
Clay:Godot向けのコンソール移植ミドルウェア「W4 Console」を展開しています。PCやモバイルと同じ方法でコンソールへとGodotのプロジェクトをエクスポートできるのが特徴です。
他社の移植サービスは多くの場合、移植とパブリッシングがセットです。W4 Consoleならソースコードを他社に渡す必要もありませんし、パブリッシングの手段は自分で選択できます。
Darin:価格の透明性とコードをオープンにしている点も重要なメリットです。移植サービスによってはどんな処理をしているか分からないブラックボックスになっていることがありますが、私たちは違います。
――W4 Consoleの活用事例についても教えてください。
Clay:Nintendo Switch™とXbox Series X|S向けの移植機能が2024年10月リリースで、PlayStation®5への対応が今年の4月ですから、まだリリースされていないタイトルが多く、事例として話せるものは少ないです。ただ、開発中のタイトルは数多くあります。
ちなみに、Nintendo Switch 2への対応については現在作業中です。
――W4 GamesのプロダクトやW4 Consoleに興味がある開発者はどうコンタクトすればよいでしょうか。
Clay:弊社のWebサイトから連絡してください。プラットフォームの認定開発者であれば、サインアップしてすぐにW4 Consoleを購入できます。
まだ契約しておらず「単純に質問したい」「技術の検証がしたい」というケースや、技術的な情報を知りたい場合でも、専用のお問い合わせフォームからご連絡いただければ対応します。
別エンジンからの移行は可能?ハードルやサポート体制
――すでにほかのエンジンで開発を始めてしまっているケースもあると思います。Godotへの移行に対するサポートはどのように考えていますか?
Emilio:移行は簡単な道のりではありませんが、以前よりも移行しやすくなっていると感じます。
WwiseやFMODのようなミドルウェアも徐々にGodotへの対応が進んでいるので、別のツールに乗り換える必要もありません。
――ほかのエンジンからGodotに移行する際の注意点はありますか?
Emilio:一番の問題は「前のエンジンと同じやり方でやろうとする」ことですね。それぞれのエンジンにおいて最適な開発手法は異なるので、Godotの考え方に沿って開発することが重要です。
Clay:特にUnityからの移行でGodotをC#で扱う場合は、パフォーマンスの面で注意が必要です。UnityはC#をゲーム開発用に15年かけて最適化していますが、私たちは標準的な.NETを使っています。そのため「GDScriptを使った方が高速」とおすすめすることも多いです。
――移行にチャレンジしたい場合、サポートを受けられる場所はありますか?
Clay:コミュニティの皆さんに相談してみるのもよいでしょう。また、W4 Gameやエコシステム内のほかのサービスプロバイダーに相談していただければサポートが可能です。
Darin:W4 Gamesでは、それぞれの開発者が持つニーズに応じた移行のロードマップを作成することで、移行をサポートしたいと思っています。
新規タイトル開発だけでなく、既存タイトルをコンソールに移植するのと同じタイミングでエンジンをGodotに移行したい場合も、W4 Gamesに相談してください。
コミュニティ、技術、市場拡大などの展望
――それでは最後に、Godotコミュニティやエンジンの展望を教えてください。
Emilio:Godotユーザーの急増により、コミュニティの規模が非常に大きくなりました。我々は小さな組織なのでコミュニティ規模拡大への対応が難しく、これまでユーザーの意見に対応できませんでした。これからはアセットストアなどの機能充実や、イベントの開催を増やしていきたいです。
より多くの寄付が集まればチームを拡大し、コミュニティのニーズにより早く応えられます。毎年開催しているイベント「GodotCon」をアジアでも開催し、コミュニティをひとつにまとめたいですね。
Clay:エンジンの機能としては、レンダリングの品質向上と効率化が目標です。将来的には、ユーザーがより自由にカスタマイズできる高度な機能の提供を目指しています。完全にカスタマイズできれば常に細かな要望に対応する必要もなくなるため、チームにとっても良いことだと思っています。
Darin:市場規模やコンテンツを生み出す力という点で、特に日本には大きな可能性を感じます。私自身、日本に住んでいた経験もあり、この市場への期待は大きいです。リサーチして戦略を立て、学習資料を作っていくのが今後の活動ですね。日本でのGodotユーザーが増え、コミュニティがより盛り上がる日を楽しみにしています。
Godotの中心人物とも言える顔ぶれに直接話を聞く貴重な機会となった今回のインタビュー。
日本のGodotコミュニティを代表するトカゲ氏を交えてGodotの魅力やポイントを語りあった座談会のレポート記事も近日公開予定です!
Godot Foundation 公式サイトW4 Games 公式サイト
大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。
ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。