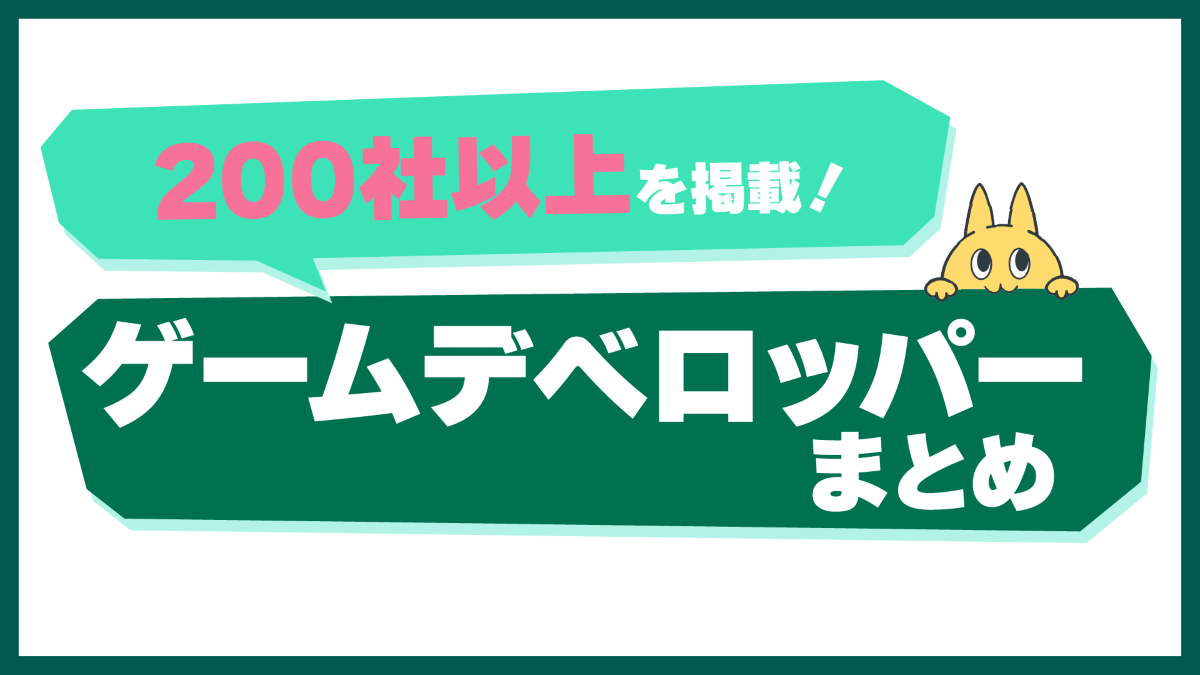2025年6月4日(水)、ゲームのプロデュースとマーケティングに特化したビジネスイベントである「GAME FUTURE SUMMIT 2025」が東京・渋谷で開催されました。
本稿では、イベント内で行われた講演「シナリオとキャラクターでユーザーを惹きつける方法 ~ADVにおける物語演出の魔力~」をレポートします。
2025年6月4日(水)、ゲームのプロデュースとマーケティングに特化したビジネスイベントである「GAME FUTURE SUMMIT 2025」が東京・渋谷で開催されました。
本稿では、イベント内で行われた講演「シナリオとキャラクターでユーザーを惹きつける方法 ~ADVにおける物語演出の魔力~」をレポートします。
TEXT / tyap
EDIT / 藤縄 優佑
本講演の登壇者は、ゲームジャーナリスト&アドベンチャーゲーム歴史研究家の福山 幸司氏がモデレーターを務め、ストーリーテリングの代表取締役 イシイ ジロウ氏、G2 Studios 取締役 佐藤 允紀氏、トゥーキョーゲームスの代表取締役 小高 和剛氏の4名。
あらかじめ用意されたテーマごとに登壇者同士で意見交換する形式が採られており、「冒頭から世界にどのように引き込むか」というテーマからスタートしました。
まずイシイ氏は『HEAVY RAIN』や『Detroit: Become Human』を例示。序盤からすぐにキャラクターを操作できる仕組みを提供し、ゲームの雰囲気や操作方法に馴染んでもらい、プレイヤーの意欲を高めることが大切だと語ります。
イシイ氏が手がけた『428 〜封鎖された渋谷で〜(以下、428)』においても、いかに早く選択肢やバッドエンドを見せ、プレイヤーを作品に引き込むかを強く意識したと言います。
また、プレイヤーの興味を引く導入づくりには「テキストを読むためにボタンを押して進める操作」も重要。テキストの表示速度、リズム感、音、改ページのタイミングといった技術的な工夫のすべてがゲームの導入に大きく影響していると述べました。
イシイ氏が序盤でのゲーム体験を重視している一方で、小高氏は物語の理解度を深めてからゲーム体験へ移行させる手法を採用しています。これはゲームであってもアニメや漫画と同じように「つかみ」が魅力的でなければ、ゲームのインタラクティブな場面までたどり着いてもらえないという考えからです。
一例として、小高氏の最新作である『HUNDRED LINE -最終防衛学園-(以下、HUNDRED LINE)』では、冒頭で数十分にわたるプロローグムービーを組み込んでいることを紹介しました。
昨今のゲームは開始後すぐにプレイヤーに操作させる流れが一般的だからこそ、長いムービーを見せ、作品の特徴の一つになり得ると狙ったそうです。
スマートフォンゲームやSteamに向けてビジュアルノベルを開発している佐藤氏は、プラットフォームにかかわらず、すべての作品で主題歌とオープニング映像を導入していることをアピールポイントとして挙げました。
これらの要素はビジュアルノベルでは外せませんが、スマートフォンゲームでは珍しく、印象的な導入として機能していると佐藤氏は説明します。
また、ノベルゲーム市場の8割以上が海外のプレイヤーであることを踏まえ、その反応も見ながら導入への工夫を重ねていると話しました。
ゲームプレイを継続してもらうには、どのようなテクニックが用いられているのでしょうか。トークテーマは、アドベンチャーゲームにおいて鍵を握る「会話パートの演出手法」に移ります。
小高氏によると、自身が手がけるゲームではスクリプトをシナリオライターが担当するようにしているとのこと。これは、小高氏がスクリプトを「監督」に相当する作業であると捉えているからです。
「監督」としてシナリオライターが物語を最も伝えたい形で表現できれば、作品の没入感も深まるだろうと期待していると、同氏は話します。
また、小高氏は没入感のある演出の一環として、目パチ、口パクを一切入れないことをポリシーにしていると明かしました。
『ダンガンロンパ』や『HUNDRED LINE』などでキャラクターデザインを手がける小松崎 類氏は、漫画的な表情の描画も魅力のイラストレーターです。しかし、目パチ、口パクといったアニメーションを加えると表情が固定されてしまい、叫んだ瞬間のような一瞬の表情を切り取ることが難しくなってしまいます。
そのため、あえてアニメーションを入れずに小松崎氏のタッチを生かした豊富な表情差分を用意し、臨場感あふれる物語体験を提供しています。
臨場感を生み出す「動かさない」演出手法と対照的に、佐藤氏は「動かす」演出について紹介。
Live2DとSpineを併用した開発環境に身を置いている佐藤氏は「感情表現として意味のある動き」と「作品らしい動き」が各タイトルで非常に強く求められていると語ります。
静止したイラストや立ち絵であっても、キャラクターらしさを引き出す魅力的なポージングの奥深さを実感し、その探求を続けた数年間だったと振り返ります。
そして、スマートフォンゲームにおける「頭身問題」も挙げました。近年、スマートフォンの画面比率の変化が影響している問題で、例えば頭身を高めに設定したキャラクターでも、スマートフォンを横向きでプレイすると縮んでいるように表示されてしまいます。
佐藤氏はこの問題に対して、独自の数式でキャラクターの頭身比率を厳密に定義し、作品のターゲット層やテーマに応じて細かく調整して対処しているそうです。
イシイ氏は、プレイヤーの立場が主観的か客観的かによって演出方針が変わると踏まえたうえで、プレイヤー=主人公である場合は、プレイヤーを物語から置き去りにしない展開を意識していると語ります。
キャラクター同士の会話だけでストーリーが勝手に進んでしまうと主人公が物語の中心から外れ、プレイヤーの存在意義が薄くなってしまうのを危惧した判断です。
プレイヤーがゲームを中断し、再開までに時間が経った場合、ストーリーの把握やプレイヤーのモチベーションを復活させるために工夫しているポイントはあるのでしょうか。
小高氏は根本的に「止め時がないシナリオ」でプレイを中断させないことを最も重視していると語ります。
ドラマや映画、小説と同様に、あらすじがなくてもプレイしているうちに展開を思い出してもらえると考えており、過度なあらすじの説明やストーリー展開の誘導は極力入れないようにしているとのこと。
ただし、『HUNDRED LINE』ではエンディング数が100個と膨大なため、フローチャート形式を採用しています。
フローチャートの分岐点が各エンディングまでのヒントになるよう構成しつつ、分岐点にあらすじを書くことは、UIの美しさを損なうため避けています。
一方でイシイ氏は、作品の構造によって方針は変わる前提で、自身が手がけた『428』に関しては、いつでもあらすじを確認できるよう導線を設計したと語ります。5人の主人公によるストーリーが複雑に連動するパズル的な構成をしていることから、プレイヤーがストーリーの目的を見失わないように、「次に何をするべきか」という小さなサイクルづくりを重視した結果だと話します。
また、ゲームを継続させる要素は必ずしもゲーム内だけに存在する必要はないとも言います。イシイ氏が世界観監修を担当する『文豪とアルケミスト』では、アニメや舞台といったメディアミックス展開を組み込み、ゲームの外にユーザーを動かすエネルギーを用意しました。
外部コンテンツを通じて作品に触れる機会を設け、それらとゲームの内容をリンクさせることによって、一度ゲームから離れたユーザーに再び戻ってきてもらうアプローチも有効だと説明します。
運営型ゲームで運営を担当している佐藤氏は、ユーザーのモチベーションを上げる施策を2つ紹介しました。
1つ目はテレビアニメの予告編のようなボイス付き動画を都度制作し、ストーリーを振り返りやすくすることです。運営型ゲームではストーリーは徐々に追加されるため、ストーリーが更新されるまでの間に期間が空くケースも少なくありません。そこで予告動画によって手軽にこれまでのストーリーを思い出してもらい、プレイヤーに次の展開への期待感を抱かせるアプローチ方法です。
2つ目はストーリーのクライマックスにレイドイベントを開催することです。プレイヤーの協力によってストーリーが進む展開は、運営型ゲームならではの盛り上げ方といえます。レイドイベントは一度ゲームから離れたユーザーを引き戻すだけでなく、話題性で新規プレイヤーを呼び込むきっかけにもなると佐藤氏は語りました。
ストーリードリブンな作品において、物語のネタバレは作品の魅力を損なってしまう可能性があり、ゲーム実況・配信の許可は重要な検討事項の一つです。
しかし、配信活動が盛んな近年では、ゲーム実況・配信は作品の大きな宣伝として働くこともあり、一律禁止が正解とは言えないのも事実です。
『ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生』はかつて、2章以降のゲーム実況・配信を禁止にしていました(2022年12月24日に全面解禁)。この対策は物語のネタバレを防止できた反面、最後までプレイできない配信者の興味が削いでしまったと小高氏は語ります。
そこで、『HUNDRED LINE』では、発売直後の話題性を失わないよう発売前から全編の実況配信を許可していました。
この判断は、作品が「100個のエンディング」と大ボリュームである点に起因しています。小高氏はゲーム実況・配信で全エンディングをプレイするには莫大な時間がかかると推測しており、一種の挑戦状としてゲーム実況・配信を許可したと説明しました。
結果的に多くの配信者が全エンディングに到達する前に、お気に入りのエンディングを見つけたタイミングで配信の一区切りにする傾向にあるとのこと。「配信で紹介されなかったエンディングに対する視聴者の好奇心が、プレイしたいという意欲につながってほしい」と同氏は期待しています。
イシイ氏は、アドベンチャーゲームへのゲーム実況・配信問題に対してプレイするたびにストーリーが変化するシステム「ローグライクアドベンチャー」を提唱しました。
このシステムであれば、ゲーム実況・配信を見たとしても同一のストーリーは起こりづらく、プレイする際の魅力が損なわれないメリットがあります。
イシイ氏が2025年7月25日までクラウドファンディングを展開している「渋谷実写アドベンチャープロジェクト」や、ケムコで開発中の人狼テーマのアドベンチャー『Depth Loop(仮)』もこうした方針に基づき、「プレイヤーによって異なるゲーム体験を届けること」を諦めずに挑戦したいと語りました。
ゲーム実況・配信でのネタバレをボリュームやシステムで乗り越える手法に対し、ネタバレを制限せず、ユーザー間で共有して盛り上げ方もあると佐藤氏は主張します。
ストーリーが都度追加される運営型ゲームでは、シナリオの更新時にSNS上で感想や考察が投稿されます。その解釈がユーザー間で共感・共有されて盛り上がり、作品の面白さにつながると言います。
10代・20代のユーザーが多いサービスにおいては「みんなで共感できる=面白い」傾向が強く、シナリオ内でわかりやすい共感ポイントを設置することへの重要性を述べました。
今回の講演は、正反対となる手法であってもそれぞれの特徴を生かした魅力的な作品づくりは可能であり、作品のテーマやターゲット、プラットフォームによって柔軟にアプローチ方法を検討するべきだと気づかされる内容でした。
ゲーム実況・配信における「ボリューム」「システム」「共有」でのアプローチ方法は、アドベンチャーゲームというジャンルが持つ手法の自由度を再認識させられる内容であったとともに、「ゲーム業界の未来をみんなで盛り上げる」というイベントのテーマらしい期待を抱かせるものでした。
「GAME FUTURE SUMMIT 2025」公式サイトゲームを遊び、ゲームを作り、絵を描き、文章を書くエビです。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。