2023年7月25日、VTuberプロダクション「ななしいんく」が開催したバーチャルライブを題材にしたアンリアルエンジンの技術勉強会『UEなんでも勉強会 – バーチャルライブ編 – vol.1』が開催されました。
本記事では、「NANASHI Sing up vol.1-Sparkle-」を題材に、UE5でのステージ制作が解説された第1セッション「バーチャルライブ制作・大解剖」をレポートします。

2023年7月25日、VTuberプロダクション「ななしいんく」が開催したバーチャルライブを題材にしたアンリアルエンジンの技術勉強会『UEなんでも勉強会 – バーチャルライブ編 – vol.1』が開催されました。
本記事では、「NANASHI Sing up vol.1-Sparkle-」を題材に、UE5でのステージ制作が解説された第1セッション「バーチャルライブ制作・大解剖」をレポートします。
TEXT / 神山 大輝
登壇したのはREZ& Co-Founder / ディレクター NOBUAKI KAZOE氏。以前はクラブなどのステージ演出やライブ演出を専門的に行っていましたが、コロナ禍によってライブ自体の総数が減少したことからアンリアルエンジンを使用し始めたとのこと。
講演題材となったライブは2023年5月3日に開催された「NANASHI Sing up vol.1-Sparkle-」。MMTとREZ&の2社が開発を担当しており、UE5を使用するコアメンバーは9名。バーチャルライブは収録型、半収録型、リアルタイム型に大別されますが、今回は観客の反応を見ながらMCを変えたり、歌声や現場のハンディカメラに併せてライティングを変更したりするためにリアルタイムが選択されました。
収録型:事前に歌やモーションを撮っておいて書き出すパターン
半収録型:困難なダンスや演出上の都合で、一部のみ収録したものを利用するパターン
リアルタイム型:今回はこちら。歌もモーションも演出もリアルタイム。UEでPLAYしたものを配信ソフトから展開
リアルタイムの良いところは、現場で起きたインスピレーションを即時的にライブに反映できるところだとKAZOE氏は語ります。「コメントが大量に流れてきた瞬間、”お客さん入ってきた!”という感覚が大きくありました。リハの時よりもロングトーンで歌声が伸びた場合、ライティングもさらに明るくしたほうが良い演出になります」(KAZOE氏)。観客の反応を得たアーティストの機微を、細かい演出で飾っていくことができるのもリアルタイムの重要な特徴です。
『【3D LIVE】NANASHI Sing up vol.1-Sparkle-【ななしいんくミュージック】』。万が一のトラブル対応のため一部でプリレンダーの映像を使用しているが、ダンスや歌唱、ライティング演出は全てリアルタイムで行っていたとのこと
ワールド制作を行う場合、「ただのCG背景にしてはいけない」とKAZOE氏は説明します。普段の視聴者が違和感を覚えないよう、ななしいんくのワールドであることを率直に伝える必要があったほか、今回ライブに選出された4名以外も「いつか出てみたい!」と奮起するような気持ちに繋がる豪華なライブステージが目指されました。
今回は神聖さや聖域、特別なライブステージというキーワードに繋げるため、テーマを「教会」と設定。教会自体はもともと音が響くような建築設計になっているため、「ななしいんくの活動が世界に響き渡るように」という想いも込められました。
「いつか出てみたいと目指す場所」として、例えばフジロックにおけるGREEN STAGE(約40,000人を収容できる、場内最大のステージ)のように、「音楽フェスのメインステージ」という題材が選ばれました。「教会」と「メインステージ」というコンセプトから、ワールドディレクターが全体のシルエットを作成。この時点で昼と夜のライティングを試しており、全体像についてななしいんく側との合意形成を行います。
続いてキットバッシュによるディティールの設計に入ります。これについては「マーケットプレイスが最高!」というKAZOE氏の言葉通り、ワールドの世界観を示すような蝋燭や燭台などのアセットを次々と購入・配置していったとのこと。また、「歌うななしさん像」など、直接的にななしいんくのステージであると理解が深まるようなキーアセットも配置し、全体の解像度を高めていくことも重要と語られました。
KAZOE氏のお気に入り&使用したマーケットプレイス一覧:
Medieval Gothic Cathedral – Gothic Dungeon – Modular
Dungeon Entrance – Dungeon Kit – Dougeons
Modular Concert Stage
Complete Modular Truss Megapack
※最もお気に入りは「Modular Concert Stage」。アップデートによってDMXにも対応したとのこと
ワールド自体のベースとなるライティングはワールドディレクター側が調整。ライブステージが全部暗転したとしても数箇所だけは点灯している状態で、最低限ワールドの世界観をキープできる状態を作っています。デフォルトのライトが明るすぎるとライブ会場風にならないため、今回は夜の教会をリファレンスとしてライティングを設定。この際に参考にしたのは「Lighting a NIGHT-TIME exterior in Unreal」チュートリアルであるとのこと。
本作の次に制作されたRene Ryugasaki 1st solo live「Garnet Moon」では、本作を超える4つのワールドが用意された。「仮想の東京で歌っている」というテーマに則り、東京駅や東京タワーをモティーフしたステージが制作されている
多くのVTuberはUnityでライブ制作しているため、アンリアルエンジンでライブ制作を行う場合はデータ変換やルックの調整等を含めて通常より多くの工数が掛かります。初期コストは掛かりますが、それ以上にライティングのルックが大きく向上するメリットがあるとKAZOE氏は指摘します。
今回は照明スタッフが現実のライブ会場で演出を行うように、リアルタイムでライト演出を行います。このため、ワールド上にも現実空間に即したライトがセッティングされました。
ラダー配置やアクト(演者)を包むように照らすフィルライト、アクトを正面から照らすキーライト、神殿の内部を照らす灯体などを設定。キーライトだけでは顎のシェーディングがおかしくなる場面もあるため、フィルライトなども併用。現場でライティングを担当するメンバーが入っても分かりやすい作りになっている
ステージ演出で重要なムービングライトのビームについては、DMXフィクスチャーをカスタマイズした灯体(照明器具の総称)を開発したとのこと。また、ムービングライトに入っているゴボ(柄)に応じてビームの形が変化するため、ゴボはオリジナルを用意しています。
DMX512は照明装置の調光・調色を行うための通信規格。アンリアルエンジンユーザーには馴染みが薄いかもしれないが、舞台やライブの現場ではごく一般的に使われる規格だ。KAZOE氏は普段grandMA3やTouch Designerで自作したコントロールユニットで制御しているとのこと
「ライトを右から当てたら左の影が大変なことになる!」「キャストシャドウが入っていないのが悪さをしているのかも?」など、ルックの調整はシェーダーアーティストと密接なコミュニケーションを取り合いながら改善を繰り返す形で進行。
また、今回はすべてがリアルタイムのライブであるため、ハンディカメラマン(ステージ内でライブ撮影を行うカメラマン)が存在するのもポイント。カメラマンがどんな角度から撮影を行っても問題がないように破綻のないルックを作ることが必須であり、キャラクターの横顔アップなど特に難しい角度からカメラを入れる場合はフィルライトを強めに当てて即対応できるよう仕組み化しておくなど、事前の仕込みの重要性が説明されました。
こうしたライトの全体デザインが完了後、演出的なライティングを楽曲に合わせて打ち込みます。この際、特定の灯体はGPU負荷が大きいため、ライトの影響範囲を狭めたり、クオリティを落としたりして最適化を図っているとのこと。
ステージ内の演出として、仮想的なスクリーンに映像投影を行うVJ表現も取り入れている。海の泡などはNiagaraで実装するより、VJ的に投影したほうがフレキシビリティに富んだ演出が可能になるとのこと。また、プロジェクションマッピング的な演出はデカールで行うなど、最適化の工夫も行われていた
また、講演後は実際のプロジェクトが開かれ、ハイクオリティなステージをリアルタイムでプレビューしながらライト演出を行う様子が確認できました。続く質疑応答でも本番環境のマシンスペックや冗長性のためにPC3台編成で臨んでいる旨など、実践的な内容で大いに盛り上がりました。
「NANASHI Sing up vol.1-Sparkle-」 動画アーカイブUEなんでも勉強会 - バーチャルライブ編 - vol.1 動画アーカイブゲームメーカーズ編集長およびNINE GATES STUDIO代表。ライター/編集者として数多くのWEBメディアに携わり、インタビューや作品メイキング解説、その他技術的な記事を手掛けてきた。ゲーム業界ではコンポーザー/サウンドデザイナーとしても活動中。
ドラクエFFテイルズはもちろん、黄金の太陽やヴァルキリープロファイルなど往年のJ-RPG文化と、その文脈を受け継ぐ作品が好き。
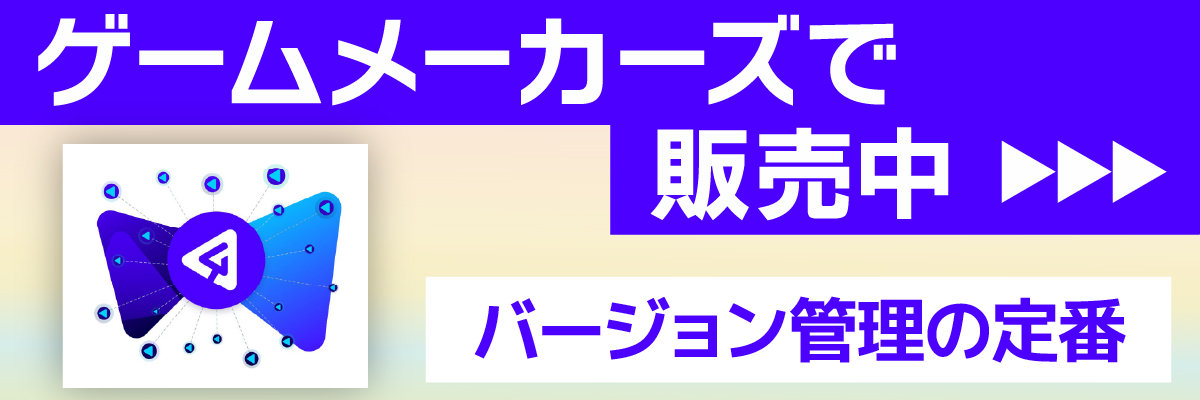
西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。




