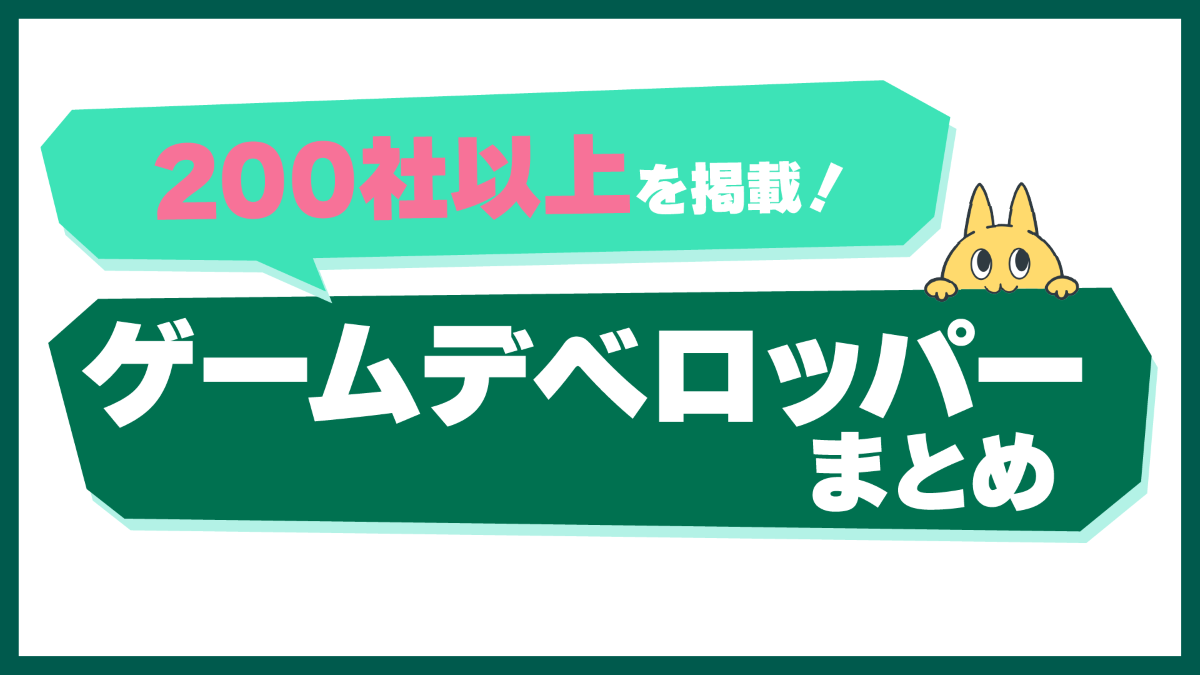国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2022(以下、TGS)」が、2022年9月15日(木)から9月18日(日)まで開催されました。本記事では、インディーゲームコーナーに出展した「青エビ研究所」と、『バイナリ・シンドローム』に注目。個人サークルである青エビ研究所のtyap(チャップ)氏にインタビューしました。
※『バイナリ・シンドローム』の画面は、すべて開発中のものです
国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2022(以下、TGS)」が、2022年9月15日(木)から9月18日(日)まで開催されました。本記事では、インディーゲームコーナーに出展した「青エビ研究所」と、『バイナリ・シンドローム』に注目。個人サークルである青エビ研究所のtyap(チャップ)氏にインタビューしました。
※『バイナリ・シンドローム』の画面は、すべて開発中のものです
TEXT / 藤縄 優佑
EDIT / 神山 大輝
インタビューの前に、『バイナリ・シンドローム』について簡単に紹介します。『バイナリ・シンドローム』はNEC PC-9800シリーズ(以下、PC-98)用ゲームをリスペクトしたアドベンチャーゲームで、SteamおよびBOOTHでのリリースを予定しています。また、VHSケースにフロッピーディスク、ゲームのダウンロードコードなどを収納したパッケージ版も発売するとのこと。
物語は、人とアンドロイドがともに生きる近未来の世界を舞台に、再起不能に陥ったアンドロイドたちへのカウンセリングを通じて治療法を探るというもの。ゲーム中は「LOOK」「TALK」「THINK」「MOVE」などのコマンドが常時表示されており、状況に応じて適切なコマンドを選ぶことでストーリーが展開されます。
こうしたシステムや、FM音源のみ使用したBGM、色数を20色に制限したドットグラフィックなどにより、PC-98用ゲームの雰囲気を演出しています。なお、PC-98用ゲームでの色数は16色であり、tyap氏もそれを目指していたものの、作っているうちにオーバーしてしまったそう。「16色に抑えるハードルは相当に高くて難しい」とtyap氏は話していました。
――PC-98用ゲームに刺激を受けたことが、『バイナリ・シンドローム』を作るきっかけだったのでしょうか。
PC-98用ゲームの画像を調べてみたのが『バイナリ・シンドローム』を作るきっかけになったため、視界に入ったすべてのPC-98用タイトルが制作のきっかけといえるかもしれません。
当時のゲームグラフィックはどれも甲乙付けがたいほど素晴らしいのですが、『ふしぎの海のナディア』や『サイレントメビウス』をはじめとするガイナックス製ゲームのグラフィック全般に感銘を受けました。個人的に、ガイナックスに関しては色使いの鮮やかさが頭一つ抜けているように感じます。何度見ても16色とは思えませんね……。
――『バイナリ・シンドローム』で注力している点を教えてください。
絵を描くことが好きでゲーム制作を始めたのもあり、グラフィックは特に力を入れています。イベントごとに新たにグラフィックを描きますし、アニメーションもさせているので、どのキャラクターも描くボリュームは膨大になります。ですので、キャラクターデザインは「自分が描いていて楽しいか」を大切にしています。
――グラフィック制作に使っているアプリと、採用理由を教えてください。
「CLIP STUDIO PAINT」でドットペンを使いながら描画しています。普段から使い慣れているアプリですし、有志の方が素材をアセットストアで公開してくださっているからですね。役に立つ複数のドットペンをありがたく使わせてもらっています。
また、ドット絵として線の重なりをなくすため、一括で線幅を細く修正できるツールにも大いに助けられています。あまりにも便利すぎて、なくなったら本当に困るレベルです。
――tyapさんはこれまでにWOLF RPGエディターで『L0ST M@IL』、『廃品回送』の2タイトルを制作しました。一方、『バイナリ・シンドローム』はティラノビルダーで制作していますが、なぜ移行したのでしょうか。
文章メインのゲームに必要な機能がデフォルトで搭載されていたため、効率よく作業するためにティラノビルダーに移行しました。もともとティラノビルダーに興味があり、いつか触ってみたかったのも理由の一つです。
ティラノビルダーは、キャラクターチップを動かすようなゲームを作るのは大変なのもわかったので、作るゲームのジャンルに合わせて臨機応変に対応していきたいですね。
――ティラノビルダーの気に入っているポイントや機能は?
スクリプトを組まなくてもパズルのようにゲームを制作できることと、UIが直感的でわかりやすいことです。
ティラノビルダー上でもティラノスクリプトは使えるため、「キャラクター画像はプレビューが付いていてわかりやすいティラノビルダーで制作し、変数分岐や凝った仕様はティラノスクリプトが担当」と、役割に応じてツールを使い分けられるのも魅力の一つです。
――ティラノスクリプトも使っているとのことですが、どういった機能を実装しているのでしょうか。
ティラノビルダーでは、レイヤーや画像ボタンのマウスホバーなど細かい指定はできません。そうしたティラノビルダーの基本機能だけでは間に合わない部分をティラノスクリプトで書いたり、css、htmlなどをいじったりしています。
具体的には、マウスオーバーで文章の選択肢の色を変えるなどしています。最初からティラノスクリプトで組まれている方から見たら使いこなせていないかもしれませんが……自分なりに工夫しているつもりです。
――その他、工夫しているところを一つピックアップして伺いたいです。
細かいですが、瞬きのアニメーションのスピードを調整しているところでしょうか。たとえば、驚いた表情をしているときは瞬きを早めに設定したり、悲しい表情では目を瞑る時間を少し長めに設定したり、感情がより伝わりやすくなるように変えています。
また、キャラクターによっても変化をつけています。軍事用アンドロイドの「ニゲル」でいえば内蔵されたシステムの設定により、瞬きも他のキャラより遅くしています。
――開発で詰まったことはありますか?そのときに参考になったWebサイトや書籍があれば教えてください。
コマンドを選択しようとすると、カーソルデザインがデフォルトに戻ってしまう点で悩みました。2021年に公開した本作の体験版では実力不足で修正できませんでしたが、どうしても修正したかったので、とにかく「ティラノ カーソル」などで何度も調べまくりました……。
プログラミング初心者なので困ることが次々に生まれ、そのたびにインターネット上の知恵のすべてを参考にしています。
――TGSでは、インディーゲーム選考出展に選ばれました。TGSに初めて出展した感想はいかがでしょうか。
2021年にサークル参加した「デジゲー博」とは雰囲気が少し違って興味深かったです。デジゲー博ではインディーゲームに興味のある方が多く来場されますが、TGSは有名メーカーさんと同じ日程・会場で出展するので、インディーゲームにあまり触れたことのない方も多かったように感じました。海外の方が多いのも、規模の大きなゲームイベントであるTGSならではだと思いました。
今までと違う客層にアプローチできた良い機会だったと思います!
――ゲームイベントの展示で気を付けていることを教えてください。
「青エビ研究所」という名前で活動しているため、青を基調とした色合いにしています。また、試験管やPCなどのミニチュアを調達して研究所らしさを演出するなど、名前の印象と齟齬のないディスプレイになるよう意識しました。
あとは自分が思う「かわいい」を信じることでしょうか。TGSでは壁も使えたので壁紙を貼り、せりだしたアーチ状のプレートを生かしてカーテンのような幕も設置しました。使える場所はとにかく有効活用しています!
――『バイナリ・シンドローム』はSteam、BOOTHでのリリース予定です。プラットフォームを拡充する予定などはありますか。
ゲームの有償販売は本作が初めてで、現在は自分の目の届く範囲だけで進めています。もう少し慣れたら他のプラットフォームで配信できたらと思います。
――BOOTHやゲームイベントで、体験版のダウンロードコードが付属したフロッピーディスクを販売していましたね。
PC-98リスペクトを謳っているので、販売する媒体もリスペクトしようと思ってそうしています。自分は本やCDなど物理媒体が好きな人間だからという理由もあります。
フロッピーディスクは生産終了しているため、未使用品を見かけたらその都度確保するようにしています。動作確認されていないものが大半ですし動かないモノもたまに混ざっていまして、動作を確認するたびにヒヤヒヤします(※)。
※フロッピーディスクにゲームそのものは入っていないが、おまけのデータを入れているため動作を確認している
――ローカライズについて、多言語展開の予定はいかがでしょうか?
中国語の簡体字、繁体字の翻訳が決定しています。個人で制作しているうえ、文字数が多くなりそうなので難しいかもしれませんが、将来的には他の言語にも翻訳していただけるご縁があったら良いなと思います。
――難航していることはありますか?
FM音源によるBGMはフリー素材をお借りしているのですが、可能であればオリジナル曲にしたいです。ですが、「FM音源の楽曲制作が可能な方」を探してもなかなか見つからず、ハードルが高い気がしています。多言語展開と同様にコストの問題もあるので、慎重に考えております。
――ゲームイベント出展にもお金がかかりますし、コストの問題はたしかに大きそうです。
TGSは選考出展に選ばれたおかげで、出展料が無料だったり宿泊費が補助されたりといった特典がありましたが、それでも大きな出費でした。BOOTHでグッズ・体験版などを購入していただいたり、pixivFANBOXで支援してくださっている方々のおかげで、当初のイメージよりも活動の幅を広げられています。また、温かい応援やフィードバックも、本当に開発のモチベーションにつながっていると実感しています。
――開発状況や目標とするリリース時期などを教えてください。
システム部分の土台は完成に近いので、あとは肉付けしていくようにストーリーを組み込んでいく予定です。基本的に自分一人で制作していているため、明確なリリース時期はお伝えするのが難しいのですが、来年か再来年までにはリリースしたいという目標で開発しています!
青エビ研究所 公式サイトtyap pixivFANBOX編集プロダクション「浦辺制作所」に所属。ITやゲームにかかわる書籍・Webメディアにおいて、執筆と編集を担当している。ゲーム全般が下手だけど好き。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。