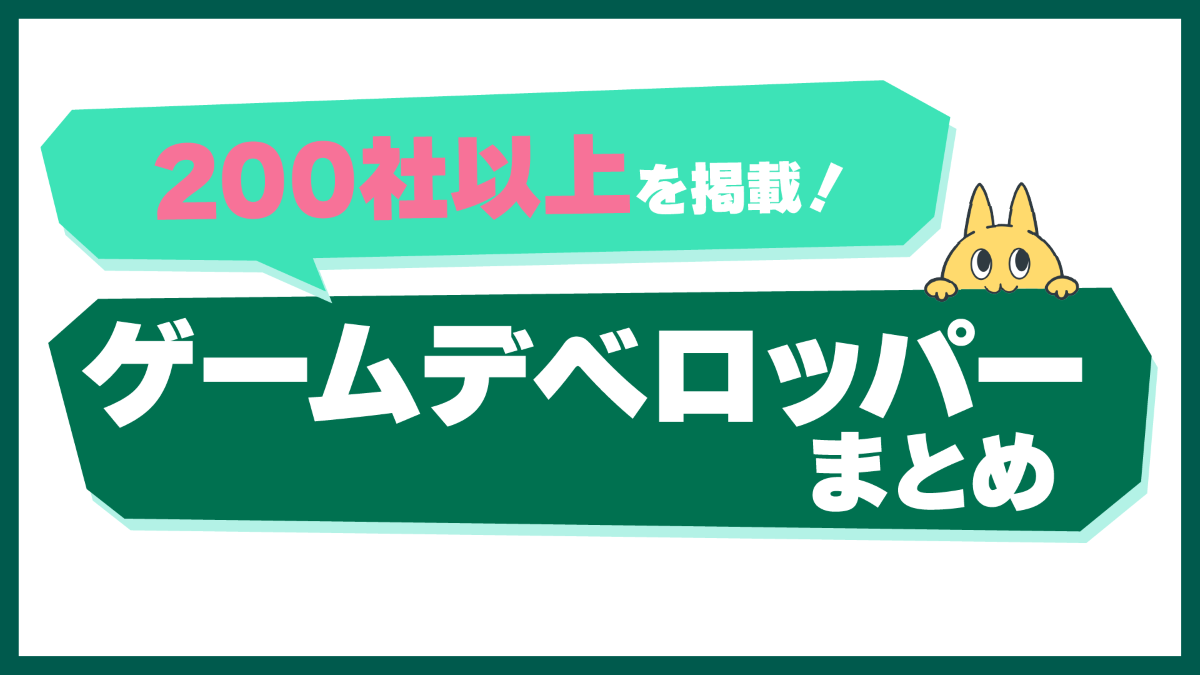2025年3月29日、大阪の梅田スカイビルウエスト10階 アウラホールにてインディーゲーム展示会「ゲームパビリオンjp」が開催されました。
今回で3年連続の開催となり、出展者数はなんと130以上に。関西インディーゲーム界における春の風物詩とも言えるイベントに成長した「ゲームパビリオンjp」の模様を、ライターがプレイして気になった作品のピックアップレポートを中心にお届けします。
2025年3月29日、大阪の梅田スカイビルウエスト10階 アウラホールにてインディーゲーム展示会「ゲームパビリオンjp」が開催されました。
今回で3年連続の開催となり、出展者数はなんと130以上に。関西インディーゲーム界における春の風物詩とも言えるイベントに成長した「ゲームパビリオンjp」の模様を、ライターがプレイして気になった作品のピックアップレポートを中心にお届けします。
TEXT / ハル飯田
EDIT / 酒井理恵
最初に紹介するのは対戦画面にどこか懐かしさも感じる『Skill Hockey』。その名の通りエアホッケーにスキル(技)の要素が加わった作品で、直感操作でライフ制のホッケーバトルが楽しめます。
操作キャラごとに3種類の必殺技が用意されていますが、発動のためには矢印キーによる「コマンド入力」が必要。マウスでマレットを操作しながらキーボードで「↑ ↑ ↑」「← → ← → ← →」と、格ゲーさながらの指さばきが要求されます。
必殺技の効果はマレットが大きくなったりパックが増えたり、あるいは相手の攻撃を防ぐ壁が出現したりとプレイ感をガラリと変える強力なものばかり。しかし、技にはクールタイムが設定されており、コマンドの受付タイミングも「パックを敵陣に撃ってから帰って来たパックを直接打つまで」に完成させなければならないので、ラリー中に乱発とはいきません。
ゲームのルール自体は非常にシンプルですが、エアホッケーはスピード感があり忙しいゲームのため、長いコマンドを入れようとしてマレット操作をおろそかにしてはいけない、マルチタスクの難しさが印象的。
会場ではAIとの対戦が楽しめましたが、お互いに技を出しあうと盤面はかなりカオスになりバトルは白熱。AIも決して強すぎず弱すぎずで、上手く技を繰り出せたタイミングや得点の喜びを味わえました。
『Skill Hockey』を手がけているのは「Bogosor Games」の皆さん。エンジンにはUnityを使用しており、デザイナーやプログラマーなど3人チーム体制での開発を進めています。
本作が生まれたきっかけは、2024年に懐かしのPCゲーム「エアホッケー」のブラウザ版が公開されたこと。同時期に開発者自身がプレイしていた格闘ゲームに着想を得て、コマンド入力の要素をミックスしてみたことでスピード感ある対戦作品が生まれています。
絶妙な強さでゲームを盛り上げる敵AIの制御は、相手(プレイヤー)側にパックがある状況ではプレイヤーの左右の動きをトレースしてディフェンスをする仕組みに。自陣にはピンチと判定される領域があり、そこにパックが入ってくると「弾速から0.1秒先のパック位置を予測して打ち返す」というシステムになっています。
防御操作にはランダムでミスが発生するため、そこが得点チャンスに。なお、AI側も必殺技の発動には内部でコマンド入力処理がされていますが、いわく「人間には不可能なスピードでの入力」もこなしてくるとのことで、AIへの勝利を目指すだけでもかなり歯ごたえのあるゲームプレイが楽しめます。
取材時点では開発状況は4割程度で、追加キャラクターオンライン対戦の実装などを進めていく予定とのこと。今後は「必殺技の受け付けタイミングが分かりやすいUI」や「レバー操作への対応」なども検討しているそうで、レバーでコマンド入力しながらマウスでマレットを動かす唯一無二の操作方法のゲームが誕生するかもしれません。
イベントによっては“アーケード筐体風”のブースを制作しての展示も行われているそうなので、懐かしのホッケーゲーム好きの方やコマンド入力に自信のある方はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
タイトル:『Skill Hockey』https://store.steampowered.com/app/3074910/Skill_Hockey/
開発:Bogosor Games https://x.com/bogosorgames
ゲームエンジン:Unity
リリース予定日:2025年
ジャンル:アクション
プラットフォーム:Steam
開発中のゲームには大小のバグがつきものですが、そんな「バグ」をテーマにした作品が『DebugDebut』です。
プレイヤーはデスクトップ内に出現したアシスタントAIに導かれ、さまざまなゲームのデバッグ作業をすることに。作中にはシューティングやパズルなどさまざまなジャンルのゲームが収録されているので、ゲームごとの基本的な「仕様説明」と「チェックリスト」を確認しながらプレイして、バグを見つけ出していきます。
ゲームとチェックリスト画面はワンボタンで切り替え可能で、リストの確認中はゲームが一時停止になる親切設計。出現するバグは「スコアが設定された値と異なる」や「リザルト画面が表示されない」など、あるあるなものから、特定の操作をした際に「予期せぬエラー」としてゲームが止まってしまう重大なものまでさまざまです。
ステージごとに発生するバグはランダムですが、バグの個数は示されている(ステージによっては大まかな数字の場合も)仕組み。明らかなバグが発見できてあっという間に1ステージクリアになることもあれば、最後までプレイしてもそれらしき挙動が見当たらないこともあり、ついつい「バグ出てこい!」と念じてしまいます。
デバッグ作業がモチーフではありますが、「壁をこすりながら走る」ようなガチガチのバグ探しではなく、「リストに沿う縛りプレイ」のような感覚でさまざまなジャンルのゲームをプレイできるテンポの良い作品になっています。
今回のデモ版ではチュートリアル+2ステージが体験できましたが、製品版では10ジャンルほどのボリュームを予定。ステージをクリアしていく報酬を活用するシステムや、そもそも「なぜデバッグをすることになったのか?」というシナリオ面の深掘りにも注目です。
『DebugDebut』を開発するのは「BeaverDevelopment」代表のタゴ氏。本業はスマートフォン向けゲーム開発を行うプログラマーであり、個人開発で2年前から本作に取り組んでいます。
使用エンジンはUnityで、アートにはBlenderやPhotoshopを活用。「アートは苦手分野で、Blenderを1から勉強」してAIのモーションを設定しているとのことでしたが、AIくんのモーションはそれを感じさせないほど滑らかで豊かな表現になっていました。
本作は大ヒットした『8番出口』に象徴される、「間違い探し」要素を含んだゲームの流行からインスパイアされた作品で、タゴ氏としては「簡単で遊びやすいゲーム」を志向しており、今後はもっと派手で笑えるような分かりやすいバグも取り入れていきたいとのこと。
作品に“本当のバグ”が残るとプレイに大きな影響が出てしまう、そして単純に10ステージ開発のためには「10ジャンルのゲーム開発」が必要になるなど、ゲーム性ならではの大変さも感じられる作品ですが、タゴ氏は「気合いで頑張ります」と苦笑い。
本業の傍ら独力での開発とあって大変さもあるそうですが、アイデアの初期からはさまざまに仕様変更を繰り返しており、自分の判断ですぐに変更を実装できる個人開発ならではの流動性の高さもバッチリ活用しているとのことでした。
タイトル:『DebugDebut』https://store.steampowered.com/app/3387340/DebugDebut/
開発:BeaverDevelopment https://x.com/BeaverDevInfo
ゲームエンジン:Unity
リリース予定日:2026年
ジャンル:シミュレーション
プラットフォーム:Steam
「ゲームパビリオンjp」には数多くの学生クリエイターの作品も出展。特徴的なデバイスを使った作品や凝ったシステムの作品など個性的なタイトルが数多く並びましたが、今回はそんな中から大阪電気通信大学の学生が生み出した『KeyTyper』を紹介します。
『KeyTyper』は「自機をゴールに移動させる」というオーソドックスなルールのアクションゲームですが、操作方法は「画面に表示されているキーを押した場所に移動する」というもの。障害物にあたらないよう、タイミングよく正しいキーを押して進まなければいけません。
コースは途中でNORMALとHARDに難易度分岐するほか、特定のポイントでは「doahakai(ドア破壊)」とタイピングすることでドアを破壊する能力を得られる、キーボード操作ならではのギミックも搭載。
クリアまでのタイムも記録されるので急いでタイピングして好タイムを目指したいところですが、ミスは一発アウトというシビアな側面もあるのでタイミングは重要。とはいえミスになった後のリスタートも素早いのでストレスはなく、気軽に再チャレンジできます。「落ち着けば絶対にクリアできるけれど、記録を詰めようと思うと難しい」印象で、タイムアタックに挑戦したくなるタイプの作品でした。
ルールと操作が一体になっているゲーム性は、短い時間で操作を覚えてもらいたい展示会の場にもピッタリ。他の人のプレイを見ているだけでもルールが理解しやすく、夢中になってチャレンジする小さなお子さんの姿も見られるなど、ブースは大いに賑わっていました。
『KeyTyper』を開発したのは大阪電気通信大学1年生(取材時点)の熊谷氏。
「ほとんどのゲームでキーボードは移動用のWASDキーしか使わないので、逆に全部使うゲームを作ってみたらどうか?」というアイデアから2か月半の個人開発で制作されており、フリー音源以外は素材もすべて自分で制作。ゲームエンジンはUnityで、アートには「アイビスペイント(ibisPaint)」を使用しています。
開発においては「パッっと見て操作が分かるシンプルなゲームにすること」を心がけていたそうで、「キーボードを全て使う」というやや複雑なゲーム性にも繋がりそうなアイデアを簡潔にまとめられる要因に。
会場で多くの来場者とコミュニケーションされていた熊谷氏は「中間地点があっても良かった」と、改善点も見つかった様子。また、技術的な部分では「複数通りの入力が可能な日本語の対応は複雑で、今は表示された通りにタイピングしてもらうシステムになっています」と、日本語での開発ならではの難しさも見つかる開発となったそうです。
今回展示されていたバージョンはクリアまでの1ステージのみでしたが、まだまだ拡張性もありそうな『KeyTyper』。今後については「もっと広いステージやボス要素を追加しても面白いかも」と意欲を見せつつ、他の作品も作ってみたいと話しており、熊谷氏や同学の学生が自由な発想で生み出すゲームが楽しみになるブースでした。
タイトル:『KeyTyper』
開発:大阪電気通信大学「電ch!ゲーム制作プロジェクト」 https://x.com/dench_gdp
ゲームエンジン:Unity
リリース予定日:未定
ジャンル:アクション
プラットフォーム:PC
春休み中ということもあり、幅広い年代の来場者で大賑わいとなった今回の「ゲームパビリオンjp」。初回となった2023年の開催と比較すると出展者数は1.5倍以上となり、スペースをほぼ余すことなく使用するレイアウトに変更してもキャパシティいっぱいの大型イベントへと成長しました。
今回はSteam上に特設ページも開設されたほか、会場内からクリエイターが直接ゲームの内容を紹介するライブ配信も実施。会場に行けなかった方のためのコンテンツも充実しています。
そんな「ゲームパビリオンjp」ですが、会場となっている梅田スカイビル10階の「アウラホール」が3月末にて営業終了となるため、同会場での実施は今回がラストに。今後は新たに大阪市中央区の展示場「マイドームおおさか」に会場を移しての開催を予定しており、まずは2025年8月の実施を目指して準備が進められています。
「ゲームパビリオンjp」公式サイト「ゲームパビリオンjp」公式Xアカウント大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。
ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。