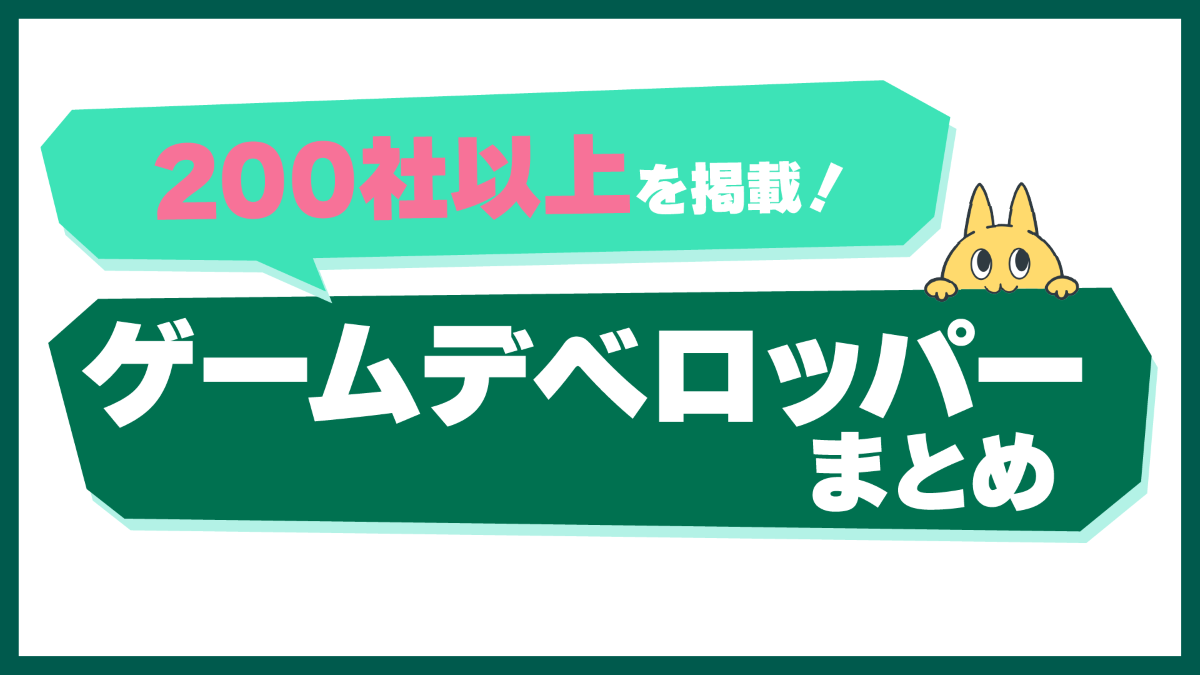2025年2月15日(土)・16日(日)、東京都立産業貿易センター浜松町館 5階展示室にて、インディーゲーム展示会「東京ゲームダンジョン7」が開催されました。
今回は、会場で展示されていた『超増税都市』を紹介するとともに、同作の開発チーム「ソラマメ工房」にお話を伺いました。
2025年2月15日(土)・16日(日)、東京都立産業貿易センター浜松町館 5階展示室にて、インディーゲーム展示会「東京ゲームダンジョン7」が開催されました。
今回は、会場で展示されていた『超増税都市』を紹介するとともに、同作の開発チーム「ソラマメ工房」にお話を伺いました。
TEXT / 藤縄 優佑
『超増税都市』は、3人組の開発チーム「ソラマメ工房」が手がけるローグライト作品で、2025年1月にSteamで正式リリースされたばかり。
『街づくり×ローグライトゲーム「超増税都市」トレーラー』
パブリッシャーはKTMG社のブランド「KIC Games」が担当しています。
同ブランドは、神戸情報大学院大学・神戸電子専門学校による教育・研究活動の事業化支援を目的としている、珍しいパブリッシャーです。ソラマメ工房の皆さんは同学校の卒業生という縁から、KIC Gamesと契約しています。
KTMGは『蒐命のラスティル – とこしえの迷宮城 -』の開発や、インディーゲーム展示会「神戸ゲームラビリンス2024」主催も担っている(画像はKTMG社公式サイトより引用)
『超増税都市』は5×5マスで区切られたマップに施設を建設し、制限時間内に納税するためにお金を稼ぐ、ステージクリア型のローグライト街づくりゲームです。
施設は一定時間ごとにランダムで3つ抽選され、そのなかから1つだけ建設可能。施設ごとに効果は異なり、施設の位置関係などに応じてシナジーが起こります。
運によって選ばれた施設をどこに建てるべきか悩みながら、より稼げる都市になるよう試行錯誤するのが楽しい作品です。
ここからはソラマメ工房を代表し、プログラマーの「のっぽ」氏(@nopopo190)に開発に関するお話を伺いました。
まずは筆者が個人的に気になったゲームバランスの調整方法から質問してみました。同氏は、ローグライトで人気のゲームと近い難易度で遊べることを目指したといいます。
調整方法は、まず各施設のパラメータやステージのルールなどを大まかに決めたら、複数の知人にゲームをプレイしてもらい、感想や反応を見て調整していきます。展示イベントでの試遊、Steamで公開した体験版の反応もチェックしながら繰り返し微調整し、製品版のバランスとなりました。
体験版配信により、うれしい誤算も生まれました。期間限定で配信した、市民の数がだんだん増える特別仕様のステージが非常に好評だったのです。チームとしても面白さを確信し、特別な仕様ではなくゲーム本編のフローに組み込まれました。
本作でもっとも苦労した調整は、ステージの初期難易度であるレベル1。リリース1か月前まで、レベル1は今の難易度より倍近く難しいものにしていました。
原因は、テストプレイを繰り返すうちに開発チームの腕前が上がり、レベル1が簡単すぎるように思えてしまい、無意識に難しくしてしまったこと。
外部の方にテストプレイをお願いしたときに、難しさを指摘されて初めて問題を認識したといいます。
その後は「簡単にしすぎない」点を最も意識しながら、レベル1を中心に調整しました。ローグライトで一番楽しい瞬間は、「シナジーを見つけて実行し、通常の何倍もの効率が生まれたとき」。
これがチームの共通認識であり、初見プレイ時にも実感してもらうためには「カジュアルに遊べる、かつ手応えを感じられる難易度」という、一見矛盾しているような難易度に調整する必要があると、開発陣は考えました。
ここからはひたすら満足いくバランスになるまでリリース前日まで粘り強く調整し続けたと話します。
そうした度重なる地道な調整が、プレイヤーから人気を得た理由のひとつなのかもしれません。筆者個人としての感覚では、体験版リリース時から多くの方によくプレイされていた印象で、製品版の実績解除率も高く見えます。
のっぽ氏は、「体験版を100時間以上もプレイしてくれた方が複数名いらっしゃって驚きました。製品版も、すべての通常ステージのレベル1をクリアしていただける方が多かったらうれしい、くらいの想定でしたが予想を大きく上回りました。」とコメント。
本作リリース後、著名なストリーマーも含め多くの方が本作を配信していたように思います。これについては、同ジャンルのゲームを好んで配信している方に対し、国内外問わずにSteamキーを添付したメールを送っていますが、有償依頼はしていないとのこと。
「どなたの配信も、かなり影響がありました。同ジャンルのゲームを中心に取り扱ったストリーマーさんが配信したときは、とくに売れ行きにも反映されました」と、配信への影響も話していただけました。なお、開発チームの一人は「しんじさん」のファンで、しんじさんに配信してもらえて感激したとお話ししていました。
本作の開発環境などについて、ここからのっぽ氏に解説していただきます。
のっぽ:ゲームエンジンとしてはUnity 2021.3.23、ドットグラフィックの制作にはAsepriteを使って開発しました。開発中は、Unityのアセット「Hot Reload」「Fullscreen Editor」がとくに役立ちました。
「Hot Reload」は、ゲーム実行中にコードを変更しても即座にゲームに反映できるアセットで、リロードの手間やコンパイルの待ち時間がなくなり、効率よく演出の確認などが行えるようになりました。
『Hot Reload Intro』
「Fullscreen Editor」は、その名の通りエディタをフルスクリーン表示できるツールです。ショートカットでシーンビューやゲームビューを呼び出せるようになるので、ビューの切り替えも簡単。ゲームのスクリーンショットや動画を撮影するときに活躍しました。
『Fullscreen Editor – Unity Asset』
開発で工夫したポイントも伺うと、マスターデータの管理手法について教えていただけました。
のっぽ:ゲームに登場する施設などのパラメータ管理にはUnityのデータコンテナ「ScriptableObject」を使っていますが、扱うデータ量の多さからエディタ上で「ScriptableObject」を設定するのが大変厳しい状態でした。
そこでマスターデータはGoogle スプレッドシートで作り、マスターデータをScriptableObjectに流し込むエディタ用スクリプトを自作しました。
これにより、エディタ上でボタンを押すだけで、スプレッドシートにあるマスターデータを反映できるようになりました。バランス調整のためにパラメータ変更は何度も行うので、管理方法を見直して良かったです!
ちなみに、マスターデータ関連で有名なライブラリだと「Master Memory」などがありますが、そこまで複雑なことがしたいわけではなかったので、この方法で十分運用できました。
最後に『超増税都市』の今後について伺うと、「皆さんのおかげで、発売から20日ほどで1万本を売り上げることができ、非常にうれしく思います。ですが、海外での認知度がまだまだ低いので、これからは海外向けの広報活動に力を入れていきたいです。また、先にはなりそうですが別プラットフォームでの発売に向けても動いていきます!」と、力強いお言葉をいただきました。
ソラマメ工房としては、『超増税都市』以降の作品もローグライク・ローグライトな作品を手がける「ローグライク専門開発チーム」として活動したいとしていました。
『超増税都市』Steamストアページ「ソラマメ工房」Xアカウント編集プロダクション「浦辺制作所」に所属。ITやゲームにかかわる書籍・Webメディアにおいて、執筆と編集を担当している。ゲーム全般が下手だけど好き。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。