2025年4月13日(日)、ホロライブの白上フブキさんが主人公の2D横スクロールアクション『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』がSteamで配信されました。
今回、本作の開発者であるPEPOSOFT氏と、パブリッシングを担当したPhoenixxの小田 響之氏にインタビューする機会を得たため、本記事にまとめました。開発体制・開発環境からこだわりのポイント、パブリッシングの戦略まで深掘りしていきます。
2025年4月13日(日)、ホロライブの白上フブキさんが主人公の2D横スクロールアクション『FUBUKI ~zero in on Holoearth~』がSteamで配信されました。
今回、本作の開発者であるPEPOSOFT氏と、パブリッシングを担当したPhoenixxの小田 響之氏にインタビューする機会を得たため、本記事にまとめました。開発体制・開発環境からこだわりのポイント、パブリッシングの戦略まで深掘りしていきます。
INTERVIEW / 藤縄 優佑
SUPPORT / ハル飯田
まずは『FUBUKI ~zero in on Holoearth~(以下、FUBUKI)』の説明から。同作は、カバーの「ホロライブプロダクション」による異世界創造プロジェクト「ホロライブ・オルタナティブ」の一つとして制作されたアクションゲームです。配信プラットフォームはSteamで、6月27日~7月11日午前2時までサマーセールが実施中。
『FUBUKI』は、ホロライブ・オルタナティブのティザーPVや漫画作品『ヤマト神想怪異譚』などの世界観を参考に制作されている
本作の舞台は「ホロアース」。国同士をつなぐゲートに異変が発生したことを契機に、「ヤマト」に住む「カミ」として主人公「白上フブキ」が冒険を繰り広げます。
ゲーム内容としては好きなステージを選んで挑戦できる方式で、ステージによって異なる敵やギミックが登場。ステージの最後には「ケガレ」の影響を受けたホロライブメンバー(ホロメン)がボスとして立ちはだかります。
白上フブキさんの武器は愛刀「ムラサメマル」。通常攻撃のほか、斬撃を飛ばす溜め攻撃「チャージショット」を使い分けながら戦います。移動に関してはダッシュや2段ジャンプ、壁ジャンプも可能と、高性能なキャラといえます。
ステージの道中や拠点にあるショップでは「召喚」キャラを入手できます。一度使うとクールタイムが発生しますが、ボス戦などで頼れる大切なダメージソースです。
個人的なオススメは、初期に入手できる「おるやんけ」。初期状態では心もとない攻撃性能だが、ステージの道中や条件を満たすとどんどん強化され、後半には頼れる性能に。それぞれが「おるやんけ」とボイスを発するので、数が増えるほど見た目もサウンドも派手になっていく
序盤から解禁される「サブウェポン」は、ステージボスのホロメンを倒すと、彼女たちにちなんだものが手に入ります。性能としては、ホーミングするミサイルや敵の攻撃を防ぐシールドなど攻略に役立つものばかり。
サブウェポンもクールタイムが発生しますが、召喚と併せて積極的に使いたいシステムです。
ここからは、『ブレードキメラ』『DRAINUS』といった作品を開発してきたteam ladybugのメンバーであり、『FUBUKI』の開発者であるPEPOSOFT氏にインタビューします。
――本作の開発チーム体制について教えていただけますか。
開発の体制は以下の通りです。
(以下、敬称略)
【企画・プロデュース】大岡 ゆうき(カバー ホロアース ホロライブ・オルタナティブ プロデューサー)
【ディレクション、プログラム、グラフィック、サウンド】PEPOSOFT
【シナリオ】野村イクミ(公式冊子『HOLOEARTH CHRONICLES』の著者の一人)
【監修など】カバー、ホロライブ・オルタナティブ スタッフ
【パブリッシング】Phoenixx
【アイデア出し】PEPOSOFTを含む、ホロライブが好きなスタッフ全員(推しているホロメンがそれぞれ異なるため)
――開発に使ったゲームエンジンや、ドット絵の制作ツールなどを教えてください。
ゲームエンジンは、Unityをベースにしたオリジナルのエンジン「PE_ENGINE」です。ドット絵の制作は「CLIP STUDIO PAINT」、アニメーションの管理は「Aseprite」、作曲には「Studio One 5」を使っています。
「CLIP STUDIO PAINT」は、「EDGE2」のようにドット絵を制作しやすくカスタマイズしている
――「PE_ENGINE」について教えてください。
もともとClickteam製の「Click&Create」~「Clickteam Fusion 2.5(以下、CF2.5)」 を、趣味のフリーゲーム制作で20年近く使っていました。「命令・条件」のメソッド類や、エディタ周りが使いやすくまとまっていますし、プロトタイピングも即座に・気軽に行える、とても好きなソフトウェアでした。
CF2.5は、『Five Nights at Freddy’s』などの開発にも使われたソフトウェア
その使いやすさをUnity上で再現・拡張するため、自分なりにエディタ拡張や便利なクラス・メソッド類を揃えようと開発しているエンジンが「PE_ENGINE」です。性質としては、2Dプラットフォーマーを作りやすくしたものと言えます。
――Unityでとくに役立ったアセットなどはありますか?
インスペクターの拡張機能「Naughty Attributes」を使っています。インスペクターに表示する変数を、グループごとに折りたたんだり、メソッドをボタン化して簡単にテストできたりと、なにかと便利なアセットです。
(画像はUnity Asset Storeより引用)
本作の開発中に「Naughty Attributes」より高機能な「Odin」も購入しましたが、開発中に環境を変更するとどんな影響が起きるのかわからず怖かったので、『FUBUKI』本リリースまでは「Naughty Attributes」を使い続けました。
――そのほかに開発環境で工夫されたポイントはありますか?
ちょっとしたエディタ拡張ですが、色付きのHeaderアトリビュートを作って、インスペクターの視認性を向上したり、AudioClipのプレビュー・停止ボタンをインスペクター上に付けたりしました。Odinを導入した今となっては、Odinを使って縦長の画面を改良したいな、と思っています。
「画面中央に常時配置されるオブジェクト」をエディタ上に作っておいて、その場所からデバッグを開始する機能も作りました。シンプルな機能ですが、デバッグは相当な回数をこなすことになるので、開発効率の向上につながりました。
――多様なステージやギミック、敵を効率的に制作・実装するために、どのような工夫をされましたか?
一般的な話だと思いますが「敵・弾・移動床・トラップ」など作ったコンポーネントは、GameObjectにアタッチしてパラメータをいじって作っています。また、敵の挙動は個別にプログラムを組んでいます。
ドット絵のアニメーション管理は、ファイル名が連番になるようにドット絵を自動出力するツールを使っていました。しかし開発が進むうち、アニメーションの変更・調整が発生するときの作業が手間で、効率が落ちてしまいました。
そこで完成度80%程度の状態ではありましたが、「Aseprite」のネイティブファイルをUnityのプロジェクトに直接インポートできる「2D Aseprite Importer」を導入しました。アニメーションの速度やアニメーションごとに設定したタグなどもUnityに自動で読み込んでくれるので、かなり助けられました。
「2D Aseprite Importer」画面上部のツールバーは自作。ツールの切り替えを1クリックで実行でき、マクロ機能も備えている。
なお、一頭身のYAGOOは採用されるかどうか絶妙なラインだったそう。「チェックを通過してよかったけど、なぜ通ったのかもわからない」と、PEPOSOFT氏はコメント
――登場するホロライブのメンバーそれぞれの個性や「らしさ」を作品に落とし込むとき、どういった点を意識しましたか。
フブキさんの「かっこよさ・かわいらしさ」を体感できて、ホロライブの「かわいさ・楽しさ・賑やかさ・ネタ」を取り入れたい思いがありました。個性をしっかり表現して、配信時のメンバー同士のかけあいそのままじゃん!と思ってもらえるように注力しました。
――ドット絵やアニメーション、アクションに関して、具体的なお話を聞かせてください。
ホロライブの持つ「カラフル・鮮やかなかわいさ」と、ホロライブ・オルタナティブの持つ「スタイリッシュでかっこいい・かわいい」を兼ね備えた絵柄にまとめあげる意図を持って作りました。
主人公のフブキさんを例に挙げると、かわいらしさはもちろん「綺麗な白い長い髪に、ふわっとした耳」は再現しなければいけない特徴だと思います。
自分としてはこれらの特徴を、「白のグラデーションを段階をつけすぎず」、ふわふわ感は「つねに風でなびいているようなアニメーション」で表現してみました。
表情が平坦に見えてしまいがちで、目の色や顔の見せ方に苦心しました。試行錯誤し、目の水色がハッキリと見える大きさで、ほっぺは少し赤くすることで表情豊かになったと思います。
アニメーションに関しては、単体は良く作れたと思っていても、その前後のアクションによっては不自然に見えてしまう、かっこよさ・かわいさが足りないこともあり、そういったときはNGにしています。誰が操作しても「らしさ」が出るようにしています。
――PEPOSOFTさん個人として注目してほしい「らしさ」はどこでしょうか。
ボスのホロメンと戦うときの会話ですね。セリフは、ホロライブ公式冊子『HOLOEARTH CHRONICLES』の著者の一人である野村イクミさまに執筆していただきました。
ホロぐら(※)とか、配信中のノリとか、メンバー同士の賑やかな様子を再現したく思い、ボス戦は騒がしさを演出しています。
※ ホロライブの公式YouTubeチャンネルで公開されている3Dアニメシリーズ「ホロアニメ」の一つ
さらに、今回のためにボイスを新録していただいたおかげで、めちゃくちゃクオリティが高くなり、賑やかになったのもうれしいです!
ホロライブ・オルタナティブのティザーPVでフブキさんが印象的なシーンは、オープニングに起用するくらい気に入っているという(画像はSteamストアページより引用)
――本作はホロライブリスナーと、歯ごたえのあるアクションを求めるゲームファンの方々をターゲットにしているように思います。こうした異なる嗜好のプレイヤー層に満足してもらうため、難しさや操作系の設計などで重視したことはありますか。
以前、アニメ作品を原作とするゲームを作ったとき、普段ゲームをしない方がかなり多くプレイすることを実感しました。こうしたゲームは原作のないオリジナルのアクションゲームよりも、万人に満足してもらう気概で作る必要があるのだと気づきました。
そこで本作では、1ボタンでかっこいい・かわいいモーションが発生し、プレイスキルに関係なく楽しく遊んでいただけるようにしました。
加えて、受けるダメージ量の設定、落下防止機能なども実装しました。ホロライブが好きな方と言ってもプレイスキルは十人十色だと思うので、アクション初心者でも上級者でも、自由に遊んでもらえるように幅を持たせたオプションを設計しています。
ジャンプ周りの挙動も工夫しています。足を踏み外してから数フレームは2段ジャンプができますし、一度壁キックをしてもすぐに再度壁キックが可能です。できるだけ、頭で考えた通りに操作できるようになっています。
穴の落下判定はかなり下に設定していることもあり、落ちてしまったと思ってもボタン連打で復帰できます。
「危なかったけど助かった!」「かっこいいことした!」と、普段アクションが苦手な方でもピンチを脱した感覚を味わってもらえるかも……と思っています。
――挙動については、ほかにどのような点に注意しましたか。
立ち回りの自由度の高さを意識しています。フブキさんの攻撃は弾消し性能を備えているので、回転斬りやチャージショットも使いながら敵の懐にガンガン切り込んでいけますし、召喚やサブウェポンを使いこなせば有利に。
ダッシュは空中でも可能にしたことで、好き放題かっこよく操作できます。
自由度を高めすぎると腕前によっては歯ごたえがなくなってしまいますが、そのあたりのバランス調整は今でも難しいと思っています。
とにかく、操作中に起こるストレスは極力減らすようにしています。
――2月25日(火)に「Steam Nextフェス(※)」でデモ版を配信しましたが、プレイヤーからのフィードバックを製品版にどのように反映させましたか?具体的な調整例があればお聞かせください 。
※ Steam上で年3回開催されるイベントで、近日登場するゲームのデモ版などを特集している。参加できるのは1タイトルにつき1回のみ
テストプレイの時点で幅広いプレイスキルを持つ方々に初見プレイの動画を頂戴し、調整したうえでデモ版を配信しました。ですが、デモ版の実況プレイを配信している方の様子を見ていると、気になる箇所がいろいろと出てきまして、以下のようなアップデートを実施しました。
テストプレイでは見られなかった発見があったので、デモ版を配信して良かったと思っています。
そして、Steam Nextフェスに関わらず、Phoenixxさまの細かいフィードバック・QAが非常にありがたかったです。
――難易度の設定やその内容についてはいかがでしょう。
難易度はEASY / NORMAL / HARD / HELLを用意しました。EASYだとこちらの攻撃は高火力になって残機は20に増えつつも、敵の動きはそこそこ激しいままです。敵の挙動を遅くするといった調整をしてしまうと、自分のプレイスキルで勝った感覚を得られにくい気がしたので、そうしています。
NORMALは、初期状態だとかなり難しいです。各ステージに挑戦しているうちに、おるやんけや召喚アイテム、ゲーム内通貨の茶葉を収集でき、だんだん自身を強化して攻略しやすくなります。
遊び方としても、たとえば回復アイテムなどを使わずにNORMALをクリアできたら上の難易度に挑戦する、RTAをしてみるといったさまざまな遊び方ができるかと思います。
――「魔界のカジノ」ステージはゲーム内通貨「カジノコイン」の収集が可能な、特殊なステージです。この仕様にした理由を教えてください。
『ポケモン』内で遊べるスロットのようなもので、特別なアイテムを収集するための特殊な通貨を採用するのもアリなのかなと思っています。ジャラジャラとコインが手に入る感覚は気持ち良さがありますし。
しかし、ゲーム内通貨が2種類になるのはプレイヤーとしては収集が面倒になるのでは?とも思います。個人的には乗り気ではなかったのですが、紆余曲折あり実装に至りました。
また、本作リリース後の初期バージョンでは、カジノコインを稼ぐにはだいぶ周回しないとならず、バランスが崩れていました。あとで自分でもバランスの悪さには気づけましたが、リリースのための追い込みによりリリース直前までは目が届いておらず……。
これに関しては、アップデートで価格を修正しています。初期バージョンで収集された方、すみません……。
カジノコインを使ってギャンブルするミニゲームを入れようかと考えたこともありますが、開発時間が足りず実現はできませんでした(今後、実装するかもわかりません)。
――ミニゲーム『おるやんけげーむ』を導入したいきさつは?
いただいた企画のボリュームが少なめで、企画の流れとして僕がステージを追加することも難しかったです。また、1ステージを長くしてボリュームを確保しようとすると、プレイがダレてしまいます。
企画の大筋を変更せず、より強い満足感を体感してもらいたかった結果として実装しました。
とはいえまとまった時間は取れなかったので、スキマ時間で作れるものとしてこのような形になりました。『星のカービィ64』などの名作にもミニゲームがあるように、癒しの時間があるというか「メインが終わっちゃってやることない」とならず、『おるやんけげーむ』の存在によってゲームの完成度が上がった……ような気がしています。
――PEPOSOFTさんは本作のBGMも制作しています。そのなかで、とくに印象的な曲を教えてください。
オープニングステージの曲は、フブキさんのメインテーマの曲としても作っていて気に入っています。ホロライブ・オルタナティブのPVや漫画『ヤマト神想怪異譚』に登場するフブキさんをイメージし、かっこよく作りました。
本作の曲は全体的に一風変わった曲調で、ホロライブゲーマーズらしさを、ピコピコ音とホロライブ・オルタナティブらしさを和風の音などで表現・融合させるといったことをしています。
また、スーパーファミコン時代のような「これはゲームの曲だな」とすぐにわかるものにしています。当時を懐かしむような気持ちになっていただけるとうれしいですね。
あと個人的には、「凍りついたテーマパーク」のBGMがノリノリで好きです。
パブリッシングに関係する話は、Phoenixxの小田 響之氏にうかがいました。
――Phoenixxさんがパブリッシャーとして担当した業務範囲について教えてください。
まず基本として、Steam上でのリリース準備や設定、プロモーション全般、翻訳業務の取次などを担当しております。このなかには、Steamでのテキストでのお知らせなども含んでいます。
(画像は「『FUBUKI』アップデートのお知らせ」のスクリーンショット)
ホロライブIPの権利元であるカバーさまへの表現確認や使用許諾などの各種作業も、一通りの進行をいたしました。
本作のPVにホロライブ・オルタナティブの一部映像を使用するといった、弊社からの要望をお伝えすることも多々ありました。監修いただいた担当者さまにはこの場を借りて改めて感謝の意を表します。
インゲームでは、タレントさんのボイスはすべて撮りおろしさせていただいたのですが、台本のとりまとめからデータの授受、管理なども行わせていただきました。
――本作のマーケティングおよびプロモーション戦略についてお聞かせください。ターゲットとなるホロライブリスナーの方々と、2Dアクションゲームファン層、それぞれにどのようなアプローチを取りましたか?
ホロライブリスナーさんへのアピールを主軸にしつつ、そのアピールの中で本ゲームの画面を見た方が「おっ」と思うように心がけておりました。
ホロライブリスナーさん、とくに主役である白上フブキさんのリスナー「すこん部」の皆さまへは漏れなく届けることが第一と考え、初報は白上フブキさんの1stソロライブの日に合わせております。
実は本作の初報から発売まではそこまで時間をかけていません。イベントは「ここ!」と思うものに絞って出展しました。
オフラインでの出展は、ホロライブリスナーさん向けの「hololive SUPER EXPO 2025」とインディーゲームファンの方に向けた「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」の2つです。
(画像はPhoenixx公式サイトより引用)
2月には「Steam Nextフェス」があったため、体験版の用意とプロモーションの兼ね合いも良く併せての出展にいたしました。
ただ、「hololive SUPER EXPO 2025」と「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025」の開催期間が丸被りだったのは本当に大変でした。PEPOSOFTさん、カバーさま、弊社内スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
最終的には『FUBUKI』の発売日をインディーゲーム情報番組「INDIE Live Expo 2025.4.13」と同日に合わせ、初見の方が興味を持ったらすぐ購入できるように意識いたしました。
同番組では何度か『FUBUKI』のCMが流れた
――本作のような大規模なIPを活用したインディーゲーム特有の難しさはありますか?
弊社では元々「東方project」の二次創作タイトルのパブリッシュを多く行っていたこともあり、権利元さまへの監修や注意点への理解などへは少し自信がございました。
しかしながら、IP元がゲームかVTuberタレントさんかという違いは思ったよりも大きいときがあり、監修に当たっての留意点の違いなどは非常に勉強になりました。
プロモーション面では、「絶対に届けるべきユーザー」を見落とさないことに注力をしております。ただ、まったく関係がないわけではないですが、普段とは違う分野へのアプローチになるため、効果的な発信方法を探すにあたっては考えることが多かったです。
「普段ゲームをプレイしない方へ情報を届けた際、そのゲームが魅力的に映るかどうか」は大きな課題です。そうした方に興味を持ってもらえるかどうかにより、ポテンシャルが大きく変化すると感じます。とくにアクションゲームは取っつきにくく感じるユーザーもいらっしゃるため、どこまで間口を広く見せられるかが勝負でした。
――最後に、リリース後のアップデートによるコンテンツ追加、あるいは次の展開などを聞かせてください。
難易度の追加などを予定しております。Nintendo Switchもリリースできるとうれしいですね。
© 2016 COVER Corp. ©PEPOSOFT
Published by Phoenixx Inc.
大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。
ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。

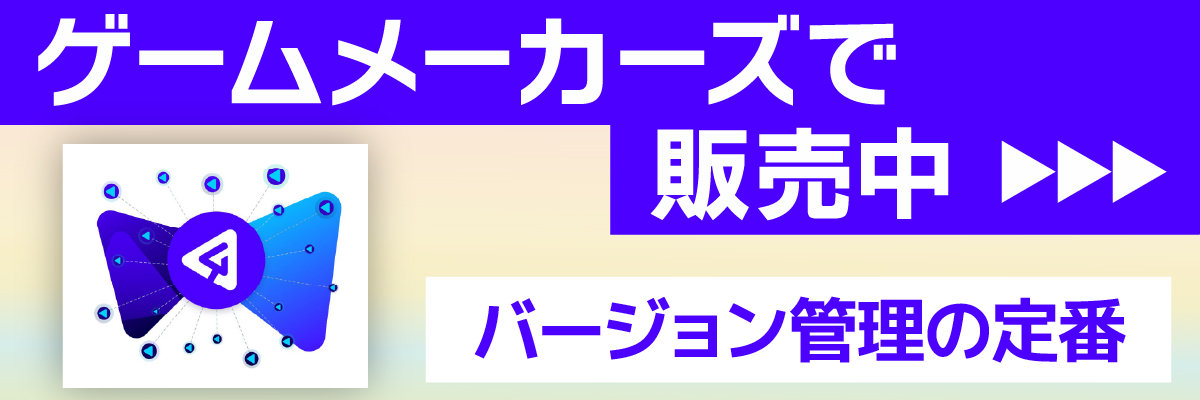

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。




