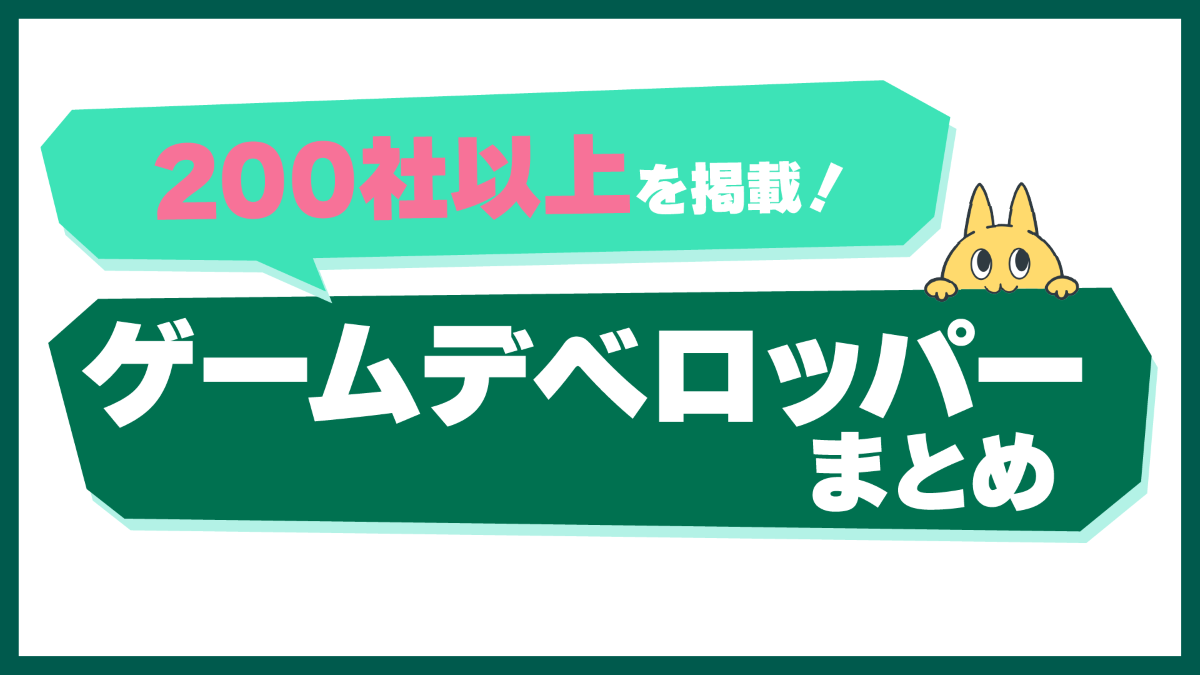2025年3月28日(金)、ゲーム開発者向けカンファレンス「GAME CREATORS CONFERENCE ’25」が開催されました。
本稿では、カプコン時代の同期である伊津野 英昭氏、神谷 英樹氏の両氏が長年にわたるディレクター経験をもとにパネルディスカッションを行った、「シン・ディレクター対談」の模様をダイジェストでお届けします。
2025年3月28日(金)、ゲーム開発者向けカンファレンス「GAME CREATORS CONFERENCE ’25」が開催されました。
本稿では、カプコン時代の同期である伊津野 英昭氏、神谷 英樹氏の両氏が長年にわたるディレクター経験をもとにパネルディスカッションを行った、「シン・ディレクター対談」の模様をダイジェストでお届けします。
TEXT / HiMiKo
EDIT / 酒井 理恵
神谷 英樹氏
クローバーズのスタジオヘッド/チーフ・ゲームデザイナー。『バイオハザード2』、『デビル メイ クライ』、『ビューティフル ジョー』、『大神』、『ベヨネッタ』シリーズなどを手がけたディレクターとして知られる。
今回パネルディスカッションが開かれるきっかけとなったのは、なんとお三方のプライベートな集まりだったとか。一緒に仕事をしていた仲間同士で話が盛り上がる中、「この場だけで話すのはもったいない」ということで、今回の講演へとつながったそう。
神谷氏は「デビル メイ クライ」シリーズの生みの親、伊津野氏は『デビル メイ クライ 2』以降のディレクター、松下氏は『デビル メイ クライ 3』のメインプログラマーと、登壇した3人は「デビル メイ クライ」シリーズに深い関わりがあります。その3人でまず話すテーマは「新作と続編」について。
伊津野氏は『デビル メイ クライ 2』の開発終盤から参画したということですが、『デビル メイ クライ 2』の際には不完全燃焼感を覚え、『デビル メイ クライ 3』はゼロから作りたいと会社に志願し、社内メンバー集めから始めたとのこと。原作へのリスペクトを持った続編づくりをする上で、生みの親である神谷氏とコミュニケーションが取れたのは幸せだったと振り返りました。
一方の神谷氏にとって、同シリーズの続編を手がけた伊津野氏は大変ありがたい存在だったとのこと。『デビル メイ クライ 2』では困難な状況を立て直し、『デビル メイ クライ 3』を立ち上げる際には開発に携わらない神谷氏にも助言を仰ぎにきたとして感謝を述べました。
また、続編は別作品にも影響を及ぼしてくれたとのことで、のちに神谷氏がプラチナゲームズで手がけた『ベヨネッタ』は、ほぼ同時期に開発された『デビル メイ クライ 4』のクオリティの高さに大いに刺激を受けたといいます。『ベヨネッタ』の開発スタッフと一緒に『デビルメイクライ 4』の試遊台もプレイしに出向いたとのことで、同作と張り合う気持ちが『ベヨネッタ』のクオリティを引き上げてくれた、と当時を振り返りました。
そもそも続編の制作には過去のシリーズ作の評判が影響するもの。ファンの期待を上回らなければならないプレッシャー、社内的な抵抗感など、続編ならではの壁にぶつかることがあるためかなり気を使うといいます。世の中に出た時点で作品は半分以上はユーザーのものになるため、ユーザーを意識しないわけにはいかないと神谷氏は語りました。
その上で、「神谷氏は続編のディレクターをやりたがらないという噂は本当か?」と話題を振られると、きっぱりと否定。いろいろな事情で手がけることができない場合もあるが、開発スタッフとは「続編ではこういうことをやりたいよね」と語り合うこともあったといいます。
伊津野氏は、『デビル メイ クライ 3』を制作するにあたっては、次作になったときにまっさらな状態で別のディレクターに渡せるようにしたいと考えていたとのこと。しかしながら、『デビル メイ クライ 4』のローンチは確実に成功させたいという要望があり、結果として3に続く4もディレクターを担当することになったそうです。基本的には制作中の作品をやりきるスタイルのため、作品を発表してから5年くらい経つと続編のアイデアが出やすいと語りました。
まず、自身がディレクターになったきっかけについて、伊津野氏と神谷氏がそれぞれ語りました。
伊津野氏は「運」だったと一言。当時のカプコンにはメインプランナーの役職の人間が全員ディレクターに昇格するようなタイミングがあり、伊津野氏はその波に上手く乗ることができたといいます。
一方、神谷氏は、ディレクター向きの気質が評価された面があるのではと振り返りました。神谷氏を次のディレクターにと推してくれたのは「バイオハザード」シリーズを手がけた三上 真司氏。『バイオハザード』制作時に積極的に意見を述べるなどしたエネルギッシュな姿勢が、三上氏からの評価につながったのではと語りました。
そんな神谷氏の発言に、伊津野氏は意見の多い人間に実際に決定権のあるディレクターをやらせてみると本当に舵取り役ができる人なのかどうかが見極められると話しました。それを受けて神谷氏も「『バイオハザード』について、三上ディレクターに発言した内容は今思い出すと軽々しかった」とした上で、「やんちゃで無責任な発言をできたのは、発言や決定事項に重みをもつディレクターになる前だったから」と語りました。
ディレクターに必要なのは何かという話題に伊津野氏は「チームメンバーのやりたいことをディレクターの意図する方向に誘導したり、考え直してもらったりする能力」であると表現。ただしやる気を無くさないよう本人が気づかないような形で行うのが重要とし、「気遣いとメンタルの強さ」が要るのではないかと結びました。
一方で、「神谷氏と伊津野氏が一緒にゲームを制作したらすごいものができるのでは」という意見をよく見かけるという神谷氏。ディレクターは“決める仕事”なので複数人いる体制では制作が難しくなると語ります。
それに対し「だからこそディレクターは他のディレクターを尊重する」と応じた伊津野氏。たとえば社内の別プロジェクトに関して問われた場合は、ワークフローやスケジュール管理について指摘することはあっても、ゲームの面白さに関わることは一切言わないようにしているとのこと。別プロジェクトのディレクターの「やりたいこと」を尊重し、決定に対して口を出さない重要性を述べました。
神谷氏は最近「やっぱりゲームは会社が作るものではなくて人間が作るものだ」と強く感じているそうで、ゲームに限らず、制作者の人間性や趣味などがにじみ出る作品が好きだといいます。そのため、自分の色を出せる人はディレクターに向いているのではと語りました。
また、自分の色を出すためには大量のインプットを日々行いながら、こういうアウトプットをしたいという思いを抱くことが重要とのこと。伊津野氏も「映画を観て期待外れだったときに、俺だったらこうするのにという思いを持つ。自分は“俺だったらこうする”の塊」と同意しました。
一方で、独自性の強い作品を手がけると、批判も集まりやすいのは事実。伊津野氏は「賛否どちらの意見を聞いても堪えられるのは資質として重要」と語りました。対する神谷氏も、SNSでは「シューティング要素がなんで入ってくるんだ、要らない」といった意見を毎回もらうが、自身のやりたいことを貫いているとしました。
両氏の共通した意見として、他のチームメンバーやユーザーの意見を聞きすぎると開発の継続は難しくなるので、“俺がやりたいんだから”と自分の意見を貫き通すハートの強さが必要と結論づけました。
続いてのテーマは、ディレクターの大先輩である両氏が失敗したことについて。
伊津野氏は基本的には、自分の下した判断に対し後悔はしていないとしながらも、入社10年目まではロジックではなく調整に頼りフィーリングで進めていたような部分があり、若い時にはたくさん失敗したとのこと。ロジックを使わない弊害として、当たり外れの幅が大きくなる、と話しました。
それを聞いた神谷氏は「それでも伊津野氏はまだ若いうちにちゃんとロジックに気づけている」と指摘し、神谷氏自身は『大神』『ベヨネッタ』の時にもフィーリングで進めてしまったと語りました。その後、プラチナゲームズに移り若いメンバーに「ピラー(※)とは……」と教育する段になってみて、当時の至らなさに気づいたといいます。
※ 「柱」の意味。ゲームを支える交換できない要素として、そのゲーム固有のシステムなどを指すことが多い。コンセプトとほぼ同義
そう反省する神谷氏ですが、「バイオハザード」シリーズに関連する神谷氏作成の資料は存在しており、伊津野氏によるとピラーや怖さの分析集なども含まれていたとか。しかしそれらについても「分かった気になったことをワープロで入力したい時期だっただけ」と話す神谷氏。『大神』も資料は存在するが、フォトリアルな自然地形にリアルな狼が走っているような内容で、“自然を味わいたい”ことを示した1枚の紙に過ぎなかったと評価しています。40代後半になってようやくピラーの重要性が飲み込めてきたと自身を批評していました。
ユーザーとの距離感について、伊津野氏は過去のディレクター経験から「ユーザーを試すようなことはあまりやらない方が良い」と考えているといいます。
それに対して「自分が作りたい、面白いと思っているものを作った結果、そうなってしまうこともある」と神谷氏。伊津野氏の話に関連して『ベヨネッタ 3』の経験を引き合いに出しました。
『ベヨネッタ 3』は『ベヨネッタ』を作ってから10年以上経って制作されたこともあって、ユーザーの中で熟成されたイメージが新しい制作物と乖離することがあったとのこと。セリフひとつを取っても「ベヨネッタはこんなことを言わない」などの反発にあいました。
「ユーザーが求めるもの」と「作り手のやりたいこと」「新作に新しい要素を加えたい意図」が乖離することは起こり得ます。ただし、ユーザーアンケートなどを通じてユーザーの要望通りに作っても面白くならないとも述べ、ユーザーのニーズとディレクターが考えるゲームの面白さとの間でバランスを取る難しさが語られました。
話は変わって、新しいゲームを作る上での発想はどこからくるのか、という話題に。
伊津野氏は先輩から「ゲームを見てゲームを作ったらあかん」と言われたことがあるといいます。ゲーム以外のものの面白さをヒントにゲームを作る、という所を出発点にすると良いと語りました。
一方、神谷氏は自身の着想の源泉について参考にしたものはいろいろあるとした上で、「新しいゲームを作る時にはなにか『呼び水』が欲しい」と述べました。
この「呼び水」とは、会社側の求めるビジョンです。たとえば『大神』を作る際に「クローバースタジオの立ち上げにふさわしい看板タイトルが欲しい」と言われたのだそう。『ビューティフル ジョー』では「ロックマン」シリーズのように、長く続けられるシリーズものを2Dゲームとして作ってほしいという要望があって発想を膨らませました。伊津野氏はこうした会社として求められるビジョンから売り上げを実現できるアイデアを発想できるのは天才だ、と神谷氏を褒めたたえました。
最後に、ディレクターとして「どんな人とチームを組むと仕事がやりやすいか」を問われたお二方。
伊津野氏は、ディレクターが作りたいゲームの「ピラーや理論」と「実現するための方法」の双方に意見を言ってくれるメンバーは組みやすいとのこと。ピラーについて意見を述べないよりは、「こういう考えもある」とピラーへの不満を冷静に述べられる方が、客観的な視点を取り入れられるので助かると語ります。
神谷氏は、自身は企画職出身で絵を描いたりプログラムを組んだりはできないため、スペシャリストに助けられて今までゲームを作ってこられたと回答。その上で「こういうことができるか?」と問われたときに「できない」と答えるだけではなく、「何を実現したくてこういうことがしたいのか?」を問い返して深掘りし、やりたいことをくみ取った上で、代替案を提示してくれると良いとのこと。「やりたいことにたどり着く方法論はひとつではないと思う」と語りました。
たとえば「100体の敵を出したい」と持ちかけて「100体は無理です」という回答ではそこで終わり。ところが、100体の敵を出して何をしたいのか?という点を深掘りすれば、「大勢の敵に囲まれている雰囲気を作りたい」という意図が引き出せます。最終的には「では大きい敵を10体出して囲めばそのように見えるのではないか?」「10体であれば出せますよ」とアイデアが解放されていき、クリエイティブにつながっていくので助かるとのこと。そういう人間はディレクターの意図をくみ取り、「どうしたらこのゲームが面白くなるか」を考えて一緒に悩んでくれるため、とても重宝する存在だといいます。
対する伊津野氏も「一緒に悩んでくれる人はいいね」と同意しました。神谷氏はさらに、一緒に悩んでくれて嬉しかった経験として、『バイオハザード 2』の背景制作の例を語りました。
当時の「バイオハザード」シリーズはプリレンダで背景を制作するため、背景制作が一番手間がかかるセクションだったとのこと。神谷氏が提示したマップ案とスケジュールは絶対にスケジュールに収まらなかったため、背景制作チームのリーダーはやりたいことをヒアリングし、「一緒にステージ数の削減案を考えよう」と言ってくれたそうです。最終的には演出上必要なステージばかりだったため削減にはつながらなかったものの、話をすべて聞いた上で相談に乗ってくれたのは嬉しかったと神谷氏は語りました。
神谷氏は『ビューティフル ジョー』の最終ステージを企画した際はスケジュールに余裕がなく、内容の甘いギミック案などの企画を出してしまったそう。すると、後輩のプログラマーに「面白くないですよ」とダメ出しをされ、ではどんな内容なら面白くなりそうか、という話で大いに盛り上がりました。しかし、いろいろなアイデアが出たところで「で、それ入るの?」と聞いたら「無理っすね」と返ってきてしまったとか。
伊津野氏も「盛り上がるだけ盛り上がって、実現は無理という時は確かにある」と同意。神谷氏は、「現実は現実なので、それは腹は立たない」とし、ただ何も言わずにプッシュバックをする人よりも、一緒に悩んでくれる人の方が「ゲームのことを考えてくれてる」感じがすると結びました。
その後につづくQ&Aでも活発なやりとりが行われた本セッション。神谷氏からの「ゲーム業界を目指している方々が、希望が叶って良い道に進めるよう願っています」という言葉とともに、参加者の温かい拍手で幕を閉じました。
シン・ディレクター対談 ‐ GAME CREATORS CONFERENCE '2540歳からCGの勉強を始めた元SE。BlenderとUEの勉強をスローペースで続けています。旅行先ではよく食い倒れています。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。