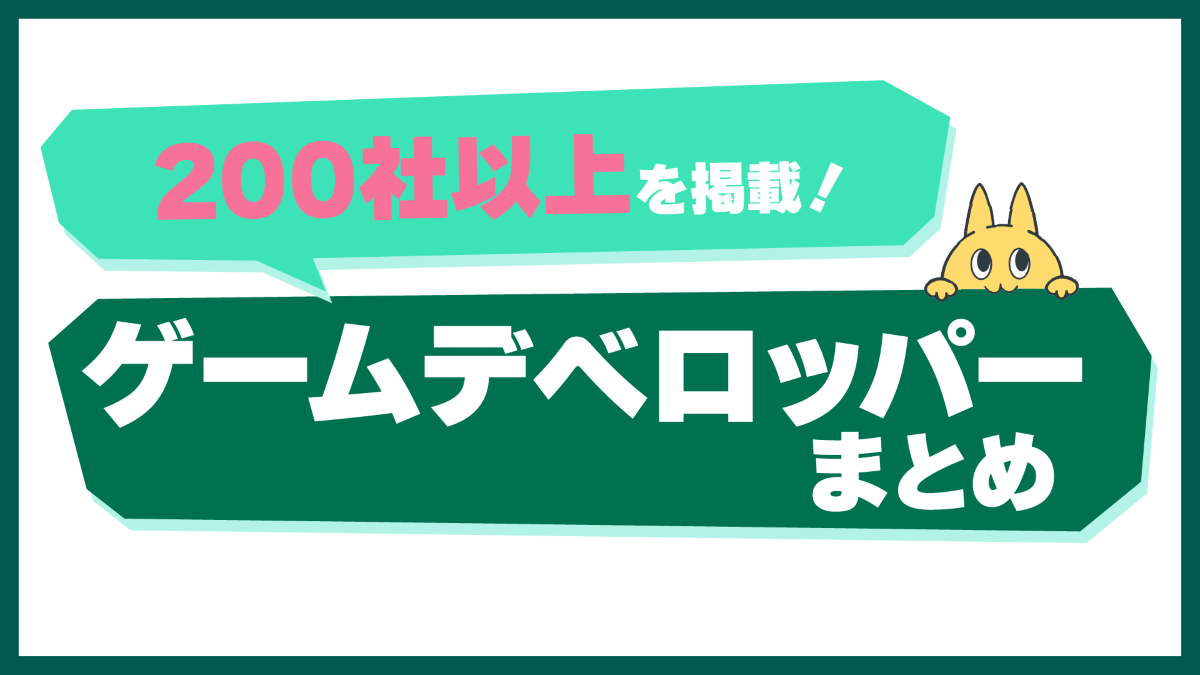2025年6月4日(水)、ゲームのプロデュースとマーケティングに特化したビジネスイベントである「GAME FUTURE SUMMIT 2025」が開催されました。
本稿では運営型ゲームにおけるコミュニティの重要性やアプローチ方法などについて、運営チームとコンテンツクリエイターという2つの目線から紹介された「広告を超える熱狂はこうつくる!逆転オセロニアとドズル社の共創コミュニティ論」をレポートします。
2025年6月4日(水)、ゲームのプロデュースとマーケティングに特化したビジネスイベントである「GAME FUTURE SUMMIT 2025」が開催されました。
本稿では運営型ゲームにおけるコミュニティの重要性やアプローチ方法などについて、運営チームとコンテンツクリエイターという2つの目線から紹介された「広告を超える熱狂はこうつくる!逆転オセロニアとドズル社の共創コミュニティ論」をレポートします。
TEXT / ハル飯田
EDIT / 酒井 理恵
本講演の登壇者はディー・エヌ・エーのスマートフォン向けゲーム『逆転オセロニア』プロデューサーの香城 卓氏、そして登録者数230万人超のグループYouTuber「ドズル社」のリーダーであり、代表取締役でもあるドズル氏。
進行はコミュニティ・SNSマーケティングを事業とするNAVICUSの代表取締役 武内 一矢氏です。
まずは武内氏が2025年1~4月の国内アプリゲーム市場における売上上位タイトルのランキングを紹介。TOP10のうち過半数がロングヒット作で、新規で“割って入るのが難しい”状況にあることに触れ、この市場で「なぜコミュニティ施策に力を入れているのか」がトークテーマに。
これに対して香城氏は、アプリゲーム市場を「ドーンと(ユーザーが)増えて、そこからの低減にどう耐えていくかという曲線」と表現し、その中でコミュニティやファン同士の繋がりがゲームを続けていくモチベーションになっていると解説。コミュニティは長期的な数字に効果があるものであるとの見方を示しました。
ドズル氏もゲームはそのプロダクトの面白さだけではなく「みんながどう楽しんでいるか」という界隈・コミュニティの雰囲気が大きな影響力を持つとコメント。動画投稿者として動画単体の面白さだけではなく雰囲気も重視されると実感しており、ゲームに限らずコミュニティの雰囲気がコンテンツに与える影響の大きさを感じているとのことでした。
ここで武内氏が「登録者数200万人を超える『ドズル社』もひとつの大きなコミュニティとも捉えられるのでは」と投げかけると、ドズル氏も「YouTubeというプラットフォーム自体が、すでに“動画屋さん”よりも“コミュニティ屋さん”に近い」と同意。
ドズル氏はYouTuberとしての活動開始から動画の撮影を“公開収録”という形で生放送したり、生放送で「企画のネタ会議」を行ったりと、一貫して「一緒に作る」を重要視していると明かし、現在もプレミア公開機能によって動画へのリアルタイムの反響が生まれる環境を作っているとのこと。
コンテンツにおいてコミュニティが持つ影響力は大きく、そのコミュニティをより良い大きなものにしていくためには「一緒に作る」こと、つまり「共創」が大きな意味を持つキーワードとなっています。
ファンとともに作り上げていく「共創マーケティング」施策の効果は大きいものの、マーケティングの立場から武内氏は「やりたいけど難しい」とコメントし、ここからは「共創マーケティング」のポイントをより深く探るテーマに。
これについてドズル氏は「ゴールを明確にすること」が要点であると言及。実際に生放送での企画会議では視聴者からのアイデアに痛烈にダメ出しをすることもある“ガチ”の姿勢を見せており、「ファンサービスでやっているんじゃなくて、本当にたくさんの人に楽しんでもらえるものを生み出すことがゴール」と、常に確認しながら取り組んでいるとのこと。
さらに香城氏は「プロセスの可視化」が強力な手法であることも紹介。『逆転オセロニア』ではユーザーがデザインしたキャラクターを実装するなど共創施策が取り入れられており、完成するまでの過程を動画として公開しています。武内氏も過程の透明化はユーザーに対しての「誠実さ」に繋がっていると、その魅力を再確認しました。
そして、共創を含むコミュニティ施策のもうひとつのハードルが「定量的な効果測定の困難さ」です。コミュニティへの受け入れられ方や施策の効果は、どのように測定されているのでしょうか。
ドズル氏は数値による「見える化」にも取り組む一方で、実はコメントなどのコミュニティから受ける直感的な「見えない部分」を感じることに力を入れていると証言。とにかくコメントやSNSなどに触れてインプット量を増やし、意思決定の回数を繰り返していくことで直感が磨かれていくと語りました。
香城氏からは実際に『逆転オセロニア』で行われているリアルイベントの効果測定法も紹介。イベントにおける「応募」「当選」「参加」の3段階でユーザーをIDなどでトラッキングして行動を分析しているとのことで、イベントに参加したユーザーが半年後や1年後にどのような変化を見せているかを計測すれば、「これくらいの効果があるなら費用をペイできている」と評価することも可能であると明かしました。
施策の効果については、ドズル氏も以前は自身のコンテンツに触れる人数からコアファンへと育っていく設計を持っていたものの、最近は決してその通りではないことにも気付いて発想を改めたとのこと。YouTubeショートで触れてくれる人にいきなりリアルイベント参加を期待するのは「ジャンクフードを食べたい人にディナーを提案するようなもの」であると例え、“イベント好き”な人たちの入り口に適した設計に見直しているそうです。
続いてのテーマは「コミュニティ施策を行う上でどう社内を説得しているのか?」について。武内氏も「やりたいけれど、予算の取り方が分からない」というケースに遭遇することが多いと明かし、なかなか知ることのできない興味深い話題に。
香城氏は「『逆転オセロニア』はリリース当初からコミュニティを使って事業運営していこうと決めていた」と明かし、事業部の中で「コミュニティチーム」があり予算も割り振られているという環境も紹介。その上で、まずは「『コミュニティ施策はマーケティング領域の中でも短期的に結果が出るものではない』と社内に知ってもらうことから始めるべき」とアドバイスしました。
経営者でもあるドズル氏も「これって意味あるの?と感じるものにお金を使うのは手が縮こまってしまう」と述べ、その中で判断軸がブレないよう「毎年の利益の50%は未来のワクワクに投資する」と自分の中に定めることで、意思決定ができるようにしていると、独特のルールを紹介しました。
両者の事例はともに「長期的に判断すること」と「あらかじめ組み込んでおくこと」という点で共通しており、コミュニティ施策には計画性と意思決定が求められることが伺える内容となりました。
最後のテーマは「コミュニティの変化」について。
香城氏は長年コミュニティにまつわる計測を続けてきた中で、この数年は特に「クローズド化、スモール化が進行している」と指摘。以前はSNSのタイムラインのような大きな潮流で意見のやり取りが行われてきたものの、近年はそれぞれのユーザーが居心地の良い小規模なグループやチャンネルで発信するようになっており、実感として「オープントラフィックの中でコミュニティを見ていくことがすごく難しくなっている」と述べました。
タイトルに関する新発表でもYouTubeのコメント機能よりも親しい間柄で通話しながら感想を共有するケースが増えていると傾向を分析。「意見や属性が区切られた中で楽しむ方が心地よくて、自分が求めるコンテンツの受け取り方として良い体験なのでは」とユーザーの心情に寄り添いつつも、運営側としては「今後どんどんトラッキングできなくなっていく」との見方を示しました
ただ、そうしたオンライン上でのトラッキングが困難になったとしてもリアルイベントでの対話を重ねていることで「業務に対してユーザーの意見が分からなくなる感覚は全くない」とも断言。ユーザーと直接コミュニケーションする人間が運営の中にたくさんいて意思決定に携わっていれば今後も崩れずに続けていけるのではと語りました。
ドズル氏も「リアルイベントっていうだけでみんなすごく価値を感じていた」というコロナ禍が明けの時期を経て、近年のコミュニティの変化を実感。自身や周囲のイベントの内容から、今後は「デジタルのコンテンツや世界観の面白さがリアルに飛び出してきたようなイベントに価値が見出される」と、ヒントを見つけていました。
続けてドズル氏は、変化していくコミュニティに対して「コントロールしようと思うのではなく、泥臭く誠実に向きあうことが一番の近道」と強調。香城氏もそれに力強く同意し、運営型ゲームにおいては「コミュニケーション能力やチャームさのような、ヒューマンスキルの重要さが増してくるのでは」との展望も示しました。
ファン・ユーザーによって作り出され、コンテンツに大きな影響をもたらす「コミュニティ」に対してさまざまな考え方やヒントが共有された本セッション。
最後には武内氏が「出来レースではなく関わりを持って共創していく中で大事な価値が生まれていく。それが長期的にはタイトルのKPIにも寄与していくため、長期の計画を立ててまとまったリソースや予算を投資して意思決定していけば上手くいきやすくなるのでは」と総括し、ゲームプロデューサーとYouTuberによる貴重な講演を終えました。
『逆転オセロニア』公式サイト「ドズル社」公式サイト「NAVICUS」公式サイト「GAME FUTURE SUMMIT 2025」公式サイト大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。
ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。