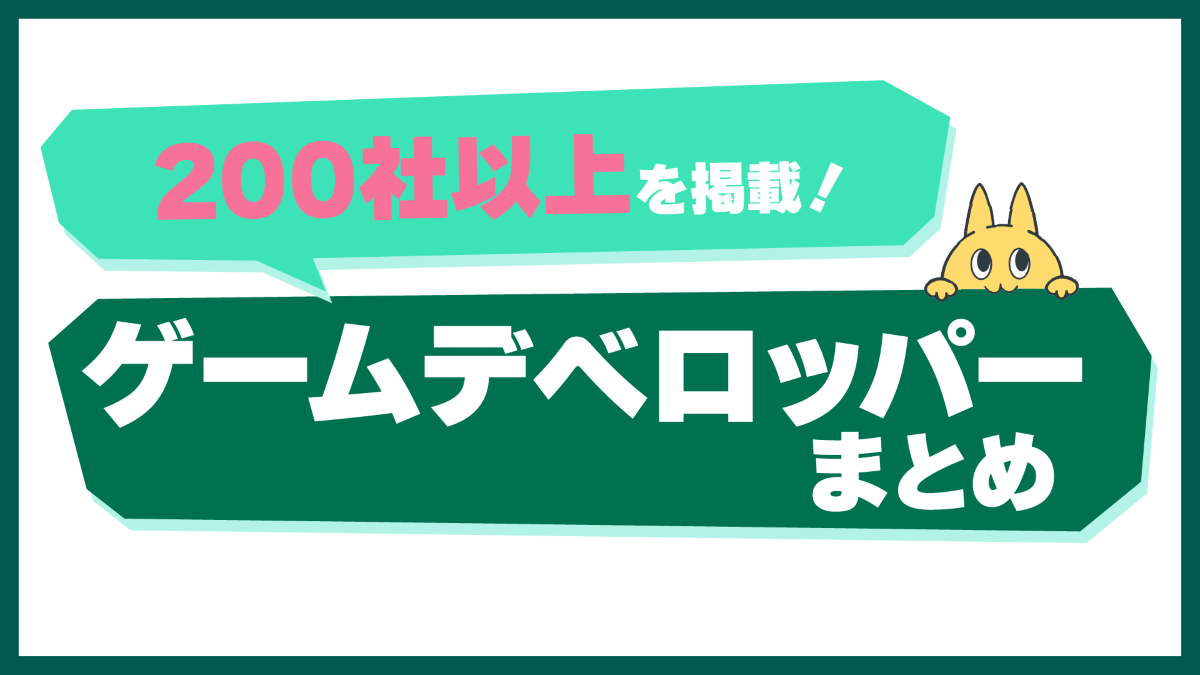「8番ライク」というフォロワー作品が多数生まれるほどの大ヒット作となった『8番出口』。その続編の『8番のりば』は、新たなゲーム性や演出がさらなる話題を呼んでいます。
走行中の電車内で発生するさまざまな「異変」を乗り越え、目的地へと辿り着く本作はどのような開発過程から生まれたのか。フォトリアルなビジュアルや前作から大きく変更のあったゲームシステム、アイデアの源泉などさまざまな疑問を開発者のKOTAKE CREATE氏にインタビューしました。
「8番ライク」というフォロワー作品が多数生まれるほどの大ヒット作となった『8番出口』。その続編の『8番のりば』は、新たなゲーム性や演出がさらなる話題を呼んでいます。
走行中の電車内で発生するさまざまな「異変」を乗り越え、目的地へと辿り着く本作はどのような開発過程から生まれたのか。フォトリアルなビジュアルや前作から大きく変更のあったゲームシステム、アイデアの源泉などさまざまな疑問を開発者のKOTAKE CREATE氏にインタビューしました。
TEXT / ハル飯田
INTERVIEW / 神山 大輝、神谷 優斗
EDIT / 酒井 理恵
本インタビューは『8番のりば』のネタバレを含みます。なお、本文中に使用している画像は実際のゲームとは一部異なる部分があります。ご注意ください。
──自己紹介をお願いいたします。
コタケクリエイトと申します。現在は『8番のりば』の開発を終え、新作『STRANGE SHADOW』の開発に専念しています。
──前回のインタビューでは『8番出口』のヒットを機に、アーティストとして働いていたゲーム会社から独立された直後でした。半年近い個人開発者生活の感想はいかがですか。
個人開発を始めたのは、自分の作りたいものを作りたかったからなので、今は自分の好みを通せる楽しさがあります。長い時は一日中開発の作業をしますし、気が乗らない時は3時間くらいで終わってしまう日もあります。午前中の方が捗ると感じていて、「お昼ご飯までにこれを終わらせよう」と短い時間制限を付けるのが良いですね。
──改めて『8番のりば』の開発について聞いていきたいと思いますが、まずはコタケさんご自身でゲームの概要を説明いただけますか?
永遠に走り続ける電車から脱出するゲームです。なんと説明するのが良いのかジャンル名は自分でも分からなくて……「ウォーキングシミュレーター+謎解き+ホラーゲーム」といったところでしょうか。
本作は5月にリリースすると事前に予告をしており、5月31日に発売開始しました。月内ギリギリにはなりましたが、突然リリースした方がバズるのではないかと思い、大きな告知などは行いませんでした。
──開発環境はどのようなものだったのでしょうか。
『8番出口』の時と変わらずアンリアルエンジンを使用していて、バージョンはUE5.2.1です。DCCツールは変わらず、MayaとSubstance Designer、Photoshopを使っており、プラグインは「UI Navigation 3.0」を引き続き使用しました。
──短期間での続編リリースとなりましたが、前作リリース後すぐに着手されたのでしょうか。企画・アートなど、どこから開発に着手したかも教えてください。
1か月くらい休憩していたので、開発スタートは2024年1月の頭頃でした。実際の開発期間は約5ヶ月です。
僕は企画書を書くよりも、頭の中でシステムを考えて、それを試しに作ってみるスタイルで開発しています。初期のプロトタイプは「異変がない車両では座り、異変がある車両では座ってはいけない」というシステムでした。これが3月初旬には完成していたと思います。
「椅子に座ると寝てしまい、目が覚めると目の前におじさんが立っている」というものや「ガラスにだけ人が映っている」といった異変を考えており、異変を8種類ほど入れた状態で身近な人にテストプレイも行なってもらいましたが、最終的にはすべて破棄してしまいました。
──プロトタイプのゲームシステムを採用しなかったのはどのような理由だったのでしょうか。
制作中から「作りたいものとは何か違うな」と薄々感じながら作業していました。電車の車両となると、異変を探すためにチェックしなければならない箇所が多過ぎるんですよね。
異変探しに目新しさがなくなっている中で、類似するシステムを採用しなくてもいいかなと感じましたし、完全に別のシステムで作った方が自分が楽しいという理由もありました。
こういった背景に加えて、とある“8番ライク”な作品とシステムが被ってしまっていたのを知って、完全にやめることにしました。
プロトタイプ段階で動画を残していたのは「いつそのアイデアを思いついたのか」の記録のためでもあった
──プロトタイプをどの程度作りこむかは人によって異なる部分かと思いますが、映像を見るとかなり作りこまれていますね。
電車を舞台にやることは決めていましたし、いいシステムを思いつくのを待っている時間で車両のモデルを作っていたのもあって、プロトタイプでも完成に近い状態になっていました。
システムとアートのどちらかの作業が疲れたらどちらかをやって、みたいな感じです。「片方ができないときは別の作業をすればいい」という自由なスケジュールが組めることも個人開発の良いところですね。
──プロトタイプから違和感を覚えていたとのことですが、『8番出口』の続編として開発するにあたって踏襲した部分と変えた部分について理由を教えてください。
異変は残そうと考えていましたが、『8番出口』のようなシステムで、『8番出口』とは違う物でありつつ、自分が納得するものとなると作るのが難しいなと、プロトタイプ作成中にも思っていたんですよね。システムを変えることに反対意見があるのは想定していましたが、おじさんやループっぽい仕組み、そして「進むたびに数字が大きくなる」などの要素は残しつつ、まったく違う作品にしようと思ったんです。すべてを説明はできないんですが、基本的には「自分が作っていて楽しいから変えた」部分が大きいですね。
以前から異変を「探す」のではなく「対処していく」アイデアもありかなとは考えていました。『8番出口』でもあった「ゲームオーバーになる異変」の割合を増やしたらどうなるだろう、と考え、今度は異変から「引き返す」のではなく「向かっていく」システムに変更したんです。
『8番出口』が引き返せるゲームだったので、引き返せないことによる面白さや、今回はどのようなルールなのか考える楽しさもあるのかなと思いました。
──前回のインタビューで『8番出口』のアイデアは『I’m on Observation Duty』が元になっているというお話もありましたが、『8番のりば』については影響を受けた作品はありますか?
各ステージで違う課題をこなしていくシステムは『スプラトゥーン3 エキスパンション・パス サイド・オーダー』の影響があったかなと思います。あと、作っている最中はまったく意識していなかったんですが『Subway Midnight』はかなり近いシステムだなとリリース後に気付きました。意識していなかったと言えば、ユーザーから「『メイド イン ワリオ』っぽい」と言われていて、これには全然気付かなかったです。
──他にも予想外だったユーザーからの反応はありましたか?
「思ったより怖がられたな」という印象です。個人的には『8番出口』よりちょっと怖いかなくらいの感覚だったんですが、それ以上の反響でした。
──怖さを調整する上で、基準や目指すラインといったものはあったのでしょうか。
「ちょうど良い怖さ」を目指していましたが、結構なんとなくで調整していたので(基準が)分からなくなっていたのかなとは思います。自分の中では『バイオハザード4』や『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』がちょうど良い怖さのラインと感じる作品ですかね。
──異変から「逃げる」という選択がとれなくなったことで結果的に怖いと感じる方が増えたのかも知れません。
確かにそれもありそうですね。僕自身本当に怖いゲームはプレイできないタイプなので、ゾンビ慣れしてない頃に『バイオハザード2』をプレイして後悔しました。グロいのもダメなので『8番のりば』にもそうした表現は入れていません。怖さのなかでも「嫌だけどちょっと遭遇してみたい」くらいの、マイナスにならないような体験が個人的な“ちょうど良い”ラインなのかなと思います。
──ゾンビが苦手というのは意外な情報でした。逆に好きなホラー作品があれば教えてください。
『ヴィジット(※)』など“人間が怖い”系のホラー映画は好きですね。あとループものとしては『ハッピー・デス・デイ』という主人公が誕生日に何度も殺されては朝に戻るというホラー映画が面白かったです。これはグロいシーンもあるんですが許容範囲内でした。
※ 休暇を利用して祖父母のもとを訪れた姉弟が恐怖の体験をする映画作品。脚本・監督は『シックス・センス』のM・ナイト・シャマラン
──先ほど、ゲームは最初にシステムを作るとお話されましたが、ゲームのコンセプトは最初にしっかり言語化するタイプなのでしょうか。
僕は「自分が体験したいこと」をベースに作品を作っているので、実装が先にあります。作りながら「ちょっとブレてきたな」と感じたら、一度しっかりコンセプトを考えてみることが多いですね。たとえば『STRANGE SHADOW』なら「不気味な巨大生物を作りたい」という気持ちがありました。その巨大生物の怖さを活用するゲームなら、(倒すよりも)逃げたり隠れたりするのが良いんじゃないかな、という流れで方向性を決めました。
ただ、『8番』シリーズはそこまでブレて立ち返ることはなかったですね。『出口』は「地下通路が無限ループする体験がしたい」という気持ちからでしたし、『のりば』は「電車がいつまでも目的地に着かなかったら怖くて楽しそう」という発想がスタート地点でした。
──「自分がしたい体験」がベースというのは変わらず共通している部分なんですね。
電車の中で目が覚めてゲームが始まり、ゲームオーバーになってもまた電車で目が覚める……という「いつまでも夢の中」みたいな演出がしたかったんですよね。
──シナリオ的な設定はあるのでしょうか?例えば「主人公が『8番出口』と同じ」だとか。
そういうのは特に無いのですが「日常生活を送っていて突然迷いこんでしまう空間」のような設定で作っていました。『8番出口』の前日譚とも言われていますが、設定的には『8番出口』から迷い込んでしまうこともありえると思っています。
『8番出口』も『8番のりば』も主人公はプレイヤー自身という気持ちで作っているので、ある意味同じですね。
──ここからは実装について詳しく聞いていきたいと思います。まず最初にアセットについてですが、今回使用したアセットはすべて自作になるのでしょうか。
電車の3Dモデルは、ほぼ全て自作になります。日本っぽい電車のアセットを購入してはいたんですが、ゲーム用ではなかったのと、自分の作りたい電車とは大きく違っていたので結局自分で作ることになりました。アセットを利用したのは主にキャラクターで、例えば満員電車のような異変でブルブル震えている大量の人物は「Twinmotion ポーズをとった人ウィンターパック1」のアセットを使用しています。あの演出はマテリアル側でテクスチャを歪ませ、各頂点を素早く動かすことで実装しています。
アセットという意味では、車内広告も募集で集まったものですね。
──ゲーム内で使用する広告にはかなりの数の応募があったのではないかと思いますが、選定基準はどのようなものだったのでしょうか。
「実際の電車にありそうなもの」か、パッと見て「こういう異変が作りやすそうだな」と感じたものですね。例えば、目が大きく描かれているZONEの広告は「これは使えるな」とすぐに思いました。広告は全部で250くらいの応募がありましたね。
──納得できる明確な基準ですね。広告と人型モデル以外は基本的に自作のアセットということですが、総数は『8番出口』から増えていますよね?
地下通路がほとんど壁と天井と床だけで表現できて簡単だったというのもありますが、電車はアセットが多かったので2倍以上のアセット数になっています。
最も工数が重かったのは電車、続いて「九々杜(くくど)駅」の異変でした。あとは改札周りのシーンも、モデリングには時間が掛かりました。
──異変に「向かっていく」ゲーム性になったことで、ブループリントも必要数はかなり多くなったのではないでしょうか
そうですね。ただ戻れば良かった『8番出口』と違ってゲームオーバーになる処理も増えていますし、異変ごとに動きが違うこともあって3~4倍の規模になったと思います。
負荷の面ではC++で実装した方が良い部分もあるかとは思いますが、PCゲームならブループリントで問題ないと考え、今回も全編ブループリントで実装しています。
──電車の揺れ感のリアルな再現も印象的でした。「電車が走っている」ように見せる工夫があれば教えてください。
走っているように感じられる一番の要因は、窓の外の景色が流れていくことじゃないかと思います。つり革や広告が少し揺れていたり、ほんの僅かなカメラシェイクが入ったりという工夫もありますね。あとこれはギリギリで追加した要素なんですが、本物の電車と同じように、今いる車両から隣の車両を見ると、車両が揺れて見えるようにしています。
窓の外の景色は、マテリアルでテクスチャをスクロールすることで実装しています。実際の景色でもブラーがかかって見えるので、テクスチャサイズは256×256ピクセルで事足りました。現実では細かく電灯がついているかと思いますが、あまり良い感じの見た目にすることができなかったので妥協しました。
──つり革や広告の揺れはどうやって表現しているのでしょうか。
つり革などを1個1個揺らすとCPU負荷が高くなるので、マテリアル側で揺らしています。つり革の揺れが大きくなる異変もパラメータを変えたマテリアルで表現しました。UEのInstanced Static Meshを用いることで揺れをランダム化できたこともリアルな揺れを感じる要因になっていると思います。
──このリアルさを出すために、実際に取材するなどリファレンスとしたものはありますか。
モデルとなる電車は実際に写真を撮りに行っていて、細かい演出に活かしました。逆に、優先座席はあえて現実と同じようには再現しませんでした。一部だけ優先座席にするより全部同じ座席の方が作りやすかったですし、「異常な電車」だから現実を完全再現しなくても良いかなと。
──窓や金属面の反射もかなりリアルですよね。
金属面はUEの標準機能「Lumen」の反射を使っていますが、窓の反射は大変でした。窓の外を見せたいので、窓ガラスは半透明にしたかったんですが、Lumenが半透明の反射がうまく表現する方法が分からず、負荷も高そうでした。このため、1個1個の窓ごとにキューブマップを事前に作成して、反射っぽく見えるようにマテリアルを設定していく力技でやりました。
──個別にキューブマップを設定するのは大変な作業ですが、だからこそ反射がきれいに見えるんですね。
本当は向かいあっている窓同士は共通のものを使いたかったんですけど、変に歪んでしまうので断念しました。事前にキューブマップを作成しているため、車内におじさんがいない異変でも窓にだけおじさんが映り込むことがありますが、そこは割り切っていますね。同様に異変も映り込んでいません。
──たしかに、窓に映っていない方が「異変」らしくて良いかもしれません。走行音なども実際に収録したものですか?
ドアを開ける音は自分で録音したものですね。
走行音も録音はしてみたんですが、アナウンスが入って上手くいかなかったので、ネットで拾った素材を使うことにしました。
サウンド関連では、今作はHIKAKINさんの声を素材として使わせていただいています。「助けてください」とドア越しに呼び掛けてくる異変では、音声が少しこもって聞こえるように加工したり、ゲーム開始時のアナウンスもそれらしく聞こえるように音質を加工したりしています。使用したのは「Audacity」というフリーソフトですね。
──処理負荷軽減のための工夫がいくつもありますが、サイズが大きな車両をループして出現させる仕組みではどうやって処理を軽くしているのでしょうか。
最初に車両共通のブループリントを3つ配置して、それを移動させる実装を行なっています。プレイヤーは3両あるうちの真ん中からスタートします。後ろの車両には戻れないので、必ず次の車両に移動することになりますが、ドアを開けて移動するタイミングで「後ろの車両」が一番先頭に回ってきて「次の車両」になるんです。なので3両をぐるぐる回していて、プレイヤーが必ず真ん中の車両にいるようになるイメージですね。
──プレイヤー目線だと何両も連なっているように感じますが、実際は3両を上手く使い回していたと。都度ロードしているわけではないので、処理負荷も少ないんですね。
そうです。これは『8番出口』の時から使っている手法で、2つの通路を移動させながら、無限に続いているように見せていました。
──異変の数や発生の順番はどう決めていたのでしょうか。
異変は『8番出口』と同じく31種類で、車両を進むごとにどんどん異変の発生率が高くなっていて、特にゲームオーバーになる異変は後半になると優先的に出るようにしていました。
──異変の抽選処理についてもう少し詳しく教えていただけますか。
分かりやすい呼び方をすると、ゲームオーバーになる異変を集めた「ゲームオーバーリスト」と全ての異変が入っている「全てのリスト」が分かれていて、後半で優先的に「ゲームオーバーリスト」を抽選するタイミングがあります。一度出現した異変はどちらのリストからも外れて、ゲームクリアするまでは出現しないようになっています。
『8番出口』では異変が出現するかしないかはランダムで、3回「異変がない」状態が続くと次は必ず異変が起こるようになっていましたが、『8番のりば』では駅を進むごとに出現率が上がり、最終的には100%異変が発生するようになっています。
──異変と言えば、例の「おじさん」は同じMetaHumanモデルでしょうか。今回はいろいろな動きをしていましたが、その動きの作り方についても聞かせてください。
おじさんは同じモデルで、異変時のモーションはアセットを使っています。ただ、座ってスマホを見ているポージングは無かったので自作しました。写真を撮ってくるおじさんのポーズを作って、アニメーションブループリントの「Look At」で指定した位置を向くように制御しています。
──おじさん再登場にはファンからの喜びの声も多かったですね。実装を断念した異変はありますか?
せっかく電車が舞台なので「席を譲る」ことに絡めた異変を入れたかったんですが、思いつきませんでした。また、最初のプロトタイプで考えていた「目が覚めたら目の前におじさん」という演出も、現実の電車でありそうな異変なので入れたかったんですが、システムを変えてしまったため実現しませんでした。
──異変の難易度調整についての工夫やポイントはありますか。
ゲームオーバーになる異変だけではプレイヤーが疲れてしまうと思ったので、いくつか「ただ待つだけ」「通るだけ」のような怖くても休憩になる異変や謎解きを入れています。
『8番のりば』では、扉上部にある電光掲示板に異変への対処方法が書かれていることがありますが、物によっては異変の発生箇所を電光掲示板に近づけることで、自然とヒントが目に入りやすいような工夫をしています。
見てはいけない異変や近づいてくる異変は少し難しいと思いますが、「電光掲示板を見なくても対処法が連想できなくもないライン」を心がけて作りました。
──異変の難易度やジャンルは、どのように管理していたのでしょうか。
異変の数はスプレッドシートで管理していました。対処法でジャンル分けしており、「全部で31個だから1/3くらいはゲームオーバーになって良いかな」などとバランスを考えながら作っていました。このスプレッドシートを見ると「通るだけ」カテゴリの異変が一番多いですね。没になったアイデアも残っています。
──一番気に入っている異変はどれですか。
個人的には九々杜駅ですかね。わざわざ駅を作る手間がかかったというのもありますが、電車ネタをやるなら有名な都市伝説の「きさらぎ駅」っぽい異変は入れたいなと思っていました。でも、せっかくなのでオリジナルの「九々杜駅」を作りました。
──九々杜駅で降りてしまうともう戻れないんですよね。
戻れないですね。ゲーム終了するしかないです。「一生帰れない駅」みたいなのを作りたかったんですが、セーブデータ破壊までやってしまうと流石にやり過ぎかなと思ったので今の形になりました。また、九々杜駅で降りた時点ではセーブデータの削除ができないようになっています。脱出しようとしてセーブデータを削除すると出会った異変の記録も消えてしまい、最初からやり直しになってしまうので。
──開発のさまざまな工夫や考え方のポイントが聞けて、非常に興味深いインタビューとなりました。最後に、今後の『8番』シリーズの展望や展開があれば教えてください。
いろいろあるといえばあるんですが……まだ言えないですね。先日ふと「もう1個くらいできそうだな」と思うアイデアもあったんですが、実装面で可能かも検証していないですし『STRANGE SHADOW』も作りたいので、ゲームとしては『8番のりば』で終わりかなと思っています。ただ、数年後には気が変わって開発する可能性はあるかもしれないですね。
一方で、僕はリミナルスペース系が好きなので、そういった『8番』シリーズとはまったく関係ないものを作るかもしれないです。しばらくは『STRANGE SHADOW』に注力して、2025年か2026年の発売を目指して開発を進めていきます。
『8番のりば』ストアページ『STRANGE SHADOW』ストアページKOTAKE CREATEさん X大阪生まれ大阪育ちのフリーライター。イベントやeスポーツシーンを取材したり懐ゲー回顧記事をコソコソ作ったり、時には大会にキャスターとして出演したりと、ゲーム周りで幅広く活動中。
ゲームとスポーツ観戦を趣味に、日々ゲームをクリアしては「このゲームの何が自分に刺さったんだろう」と考察してはニヤニヤしている。



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。