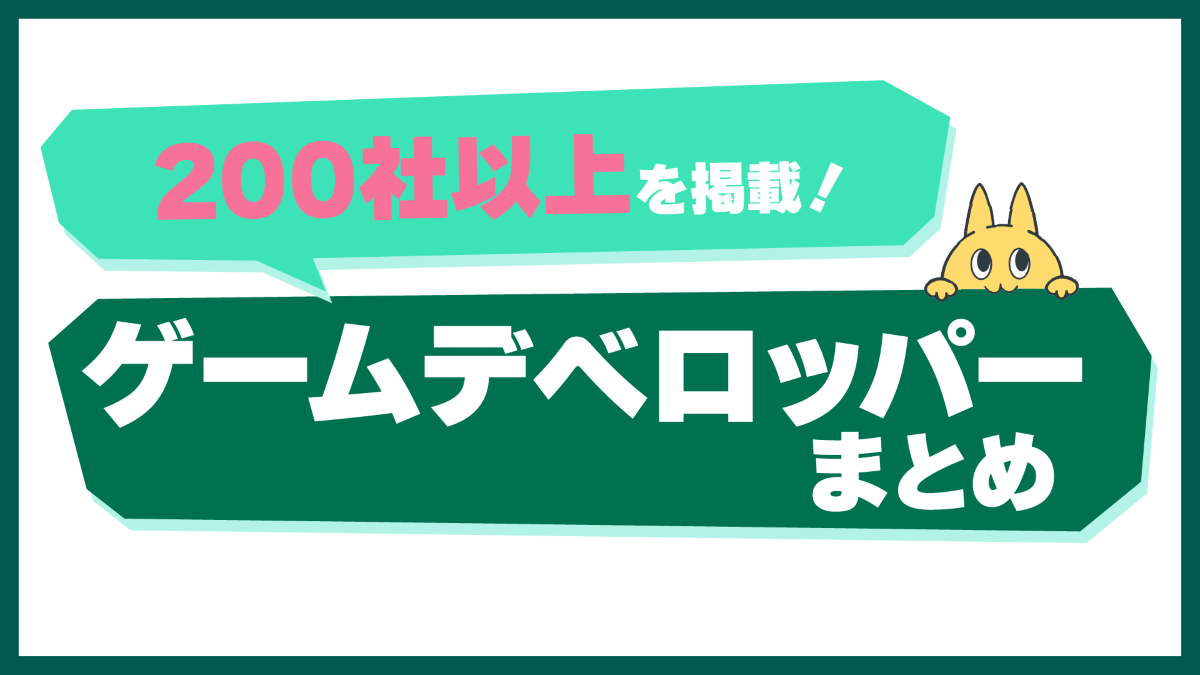2025年9月25日(木)から28日(日)の4日間、幕張メッセで開催された『東京ゲームショウ2025』。Ukiyo Studiosブースでは、Iron Gateによる北欧神話サバイバルゲーム『Valheim』が展示されていました。
今回、同作品の開発者であるクリエイティブリード兼アートディレクターRobin Eyre氏ら3名に、小規模チームで1,200万本のヒット作を生み出した開発の背景について幅広くお話を伺いました。
2025年9月25日(木)から28日(日)の4日間、幕張メッセで開催された『東京ゲームショウ2025』。Ukiyo Studiosブースでは、Iron Gateによる北欧神話サバイバルゲーム『Valheim』が展示されていました。
今回、同作品の開発者であるクリエイティブリード兼アートディレクターRobin Eyre氏ら3名に、小規模チームで1,200万本のヒット作を生み出した開発の背景について幅広くお話を伺いました。
TEXT / 神谷 優斗
『Valheim』は、スウェーデンのIron Gateが開発した、北欧神話をモチーフとするオープンワールド型サバイバルゲームです。2021年2月2日にSteam早期アクセス版としてリリースされると、開発チームの予想をはるかに超える反響を呼び、1,200万本以上を売り上げる大ヒット作となりました。
『Valheim』リリーストレーラー
プレイヤーは「Valheim」と呼ばれる世界に裸一貫の状態で降り立ちます。森で木を切り、石を採掘し、拠点を建設。段階的に装備を強化し、新たなバイオームを開拓していくことで、最終的に「見捨てられしもの」と呼ばれるボスを倒すことを目指します。
「草原」「黒い森」「沼」「雪山」など多彩なバイオームが用意されており、各エリアには固有の敵、素材、ダンジョン、ボスが存在します。新たな素材を発見することでクラフト可能なアイテムが一気に増えるため、探索には常に発見の喜びが伴います。
さらに最大10人でのマルチプレイにも対応しており、世界中で大きなコミュニティが形成されています。協力して拠点建築やボス討伐に挑戦する楽しさも本作の大きな魅力となっています。
現在実装されているバイオームは8つで、最後のバイオーム「Deep North(極北)」の開発が進行中。「Deep North」の完成をもって、正式リリースとなる予定です。
ゲームエンジンにはUnityを使用しています。最適化とローポリゴンのアートスタイルにより、容量1GBという軽量化を実現しています。
『Valheim』公式サイト今回は、Iron Gateのクリエイティブリード兼アートディレクターのRobin Eyre氏、コミュニティマネージャーのJosefin Berntsson氏、3DアーティストのLisa Tveit Holfjord氏の3名にインタビューを行いました。
左からLisa氏、Josefin氏、Robin氏。右は『Valheim』ブースのコスプレイヤー ぐり粉氏
――皆さんの経歴とIron Gateでの役割について教えてください。
Robin:Robin Eyreと申します。Iron Gateの最初の社員であり、現在はアートディレクター兼クリエイティブリードとして、『Valheim』の世界観やキャラクターなど、ビジュアル面全般を統括しています。
Josefin:Josefin Berntssonです。コミュニティマネージャーとして、アーリーアクセス開始から1〜2ヶ月後にジョインしました。プレイヤーからの反響の大きさで当初コミュニティマネージャーを担当していたLisaの手が回らなくなったため、サポートとして入りました。現在はコミュニティ全般に加え、ゲーム内のシナリオやナレーションなどの執筆も担当しています。
Lisa:Lisa Tveit Holfjordです。2020年に大学を卒業してすぐ、5人目の社員として入社しました。当初はコミュニティマネージャーと3Dアーティストを半分ずつ兼任していましたが、2022年から3Dアート制作専任になりました。
――開発開始時のチーム構成と、現在の体制について教えてください。
Robin: 開発開始時は、私を含め3人でした。アーリーアクセス開始時には5人体制で、最初の1年で10人まで拡大しました。現在、開発に関わっているのは11人です。
Josefin:私たちは意図的にチームを小さく保ち、全員が常にコミュニケーションを取れるようにしています。
また、基本的にチームメンバーは専門性を極端に高めるのではなく、複数の役割を兼任しています。例えば、プログラマーをやりつつUIデザインも担当する、といった形です。
Robin:ジェネラリスト、つまり複数の作業をこなせる人材がいることで、ゲームの異なる領域についてより深く理解できます。これにより、様々な形でチームを助けることができ、「このタスクを終わらせるまでみんなの作業が止まる」といったボトルネックが発生しません。
また、メンバー全員が多角的なアイデアを提案できるのも強みですね。
――開発にUnityを選択した理由は何でしょうか。
Robin:初期メンバーであるプログラマーのRichardが以前からUnityを使っていたため、当時はUnityを選ぶのが最も理にかなっていました。今振り返っても、『Valheim』にとってUnityがベストな選択だったと思います。
そのほかのツールとしては、3Dモデル制作にBlender、ペイントツールにKritaと、長期的なサポートが期待できるフリーソフトを中心に使っています。
――新機能やコンテンツの開発優先順位は、どのように決定されているのでしょうか。
Robin:どのバイオームを追加するかは、アーリーアクセス開始時にすでに決まっています。バイオーム追加がある大型アップデートの合間に入れる小規模なアップデートの内容は、6ヶ月前ごろから私、プロデューサー、デザイナーで議論します。
判断基準となるのは「今ゲームに必要なものは何か」「プレイヤーが求めているものは何か」「今実装すべきで、後回しにできないものは何か」です。
例えば、9月9日リリースの「Call to Arms」で行った戦闘システムのアップデートは、正式リリース時に入れることも検討しました。しかし、正式リリースの前に実装することで、プレイヤーに新しいシステムをテストしてもらえます。「将来に向けて準備する」という意味で、今実装すべきだと判断しました。
Josefin:また、私たちは誰でも自由にアイデアを提案できる環境を意識しています。
アイデアを思いついたメンバーは、チームに対してピッチ(短いプレゼン)を行います。ピッチの後は、そのアイデアを導入すべきかどうかをチーム全員で話し合って決めます。
――アイデアを積極的に受け入れる文化なのですね。
Lisa:そうですね。チームからはいつも多くのアイデアが出るので、アイデアを導入するスピードも重要です。私が提案した「爆弾を投げる」機能は特に早かったですね。
Robin:ピッチから実装まで約4週間でした。ただし最初の3週間は、Lisaが「これを実装しないと友達じゃない」とRichardを説得し続けた期間です(笑)。実際の開発は1週間程度ですね。
――アイデアを入れるかどうか、チーム内で意見が分かれることもあると思います。どう解決しているのでしょうか?
Lisa:意見が分かれたときは、納得いくまで皆で話し合って決めます。「Call To Arms」で追加したMob「熊」のアイデアはかなり前からあがっていましたが、ずっと結論が出ず「いったん保留」という形で検討を重ね続けてきました。また、グラップリングフックはテストまでしましたが、まだ実装していません。
Robin:意見が分かれるのは当たり前のことで、必ずしも悪いことではありません。意見が対立してもリジェクトされても、どんどんアイデアを出し続ける文化の方が大切だと考えています。
――アーリーアクセス開始前、どの程度の売上を予想していましたか。
Robin:正直に言うと、まったく予想していませんでした。私は「2万本売れてほしい」と願っていました。2万本売れれば、5つのバイオームを追加して開発を終わらせようと思っていましたね。
パブリッシャーのCoffee Stainでは社内で賭けをしていたようですが、最も高い予想でも6万本でした。それが、最初の1週間で50万本売れて、その後毎月100万本ずつ売れていったんです。
――まったく予想しえなかったとは驚きました。発売直前でも期待値は低かったのでしょうか。
Robin:本当に何の盛り上がりもありませんでしたね。SNSでの反応も薄かったです。ベータテスト用のDiscordには多くの人がいましたが、『Valheim』への期待が話題として表に出てくることはあまりありませんでした。
Lisa:盛り上がり始めたのは、発売の1週間前、PRチームから働きかけていたストリーマーたちが配信を始めてくれてからです。
――予想外のヒットを受けて、開発方針の変更はありましたか?
Robin:最初の6ヶ月間は、とにかくバグ修正に専念することになりました。ベータテストでは2,500人のテスターでしたが、アーリーアクセス開始時には50万人が同時にプレイしていたため、バグ報告の数が桁違いでした。
Lisa:これほど大規模なプレイヤーが参加すると、予想もしなかった遊び方や問題が発生します。例えば、木だけを延々と切り続ける人が現れて、薪が溜まりすぎてゲームがクラッシュするということもありました。
Robin:その後、「どうすれば『Valheim』を最良のものにできるか」を深く検討し始めました。そのうえで重要な点は、私たちは決して「お金が入ってきたからゲームを大きくしよう」とは考えていないことです。「自分たちが作りたいと思っている物語を最後まで作り上げる」ことが最も優先すべきことだと考えています。
――継続的な開発を続ける中で変化していったことを教えてください。
Lisa:メンバーが増えたため、進行管理を洗練させる必要がありました。以前は共有ドキュメントで計画を立てていましたが、現在はカンバン方式のような形で、誰が何をいつまでにやるかを全員が把握できるようにしています。
Josefin: 発売の1年後くらいから、パブリックテストブランチ(※)も導入しました。
※ リリース前のバージョンをプレイヤーがテストできる環境
というのも、最初の大型アップデート「Hearth & Home」をプレイヤーのテストなしでリリースした結果、1週間以内に緊急パッチを連続で当てる必要にせまられたんです。それを受けて、アップデートの内容をヘビーユーザーにテストしてもらうことで、多くのバグやバランスの問題をより早く発見できるようになりました。
――一方で、変わらない開発哲学のようなものはありますか。
Robin:私たちが持つ3つの指針はずっと貫いています。
1つ目は「Rule of Cool」です。面白そうだと思ったら実装することを原則にしています。ゲーム的な整合性より、プレイヤーが「おお!」と思える体験を優先します。
2つ目は「Good Enough」。完璧を目指して詰めすぎず、必要な条件を満たせばそれでOKとする、という考え方です。質より量で、どんどん追加コンテンツを入れていくスタイルをとっています。
3つ目は「Follow the Fun」。楽しさを保ち続けられるようにすることです。例えば、『Valheim』では装備の修繕コストがかかりません。死んでもアイテムを回収できます。本来のサバイバルクラフトとは異なっても、ストレスフリーで遊べることを重視しています。
――開発哲学を貫きつつ、プレイヤーからの様々な要望にどう対応しているのでしょうか。
Josefin:前提として、特定の少数派の意見が、必ずしも全体にとって良いとは限りません。そのため、いただいた意見をひとつひとつ取り入れるということはしていません。
代わりに、それぞれの意見が根本の部分でつながっていないかを分析します。根本の改善点を改善することで、できる限り多くの人の要望に応えられるようにしています。
――最後に、『Valheim』の開発を通して得た最も大きな学びと、これからゲーム開発に挑戦する人へのアドバイスをお願いします。
Robin:ゲームの規模を大きくしすぎないこと。小規模でも楽しめるゲームを、クオリティの高い状態でリリースすることが重要です。
ゲームの第一印象を作る機会は一度きりです。バグだらけのゲームをリリースすれば、「この開発者はバグ修正もせずにお金を取って売るのか」という悪い印象をプレイヤーに与えてしまいます。
また、前例のないアイデアでも、自分のビジョンに合っていると思ったら導入してみることも重要だと思います。
『Valheim』公式サイト『Valheim』Steamストアページコーヒーがゲームデザインと同じくらい好きです



西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。