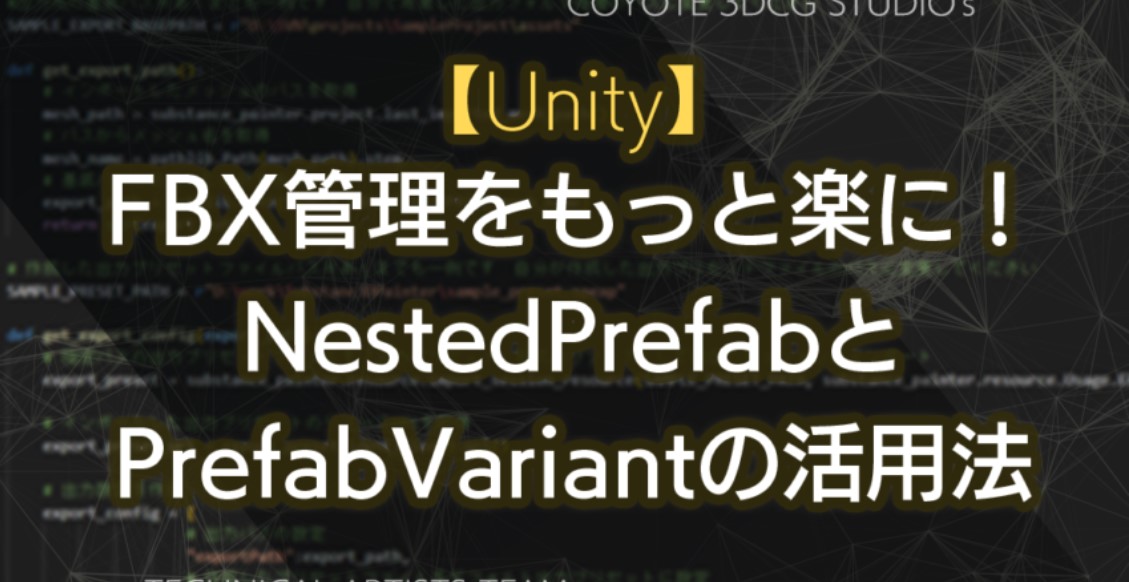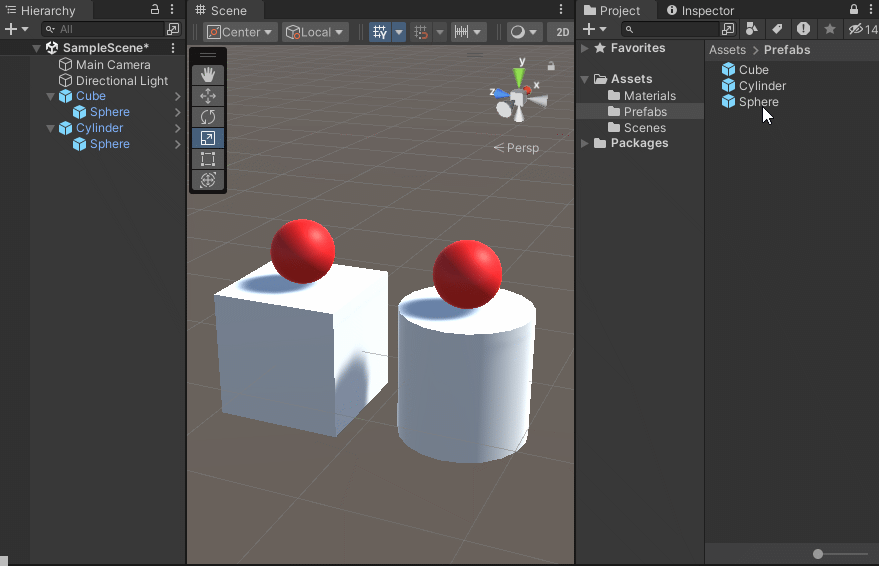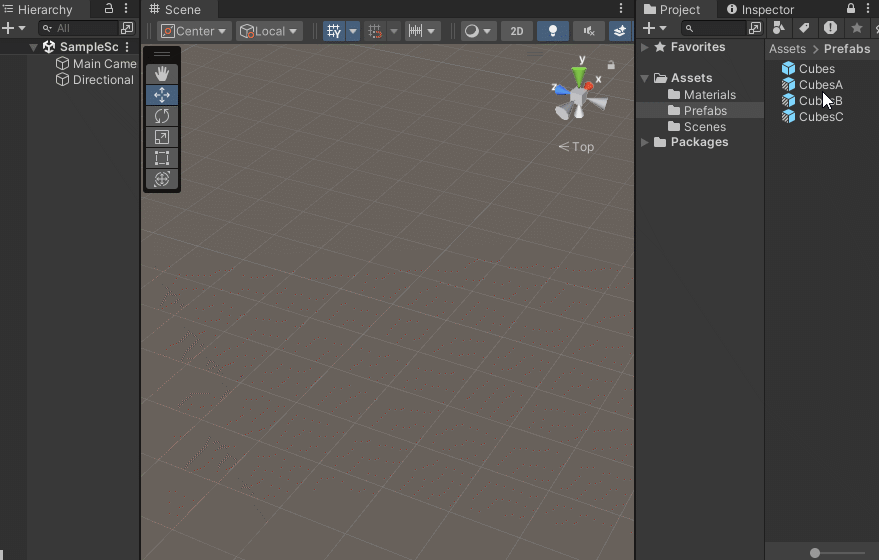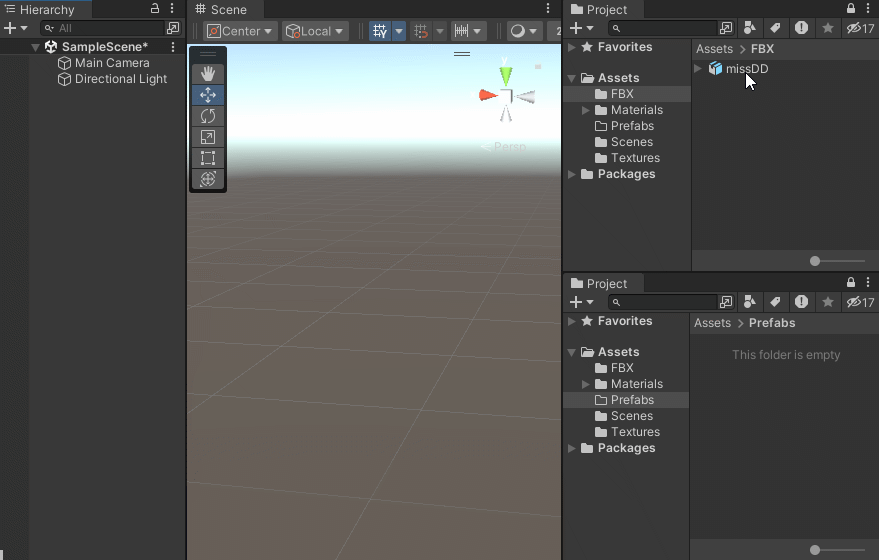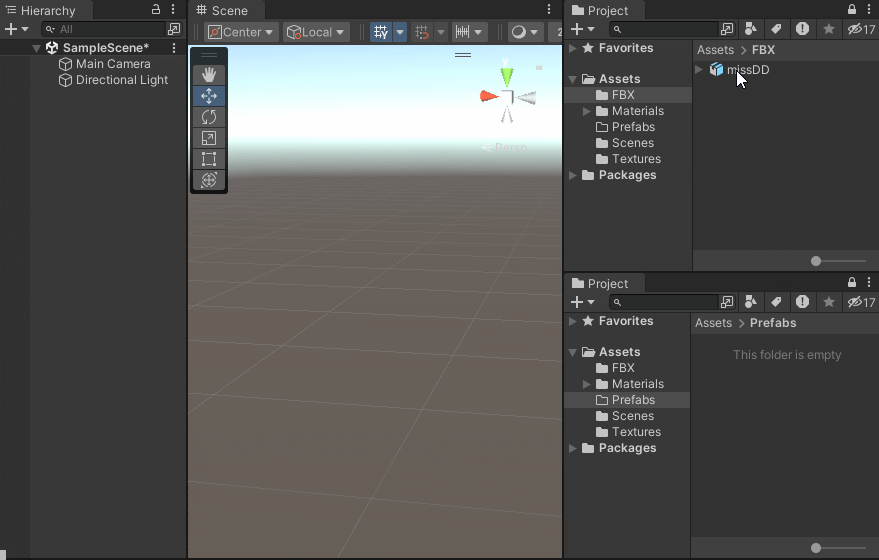この記事の3行まとめ
- クリーク・アンド・リバー社、UnityのFBX管理テクニックを紹介する記事を公開
- FBXからインポートした3Dモデルを、参照を残したままPrefab化する方法を解説
- Prefabに関する2つの機能、NestedPrefabとPrefabVariantを活用
クリーク・アンド・リバー社の「COYOTE 3DCG STUDIO」は、『【Unity】FBX管理をもっと楽に!NestedPrefabとPrefabVariantの活用法』と題する記事を、同スタジオの技術ブログにて公開しました。
(画像は公式ブログより引用)
ブログではまず、Prefab、NestedPrefab、PrefabVariantについての解説があります。
NestedPrefabは、別のPrefabを含んだ(親子関係を持った)Prefabです。複数のNestedPrefabが同一のPrefabを子にしている場合、子のPrefabに変更を加えるとそれぞれのNestedPrefabに変更が適用されます。
子のPrefabに加えた変更は親にも反映される(画像は公式ブログより引用)
PrefabVariantは、ベースとなるPrefabを継承し、一部に変更を加えた別のPrefabを作る機能です。ベースとなるPrefabに変更を加えると、継承したすべてのPrefabに変更が反映されるため、バリエーションを持たせた複数のPrefabを作成できます。
元のPrefabから赤い立方体を削除すると、PrefabVariantからも削除される(画像は公式ブログより引用)
公開された記事では、FBXからインポートした3Dモデルを、NestedPrefab、あるいはPrefabVariantを活用することで、FBXの更新が反映される状態でPrefab化する手法が紹介されています。
NestedPrefabを使う手法(左)とPrefabVariantを使う手法(右)(画像は公式ブログより引用)
同記事では、NestedPrefabを使う手法とPrefabVariantを使う手法について、それぞれの手順やメリット・デメリットなどについて解説しています。
詳細は、公式ブログをご確認ください。
『【Unity】FBX管理をもっと楽に!NestedPrefabとPrefabVariantの活用法』