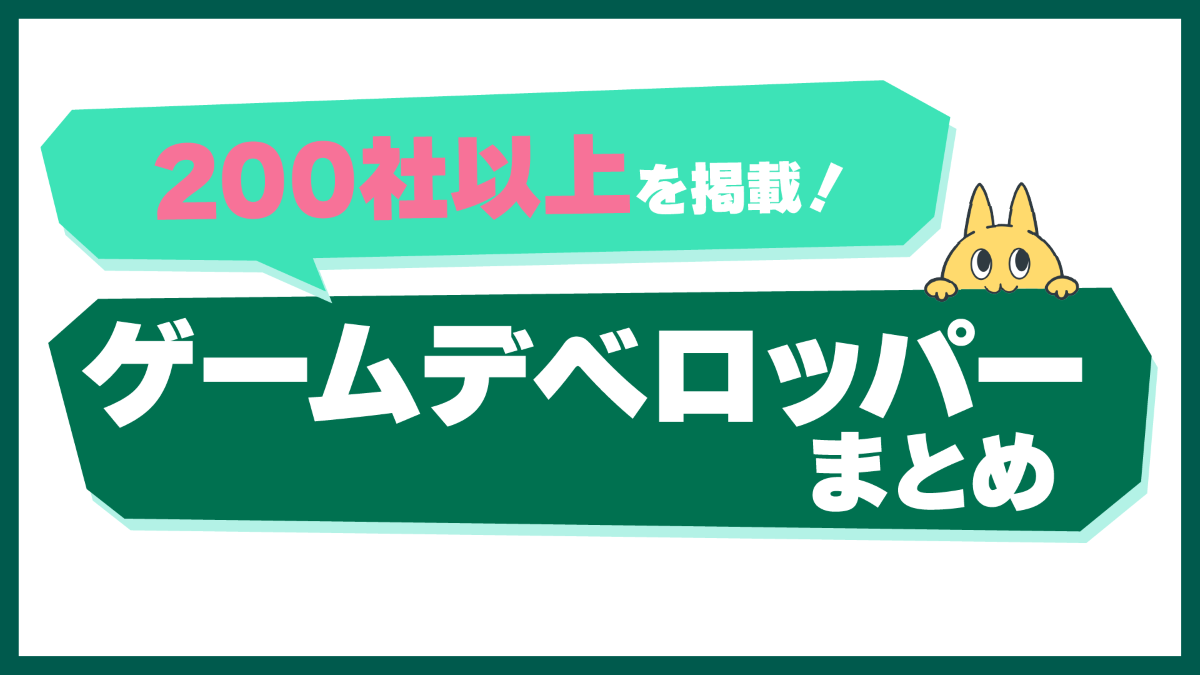2023年10月6日(金)〜8日(日)の3日間、北海道の札幌市産業振興センターにて、ゲームクリエイターの育成などを掲げるイベント『Sapporo Game Camp 2023』が開催されました。

本イベント内の企画の一つとして、プロクリエイターと一緒にチームを組み、3日間でゲームを作り上げるゲームジャムが実施されました。
今回、筆者はプロ側の立場として参加したので、そのときの体験を記事にまとめます。
2023年10月6日(金)〜8日(日)の3日間、北海道の札幌市産業振興センターにて、ゲームクリエイターの育成などを掲げるイベント『Sapporo Game Camp 2023』が開催されました。

本イベント内の企画の一つとして、プロクリエイターと一緒にチームを組み、3日間でゲームを作り上げるゲームジャムが実施されました。
今回、筆者はプロ側の立場として参加したので、そのときの体験を記事にまとめます。
TEXT / べる
EDIT / 藤縄優佑
ゲームジャムのスケジュールは、初日は開会式の後、19時30分から開発スタート。最終日の15時に作品の最終発表会が設けられています。
つまり、ゲーム開発にかけられる時間は、43.5時間ほど。なお、会場は22時に閉まり、閉じているあいだは自宅などでの開発が認められています。
チームで作るゲームのテーマはゲームジャム開始時に知らされることなどは、ほかのゲームジャムと同様です。
ですが、このゲームジャムならではの特色として、1チームにつき1名以上の「『Sapporo Game Camp 2023』の運営に協力しているゲーム開発会社のプロクリエイター」が必ず参加します。
『Sapporo Game Camp 2023』に運営協力した札幌市のゲーム開発会社(画像は『Sapporo Game Camp 2023』公式サイトより引用)
今回、僕はそのプロ側のデザイナーとして参加しました。
初日の10月6日(金)、開会式の19時より少し早めに会場に到着すると、今回参加する「チーム8」のテーブルに案内されました。
チーム8のメンバーは総勢8名。チーム番号と人数が一緒で覚えやすいです。メンバーは初対面で、プロのクリエイターとして熟練のプログラマーさんもいました。
チームメイト同士、お互い「はじめまして」と挨拶をしている間に19時となり、開会式が始まりました。
開会式が終わるとき、今回作るゲームのテーマが「増殖」だと発表されました。
「増殖」に沿ったゲームを、約43時間で、「はじめまして」の8人チームで完成させます。
テーマが決まったところで、チームメンバー同士で改めて自己紹介。各々が参加時に希望する役割と所属を教えてくれました。
8人の編成は以下の通り。
プロ以外は学生で編成された、フレッシュなチームです!ですが、このチームが珍しいわけではなく、一般参加者のほとんどが学生のようでした。
自己紹介も早々に、チーム8はまず「1時間をかけて、全員でアイデアを計50個出す」ことにしました。
そのとき、僕は勘違いして「1人で50個」のアイデアを出そうとしていました。28個のアイデアを出したところで勘違いだと気付いたため、50個すべて出さずに済みました。
集まったアイデアの中で支持を得たのは、「魔法の杖で雪玉を集めて、雪だるまの友達をたくさん作るゲーム」。テーマの「増殖」を「増やす」という動詞に置き換えて、「友達を増やす」ゲームを開発することにしました。
そして今回はプランナーの熱い要望により、マウスを魔法の杖に見立てた「専用コントローラー」を制作する案が浮上します。
専用コントローラーといっても、マウスそのものを改造するわけではなく装飾にとどめ、ゲーム中に行う操作はカーソル移動のみ。プログラマー班も「それなら実装できる」と判断し、専用コントローラーの制作が確定したのです。
予想外の企画を受けて「面白いなぁ」と思いつつ、翌日の10時半から「企画発表会」があることを思い出し、残り時間の少なさに少し焦りを感じました。
初日はスタート時刻が遅いため使える時間が少なく、実質2時間ほどで企画を決める必要があります。
企画発表会で使うスライドの制作・発表までの段取りをプランナーさん主導で急ぎ進めつつ、ゲーム開発にはUnityを使うことも決めるなどしてるうちに、会場が閉まる22時付近に。
Discordで連絡を取れるようにしておいて、データのやり取りはGoogleドライブを活用することにしたところで初日は解散。
10月7日(土)。ゲームジャム2日目。9時の開場と同時に会場入りします。企画が決まったので、デザイナーの僕はゲームの企画をビジュアルでチームに共有します。
ビジュアルはキャラクターでも良いし、コンセプトアートでも良いです。このビジュアルは企画発表会のときにも見せたいと考えています。
企画内容をチームで再確認・ブラッシュアップし、「専用コントローラー(装飾したマウス)を使う2人協力型ゲーム」と固めてから、ゲームで遊ぶときの状況や画面遷移図を、配布されている画用紙に描きました。
ゲームプレイの状況や画面遷移図をざっくりビジュアルに起こしたら、チームで共有、打ち合わせ、認識のすり合わせをします。
最終的な意思決定権を持つ「リーダー」を据えると開発がスムーズに進みやすいため、チーム8はプランナーさんがリーダーを務めることになりました。
企画を詰めている間に、デザイナーさんが魔法の杖のデザイン草案を描いてくれました。手がとても早く、プロとしてサポートする場面はほとんどありませんでした。
企画発表会用のスライド制作を終えたところで、企画発表会が始まります。実際に発表するのは各チーム1名だけなので、発表はリーダーに託しました。
発表会ではチーム名も命名・発表する流れが生まれており、チーム8はプランナー兼リーダーが着ていたTシャツにプリントされたゲームから、「だれでもいっしょ」とプランナーさんが命名。この名前は、「誰とでも一緒に遊べる協力型ゲームを作る」という意味も込められた、最高のチーム名だと思います。
発表は無事に終わり、プログラマー班はすぐに実装を再開しました。デザイナー班もUIやイラスト、3Dモデルの素材の制作に取り掛かります。
偶然にもチーム8は、手芸・プラモデル・デバイス制作が趣味のメンバーが揃っていたため、工作するために編成されたようなチームといえるでしょう。
ゲームジャムの神様が「専用コントローラーを作れ」と言っているに違いないと確信しました。
専用コントローラーである「魔法の杖」の作り方は至ってシンプル。
これだけです。棒でマウスを動かすだけでプレイできるゲームなので、クリック操作は不要で、かつマウス内部の改造も必要ありません。
ただし、1台のPCでマウスを2つ使う協力型ゲームにしている点が少々ネックなようで、一度に2つのマウスを認識させるのはUnityだと難しいらしいとのこと。その難しそうな仕組みの実装は、ベテランのプログラマーさんに一任しています。頼もしいです。
専用コントローラーを制作するため、デバイスの設計図が頭の中にあったプランナーさん、そしてデザイナー全員で材料の買い出しに向かうことにしました。
チームが実費で材料を用意する事情もあり、100円ショップで材料を揃えることに。マウスを装飾する構造は簡素なので100円ショップで事足りるだろうと踏んでいましたが、肝心のマウスが見当たりません。しかも無線マウスだと安定して動作しないようなので、有線マウスでないといけません。
調べたところ、有線マウスが売っている100円ショップを見つけましたが、最寄りでも会場から徒歩で40分ほどの距離。歩かず、時は金なりの精神でタクシーに乗る決断をします。100円ショップを使う理由が薄らいだ気もしますが……。
なんだかんだで3時間ほどかかりましたし、その後も僕は100円ショップと会場を何度も往復をすることになりましたが、ひとまず材料は揃いました。
柄部分は孫の手、装飾にはレジンなどを使った。思ったより材料を豊富に使っており、最寄りの大手100円ショップ3店舗はコンプリートした。なお、レジンを固めるUVライトも100円ショップで購入。こんなに工作に手間暇かけるゲームジャムは稀かもしれない
買い出しから戻ると、デザイナーさんがイラストで現状の画面設計を整理してくれました。
画面遷移図が完成したので、スプレッドシートで要件リストを作成しました。要件を可視化してみると、「脳内で考えてたより、必要な機能や素材が多い」ことに気付かされます。
これで作業量と進捗がつかめるので、ゲームジャムでの要件リスト作成はオススメです。
画面遷移図を貼り付けて、必要な機能と素材を、画面単位にメモしておくだけでも良いですね。
ゲーム内のデザイン部分に関しては、役割の配分を考慮し、UIや背景を2D素材、雪玉や雪だるまは3D素材で制作する方針としました。2Dの作業量に対して3Dの作業量を少なくしています。
学生のデザイナーさんは2人とも手が早く、自分で試行錯誤しながら素材をガシガシ作っていってくれたので、この時点でも僕が手を動かす必要はありませんでした。
その分、プロ雑用の力を発揮して足を動かしました。
夕方頃。組み上がっていくゲーム画面。そして魔法の杖、もとい専用コントローラー。
孫の手をマウスに取り付ける角度によって、マウスが反応しないことが判明するといった難所をなんとかプランナーさんの手によってクリアし、どうにか正常に動作しました。
皆の頑張りもあり、専用コントローラーは目途がつきました。
デザイン関連の進捗を確認し、僕は不足している素材(フォント、タイトルロゴ、背景、その他)の制作を担当し、ほかのデザイナーさんにはキャラクターイラストに注力してもらうことにしました。
サポート(買い出し)に回っていた僕がデザイナーとして役に立つときです。まずはゲームに使うフォントの選定から。
フォントには、「Google Fonts」を活用しました。これは商用利用も可能なオープンソースのフォントなので、ゲームジャムでなくともオススメです。
その後は、ゲームのタイトルロゴづくりです。といいつつ、そもそもタイトルを決めていなかったので、ChatGPTに計30個くらい案を出してもらいました。
この中で「結晶の絆」の人気が高かったので選出。少し印象を柔らかくしたいので「絆」を「キズナ」に変更し、最終的なゲームタイトルは『結晶のキズナ』に決定しました。
その間、プログラマーの方々は商用利用可能な無料の音の素材を選定してくれていました。そうした作業に没頭していると、あっという間に22時となり、2日目は解散しました。
6時半に目覚ましで起床。今から会場に行っても開いていないので、自宅でα版の発表会用に不足しているデザインの制作を開始します。
インゲームの背景はNovelAIの力を借りてベースを生成しました。イメージラフを取り込み、AIで画像生成、オリジナルのイラストに加工しています。
ロゴデザインはラフを描き、そのまま完成としました。清書する時間が残されていませんし。
約1時間で背景とロゴ、ボタンの素材を作成してGoogleドライブにアップロードしました。その後、バナナとヨーグルトだけの朝食をサッと済ませて、会場へ向かいます。
最終日のスケジュールは、α版発表会が10時半開始、最終発表会は同日の15時開始。最終版提出まで6時間を切っています。
泣いても笑ってもこれが最後!と、気合を入れます。
まずはデザインの進捗を確認したのち、自宅からアップした各素材をタイトル画面のラフに合わせて配置します。
ゲームのプログラムも、スタートからクリアまでの導線がつながりました!昨日の閉場後も、自宅で夜中まで頑張ってくれたプログラマーさんのおかげです。
専用コントローラーの反応も概ね良好です。準備万端の状況でα版発表会の時間を迎え、無事発表を終えられました。全16チームの発表が終わったのは11時半ごろ。
ゲーム開発に使える残り時間はおよそ3時間。
僕は100円ショップに向かいます。
そうして僕らチームの夢、魔法の杖(専用コントローラー)が完成しました。
最終発表会までの時間をフルに使い、なんとか完成にこぎつけました。直前にテストプレイをすると、「このゲーム、思ってた以上に面白い!」と、チームの予想を超える手応えを感じました。
本作『結晶のキズナ』は2人で協力して雪だるまを作る、シンプルなゲームです。ゲームでは、画面上部から降ってくる雪の結晶を2人がそれぞれ魔法の杖(専用コントローラー)でマウスカーソルを動かしてキャッチしていきます。
雪の結晶をキャッチするごとに、雪玉がどんどん大きくなります。
ある程度雪玉が大きくなったタイミングで、お互いの雪玉をぶつけ合うと、雪だるまが1体できあがります!
この雪だるまを、制限時間2分以内にどれだけ作れるか、という単純だけどつい熱中するパーティゲームです。
自然とプレイヤー同士の声がけが生まれ、挙動も気持ち良い点など気に入っています。
15時、ついに最終発表会が始まります。他のチームの発表を見ていると、紆余曲折があったんだろうな……と思う部分にあうたびに勝手に親近感を覚えます。
そんなことを考えているうちに、発表の順番が回ってきました。最終発表会は今までの発表会と異なり、チーム全員で会場前方の巨大スクリーン前に移動して話をします。
もちろん専用コントローラーも持ち運ぶので、壊れないかヒヤヒヤしつつ移動しました。
スクリーンに映像が映り難いトラブルもありましたが、ゲームの完成を皆に報告できました。こうして、チーム8「だれでもいっしょ」のゲームジャムは無事にゴールしました。
その後、20時の交流会では全チームが互いのゲームを試遊しつつ、他のチームやゲーム会社の方々との交流を楽しみました。
怒涛のゲームジャムを終えた翌日、ゲーム開発の意欲は落ち着くどころか「ゲーム作りたいなぁ!!!!」と燃える気持ちが湧きたちました。
僕はゲーム開発が好きですし、ゲーム開発に興味・関心のある人が集まる一種のお祭りといえるゲームジャムも好きなのです。
本記事を読んでゲームジャム未経験だけど面白そう!と思った方は、全国各地で多彩なゲームジャムが開かれるので、自分に合った条件のゲームジャムを探して、参加を検討してみてはいかがでしょうか。
今回のゲームジャム体験記で、少しでもゲームジャムの魅力が伝わったのなら幸いです。
どさんこ。KAWAII絵が描ける。冷やし中華とグミが好き。

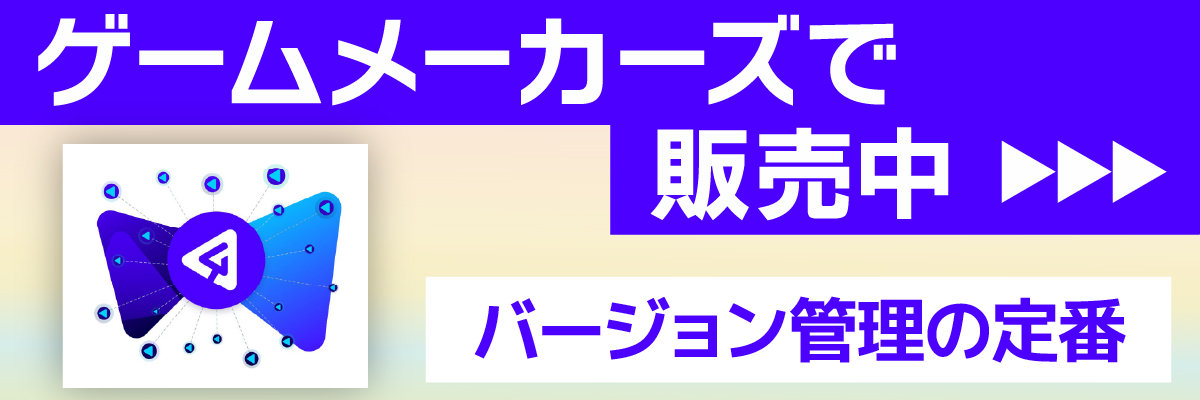

西川善司が語る“ゲームの仕組み”の記事をまとめました。
Blenderを初めて使う人に向けたチュートリアル記事。モデル制作からUE5へのインポートまで幅広く解説。
アークライトの野澤 邦仁(のざわ くにひと)氏が、ボードゲームの企画から制作・出展方法まで解説。
ゲーム制作の定番ツールやイベント情報をまとめました。
CEDECで行われた講演のレポートをまとめました。
UNREAL FESTで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
GDCで行われた講演などのレポートをまとめました。
CEDEC+KYUSHUで行われた講演のレポートやイベントレポートをまとめました。
GAME CREATORS CONFERENCEで行われた講演のレポートをまとめました。
Indie Developers Conferenceで行われた講演のレポートやインタビューをまとめました。
ゲームメーカーズ スクランブルで行われた講演のアーカイブ動画・スライドやレポートなどをまとめました。
東京ゲームショウで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
BitSummitで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
ゲームダンジョンで展示された作品のプレイレポートをまとめました。
日本と文化が近い中国でゲームを展開するための知見を、LeonaSoftware・グラティークの高橋 玲央奈氏が解説。
インディーゲームパブリッシャーの役割や活動内容などを直接インタビューします。